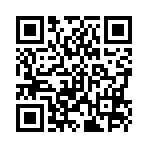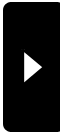2007年12月31日
207) 除夜の鐘
除夜の鐘というと、昔からNHKの「行く年来る年」で有名なお寺の鐘の音を聞くぐらいしかありませんでした。お寺には鐘つき堂があるのは知っていましたが、毎年除夜の鐘をつくとは知りませんでした。もっとも自宅からお寺が離れている為知る由もありませんでした。12月31日は大晦日の夜を1年の日ごよみを除く夜と言う事で除夜と言うようです。除夜の鐘は108回叩きますがそれは何故だかご存知ですか? 108という数が人の煩悩の数だというのは知っている事と思いますがその108という数の由来については色々な説が有るようです。108の煩悩は人間の感覚を司る眼(げん)耳(に)鼻(に)舌(ぜつ)身(しん)意(い)の六根が、それぞれに好(気持ちがよい)悪(いやだ)平(何も感じない)不同の3種があり3×6=18の煩悩となり、これが、また浄(きれい)染(きたない)の2種に分かれ18×2=36の煩悩となり、さらに、現在・過去・未来の3つの時間が関わって、36×3=108となり、それが、108の煩悩だといわれるようです。
今日は22:30にお寺に集合です。お寺は清水区今泉にある楞厳院です。23:45から鐘をつきはじめます。本来であれば108つで終わりですが、この楞厳院では、来られた方全員にうってもらいます。昨年は400名ほどが来られ、終ったのが1時過ぎでした。近所の住宅は迷惑な話かも知れませんが1年に1回のこと、大目に見てもらいたいと思います。鐘を力任せにうつ人もいますが、音が割れてしまいます。ゴーンという響きのある音は、力加減が必要です。
貴方も鐘をうちに来ませんか?
2007年12月30日
206) ビール類出荷過去最低を記録
我が家では、毎日晩酌することが無く、又、この夏も暑いと言ってビールの消費量が増えたわけではありません。逆に飲まない比の方が多くなったかも知れません。その一つの理由がこのブログであることは間違いありません。晩酌すれば横になりたくなります。すると、書く時間が減ってしまいます。又、外で飲んでも深酒は慎むようになりましたし、早く帰るようになりました。しかし、外で飲む回数は以前に比べて増えたと思いますが、消費量は確かに減ってます。
新聞記事で気になったことがあります。「少子高齢化に伴う人口減や飲酒運転問題などの逆風に押され、需要拡大にはつながらなかった」と書かれていました。20歳以上の飲酒者数は本当に減ったのでしょうか?又、飲酒運転問題が逆風という表現は、飲酒運転を肯定しています。飲酒運転問題がなかったら、需要は増えたということでしょうか?「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は当たりまえのこと、今年から設定された飲酒運転問題ではありません。記者の方の認識を疑ってしまう表現です。その記
事の意味の真意は何か聞いてみたくなりました。読者センターがありますので、明日でもメールしてみます。回答が来るかどうかわかりませんが....
ビール類の出荷量が下がったことは一目瞭然です。マスコミ各社も伝えていましたが、居酒屋でも若者の酒類のオーダーが変わり「とりあえずビール」が減ってきたと。明らかに居酒屋でのビールの消費が減っているというデータがありますのでそのことを理由として書くべきだと思います。12月も明日で終わり、忘年会も多く参加されたと思いますが、「とりあえずビール」だったでしたか?それとも.....
1月になって新年会になりますが、やはり「とりあえずビール」ですか?それとも、日本酒、焼酎、ホットワインですか?
2007年12月29日
205) 9日間の年末年始休日
さて、これからの9日間ブログは何を書こうか迷っています。多分日々の日記になると思いますので、今までのパターンとは少し異なりますが、ご了承下さい。
本日29日は、墓参りに行きお墓の掃除をしてきました。お墓は車で10分ほどの距離があるため、頻繁に行くことができず、9月に行ったきりでした。当方のお寺には墓守、お手伝い、ボランティアがいないため、活けた花はそのままで枯れていました。他のお墓もあちこちで同じ光景が目に入りましたので、当墓だけのことではありません。たまにしか墓に来ていない檀家さんが多いことを物語っています。お寺の住職に挨拶をして帰りましたが、帰り際に年が空け落ち着いたら、ちょっとご相談があると言って分かれました。話というのは、今後のお寺のあり方を話したいと思っているからです。お寺の檀家という考えが無くなってきており、お寺の運営に影響しつつあるからです。ことしは、東京の築地本願寺で「しんらん」というカフェがオープンし、話題となりました。ネットカフェのお寺も東京にあるようです。又、7宗派のお坊さんが集まってイベントも開催されたという話も聞きました。少しづつお寺が変わってきたという証拠です。ですから、当方のお寺でも、檀家さん相手のみではなく、昔のようなお寺の役割を再度考えたり、地域住民とのコミュニケーションも取れるようになればと思っているからです。
当お寺では、大晦日の日の23:45分から除夜の鐘を鳴らします。本来であれば108回で終わりですが、当お寺は凝られた方全員に鐘をうってもらいます。例年400名程が訪れます。よって最後の鐘が鳴るのが1時過ぎとなります。境内では、お汁粉、甘酒が配られます。
エスパルスドリームプラザでのカウントダウンに行かれる方も多いと思いますが、貴方も除夜の鐘を叩いてみませんか?
2007年12月28日
204)各種10大ニュース
毎年年末になると新聞紙上で各新聞社が今年の10大(重大)ニュースを掲載します。そして故人を偲ぶ意味で、亡くなった方々の紹介もされます。読売新聞社は1947年以来、毎年の10大ニュースを読者の投票により選定しています。その読売新聞社によれば今年の10大ニュースの1位から5位は
1)安倍首相が突然の退陣、後続は福田首相
2)「不二家」が洋菓子販売休止、老舗「赤福」等の偽装相次ぐ
3)年金記録漏れ5,000万件
4)参院選で自民歴史的惨敗、民主第1党に、与党は過半数割れ
5)守屋前防衛次官逮捕、ゴルフ接待389万円収賄容疑
とのことでした。その他には中越沖地震や、宮崎県知事にそのまんま東氏、横綱朝青龍2場所出場停止、民営郵政スタートなどが挙げられていました。こちらでも、やはり明るいニュースはありませんね。人間の記憶は、悲しいもの、暗いもの、人の不幸のほうが明るいものより強いようですので、仕方ありません。明るいニュースを思い出そうとしても、なぜか出てきませんね。よって人の記憶による10大ニュースであれば明るいものは少なくなることが証明されます。
ネットで10大ニュースを検索すると、各社新聞社は当たりまえですが、「インテルが選んだ10大ニュース」、「オーディオ、ヴィジュアル10大ニュース」、「SEM業界10大ニュース」、「音楽界の10大ニュース」、「ケイタイ10大ニュース」などいろいろなものが出てきます。静岡新聞夕刊の茶況には「茶業に関する10大ニュース」が載っていたことには驚きました。皆さん関心があるということですね。日経BP ON LINEでも、1年間に紹介した記事のページビューが多いものをランキング化したものが10大ニュースとして発表されていました。又、2007年にご紹介した47冊の「超ビジネス書」の中から、読者からいただいたページビューが多かったものも紹介されていました。今年は、身近な「通勤」に潜むリスクを取り上げたあの本がトップとなったようです。ほんのトップ5のタイトルは
1)『ぼくは痴漢じゃない!』
2)『嘘だらけのヨーロッパ製世界史』
3)『ホームレス中学生』
4)『生きさせろ!』
5)『いらっしゃいませ』
となっていました。3)の「ホームレス中学生」は話題となった漫才の「麒麟」の田村裕氏が書いたものです。詳しくは、以下を参照頂きたいと思います。読書好きの方であればこれらの本は読まれたことでしょう。読書嫌いな当方は1冊も目にしておりませんでした。
超ビジネス書レビュー2007年PVランキング: http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20071226/143953/
ちなみに、「Walterの10大ニュース」を考えてみましたが、トップに来るのは「ブログを毎日書き始めた」ことになると思います。その他、試験に受からなかったことがありますが、それ以外はこれといったことが思い出されません。平凡な1年だったということでしょうか?それとも単に覚えていないということでしょうか?
貴方の10大ニュースは何ですか?
2007年12月27日
203) 軽自動車のシェア(スズキがNo.2に)
販売台数の数字で見ると、スズキは2005年より毎年販売台数が減少しています。軽自動車だけでなく「スイフト」や「SX4」などに生産をシフトしたからという理由もあるようですが、供給が間に合わない為、販売機会を逃したのであれば、その理由も正当化できますが、単純に販売台数が減ったことの理由が生産体制としたらおかしな事とあります。今年2007年では販売台数60万台をきる見通しのようです。それに引き換え、ダイハツはは2002年を底に年々販売台数を伸ばしています。そして今年2007年は60万台を超える見込みであり、スズキを抜くという結果になるそうです。
以前業界関係者に聞いた話ですが、スズキとダイハツとでは根本的に大きな違いがあるとのことでした。それは企業力の違いであるということ。ダイハツはトヨタグループの一員であることが大きな強みです。最大の違いは同じ部品であれば、多分ダイハツのほうが安く買えると思われます。総コストが下がれば、利益が増えます。利益が増えれば投資を増やすことが出来、良いものづくりのサポートが出来ることになります。もし、価格競争になってもダイハツが有利であることは間違いないと思われます。来年2008年にスズキがどんな手を使って、シェアNo.1を奪回するか見ものです。鈴木会長が、2006年の軽自動車減産表明の際に「軽自動車よりも輸出向けの小型車の方が利幅が高い。シェアトップという名誉よりも実益を取る」と述べたそうですが、実際、欧州を中心に販売が拡大し、現地工場では生産が追いつかず、日本からの輸出で対応していることから考えると、もしかしたらNo.1を奪回するより実益を取り、利益を増やした後、シェアNo.1奪回に力を注ぐかも知れません。
軽自動車メーカーの「スズキ」なのか、それとも自動車メーカーとしての「スズキ」なのか、どちらを選択するかは経営者次第ですね。この選択はジャッジに苦労することでしょう。軽自動車の市場が全世界に波及するのであれば、軽自動車に特化しても良いかも知れませんが日本だけの現象であれば、スズキの選択は二重丸となります。日本の携帯電話メーカーが世界でメジャーになれなかったのは、通信システムの違いはありますが、国内に特化してしまったからです。それを考えると、シェアNo.1より実益を取ることになるでしょう。いつでもシェアNo.1は奪えると思えば、戦略を立てやすいですね。
はたして、来年の終わりはどうなっていることでしょうか?
2007年12月26日
202)2007年の新語10選
新語ウオッチャーであるもり・ひろし氏の2007年どの新語10選が日経BPnetに掲載されていました。これhあもり氏が、個人的な観点で選んだ「今年の新語」で、選出にあたって考慮した条件は3つで、第1に、今年その言葉が話題になるきっかけがあったこと。第2に、その言葉が今後しばらくは定着しそうであること。第3に、その言葉に対する社会的関心が大きかったことだそうです。新語から浮かび上がった今年の世相は「信頼関係の分断」だった。
1)モンスターペアレント - 協調関係の崩壊が怪物を生む -
2)ワーキングプア - いちど転落すると抜け出せない -
3)ネットカフェ難民 - 住居からも切り捨てられる人々 -
4)氷河期世代 - 労働市場から取り残された世代 -
5)2007年問題 - 団塊世代の大きな影響力 -
6)学校裏サイト - 子供社会の闇サイト -
7)赤ちゃんポスト - 社会の中で孤立する母親 -
8)猛暑日 - 意地の独自命名 -
9)メガ食品 - 健康志向からの逸脱が生んだ流行 -
10)KY - 若者にも受け継がれるムラ社会の空気 -
これら10の言葉が今年流行したものとは驚きました。中にはこのところ頻繁に聞く言葉もありますので、もっと前から使用していたのではと錯覚してしまいます。2007年問題は以前より言われてきましたが、実際問題となったかどうか定かではありません。当社では全く問題がなかったのではと思っています。KYはほんのつい最近テレビなどで称され始めたのではないでしょうか?知らない人もいるかも知れません。もり氏が「今後しばらくは定着しそうである言葉」を条件にしましたが、まさにそれぞれ定着するのではないでしょうか?その中でもワーキングプアーがこれからますます使用されるのではないでしょうか?ほんの先日、NHKでも特集をしており、日本のみならず世界各国の現状を放映していました。
ふとこれらの言葉を注意してみると、すべてネガティブな内容の言葉ばかりです。メガ商品のみその対象にはなりません。全般的には景気が良かった1年ですが、世相はその逆を反映しています。それとも悪いことばかりが基本であるかも知れません。何か明るいニュースによる良い新語はないものかと思いますが、思い当たる節がないほど今年は悪いニュースばかりだったということになります。今年の一字が「偽」と言うこともあり、2007年をすべて「偽」として語っても良いかも知れません。良いといっていた景気も実は「偽」だったかもしれません。儲かった会社はほんの一部の大手企業ばかりと言うデータもありました。信者が儲かると言う理屈ですので景気の良かった会社は「偽」は全くなかったということになります。マクドナルドは当てはまらないようですが.....
もり氏は以下のように結んでいました。
「例えばモンスターペアレントの背景には、学校と保護者との信頼欠如がある。またワーキングプア、ネットカフェ難民、氷河期世代の背景には、政界や経済界が労働者に対して抱くべき「情」の欠如がある。さらに学校裏サイトでは生徒同士の信頼が崩れているし、赤ちゃんポストでは「信頼できる社会」を持てない母親が孤立している。信頼関係が薄らぐ社会の中で、若者が必死に空気を読もうとするからこそ、KYという言葉も必要になったのではないか?」と。
来年はどのような新語が生まれるのでしょうか?明るい話題の新語が生まれることを望みます。
2007年12月25日
201) 白熱球がなくなる
新聞によると、切り替えの期間は今後詰める用ですが、3年以内とする案も浮上しているようです。温室効果ガスの排出削減を義務付けた京都議定書の約束期間が来年から始まるのを控え、排出量が急増する家庭・オフィス部門の対策を強化。全世帯が電球形蛍光灯に切り替えた場合のガス削減効果は、家庭からの排出量の1.3%に当たる約200万トンとみているようです。家庭で使う電球形蛍光灯の価格は白熱電球に比べ10倍以上と高いため、消費者の反発を招く可能性もあるとのことで慎重に進めるようですが、多分強行採決されるので鼻以下と推測されます。日本電球工業会によると、2006年の白熱電球の販売個数が約1億3,500万個なのに対し、電球形蛍光灯は約2,400万個にとどまっているようです。大手家電メーカーの試算では、白熱電球の消費電力は電球形蛍光灯の約5倍で、10,000時間使った電気代は一個当たり9,600円高く、蛍光灯は寿命が10倍で取り換えも少なくて済むと言っているようです。
当方でも白熱球をしようしている照明機器がいくつかあります。その中で、代表的なものが居間にある照明機器です。定格では60W球を6個計360W使用する照明機器です。なぜかこの電球が頻繁に切れるのです。以前はあまりにも頻繁であったため、取り替えた日をマジックで書いたりしたのですが、ばかばかしくなって止めてしまいました。その為、最低4個はストックしています。切れた時にすぐ取り替えられるようにと。1個100円ほど、2個パックで180円位で販売されていますので、価格としては安いものです。ただ、同じ明るさであれば、現在市販されている赤色系蛍光灯のほうが長寿命であることはわかっていましたが価格が高いためずっと白熱球を使用しています。今回の試算では蛍光灯にした場合トータルコストは減るということでしたので、検討していたところ、ふとしたことで挫折してしまいました。
当家では暗くなると点灯するフットライトを取り付けています。先日調子が悪くなり、メーカーのお客様相談室に問い合わせ、ついでに現在使用している照明機器の白熱灯を蛍光灯に替えたいことを尋ねると、「その照明機器では蛍光灯を使用できません」と言う回答でした。規格にあわないとのことでした。すると、もし、白熱球が生産中止になると照明機器を買い替えなければならないことになっています。居間の照明機器はファンつきのものですので10万円以上します。壊れていないのに買い替えるわけには行きません。地球温暖化防止には協力したいのですが、10万円あれば温暖化防止のための植林が何本出来ることになるのか計算すると植林の方が地球のためになるのではないかと考えてしまいました。
技術の進歩でなくなる商品があっても差し支えありませんが、強制的に無くすのはどうかと思います。省エネルギー、温暖化防止のことは重要なことです。しかし、そのほかの対策ももっとあるのではないでしょうか?オイルショックを契機に深夜放送がなくなりました。電飾看板の自粛もあったと思います。白熱球から蛍光灯に替えることで家庭からのガス排出量が1.3%削減できるようですが、現在の生活から3%電気を使用しない生活をすることのほうが簡単ですし、決して無理なことではないと思っています。もっと根本的な対策を考えることは出来ないものでしょうか?
2007年12月25日
200) なばなの里(三重県)のイルミネーション

妻に誘われ、アンビアツアーの長島スーパーランドに隣接するアウトレット「ジャズドリーム長島」と日本一と言われているなばなの里のイルミネーションツアーに行ってきました。なんと280万個の電球(LED含む)を使用したイルミネーションです。御殿場の「時之栖」の2倍の電球を使用しているとのことですので驚きです。
入場料がツアー料金に含まれていたため、入場料がいくらかわからなかったのですが、帰りに調べたところ2,000円で1,000円相当の園内で使用できる金券付とのことでした。日暮れおよそ17:00より点灯されますが、多くの人でにぎわっていました。巨大な駐車場は一杯であり、入場件売り場は長蛇の列、園内に入ると流れは一方通行ですがのろのろ走行(皆写真を撮るため立ち止まるため)で、まるで人ごみを見に行くような場でもありました。自由時間は1時間30分ほどありましたが、平日であれば充分見ることができたかと思いますが、本日は祝日であり、又、クリスマスイブということもあり多くの観光客が集まり、1時間30分では時間が足りませんでした。入場者数は正確にはわかりませんが4~5万人はいたのではないでしょうか?当方18:30に
帰りましたが、まだまだ来る人の渋滞があり、夜は21:00まで開催されているため、もっと多くの入場者があったかも知れません。

渋滞、人ごみに耐えられる方は一見の価値はあるのではないでしょか?
来年3月2日まで毎日開催されるようです。来年になればぐっと入場者数も減るのではないかと思いますので、これから出かけても充分と思います。
なばなの里 http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/illumination/index.html/

白い電球の光のトンネル

白い電球は花型
2007年12月24日
199) 映画 ムービー シネマ
当方、昔から映画好きでテレビをつけるときはケーブルテレビの映画チャネルをいつもチェックします。BGM代わりに映画チャネルかけていることが多いです。地上波でも必ずと言っていいほど夜9時からの映画番組を新聞でチェックします。今回の「ナショナルトレジャー」第1作目を見てファンとなりました。サスペンスも好きですがどちらかというとアドベンチャーものが大好きです。ニコラスケイジも好きな男優の1人で、「コンエアー」から見始めたと思います。しかし、「911」だけは見る機会を失ってしまいました。確か、「ナショナルトレジャー」の1作目は映画館で2度見て、ストーリーを確認しました。その後ケーブルテレビでも、何度か見てます。まさか第2作目ができるとは思ってもいませんでした。それにしてもこのようなストーリーを考える作者はすばらしいと関心せざるを得ません。
映画館で2度見たものとしては「ロードオブザリング」があります。第1作目を見たとき感動しましたが、内容が今ひとつ理解できず2度見たことが始まりです。その後3作続きましたが、2度づつ見ています。この映画は当方の好きな映画の一つです。後、1度見ただけでは内容がわからなかったものに「パイレーツオブカリビアン」があります。2作目と3作目は2度づつ見たと思いま。2度見たということは好きな映画ということになります。映画館ではなくテレビで観た映画で最も回数の多いのはヒューグランドとジュリアロバーツ主演の「ノッティンヒルの恋人」です。少なくとも5回以上は見ています。先月もケーブルテレビでやっており、又見てしまいました。嫌いなシーンはチャンネルを変えたりもしています。
今日久しぶりに映画館に行き、映画の楽しさを改めて感じました。Movix清水ができたとき、嬉しくて最低月1回は見に行っていました。しかし、今年は数えるほどしか見に行っていません。それもいわゆるメジャーなものばかりです。見損なった映画も数知れません。以前では見損なった映画は必ずレンタルビデオで借りて見たのですが、現在は借りても見る時間が無いため借りません。とても残念なことですが、休みが充実している証拠であると思っています。50歳以上は、妻と一緒だと夫婦割引で二人で2,000円です。ですから、もっと見に行きたいのですが....
いつもDVDで映画を見ている貴方、たまには映画館に行って見ませんか?映画も良さがより一層感じられますよ。
2007年12月23日
198) 愉快な仲間達
今日は、久しぶりに家庭菜園に行き、ダイコン、ニンジン(ウサギの餌ほどしか成長していません)、サトイモ、しょうが、キャベツ(まだ玉になっていない)、ハクサイの収穫をしてきました。その後、県立大学の社会人ビジネス講座の最終回に出席し、前回の講座で知り合った4名(12/6の焼津の工場見学に行ったメンバー)で、講座の打ち上げ兼忘年会をしてきました。他の受講生にも「懇親会をやりましょう」と急遽声をかけましたが、集まったメンバーはいつもの面子でした。今回も講師の先生から「この講座の意義は?」の問いかけに「講義のほか異業種の人と知り合いネットワークを作る事も大事」と言われていたのですが、ちょっと残念です。
2時間にわたり色々な話ができました。とあるTさんは音楽が好き、特にロックが好きとのことでギターも昔かじったとのことでした。「そろそろギブソンのギターが欲しくなるのでは?」と問いかけたところ、社会人になったすぐに購入したとのことでした。それも当時(20年以上前)で200万円ほど投資したとのことでした。そのギブソンのギターもたまには押入れから出してメンテナンスしているとのこと。今では、単なる中古品かプレミアム品になっていることと思います。その他、お茶の話、鰹節の話、我々の年代だとすぐ話題になる健康の話、など話題が豊富でした。
これからも多くの人たちと交流を持ち、続けていきたいと思います。
皆さんもネットワーク作りしていますか?
2007年12月21日
197) 社員が辞めるのは上司の責任 -声かけ-
それは、「社員が辞めるのは上司の責任である」との意見です。小山氏曰く「社員は待遇や仕事内容に不満があっても、それだけでは辞めない。むしろ、人間関係がしんどいとか社内の風通しが悪いとかコミュニケーション不全に由来する退職のほうがずっと多い」ということです。心当たりありませんか?
コミュニケーション不全は多くの場合、上司に責任があります。一般社員のコミュニケーションスキルが低いのはある意味で当然であり、それを上手くフォローすることが大切です。いや「大切」というよりは、「上に立つ者としての当然の義務」です。 「周囲に溶け込んでいないな」と見れば溶け込む工夫をし、「人間関係に悩んでいる」と判断すれば相談に乗る。こういうキメ細かな配慮をし、部下がやりがいや充実感をもって仕事ができる環境をつくることが上司の仕事です。よく「部下に辞められると自分のマネジメント能力が問われる」と渋い顔をする管理職がいます。そういう人は、果たして自分が上司としての務めをしっかり果たしていたかどうかをまずは自問するべきです。上司としての仕事をおざなりにして自己保身に走るとは笑止千万もいいところです。と言っています。
そこで、小山氏は毎日、部下全員に声をかけることを日課としたそうです。しかし、上手くいかなかったようです。というのは当時の部下にしてみれば「上司から声をかけられる」は、「面倒な仕事を押し付けられる」「説教される」と思ったからです。しかし、あきらめずに毎日声かけをしたところ、社内のコミュニケーションは非常に良くなり、辞める社員は飛躍的に減ったようです。「小山は説教をするわけではない」「大部分は馬鹿話だ」ということが分かり、話しかけられることを嫌がる社員がいなくなったと言うことです。
コーチングでは、うなずき、承認、聞き上手になることを教わりますが、超えかけも重要な要素になっています。小山氏のやられていることは、そのままそっくりコーチングに当てはまっています。だから、小山氏はよきコーチであり、よき社長であることがわかります。小山氏の講演、セミナーはいつも「満員御礼」のようですが、わかる気がします。当方にも、挨拶が出来ない(しない)スタッフがいますが、当方もあきらめずに日課として続けていこうと思います。声かけについても、コーチングのセミナーで習った時は試みるのですが、何時しか適当になってしまっています。反省し、心して取り組みたいと思います。
小山氏は最後に以下のように結んでいました。「勉強するのは、もちろん良いことです。しかし人は、勉強しただけでは変わりません。勉強したことを実行して初めて変わるのです。人が変わらなければ、組織は絶対に良くなりません。ここを誤解してはいけません。」と。
人を変える前に、まず自分から変え、組織を良くしたいものですね。
2007年12月20日
196) お正月のしめ縄飾りづくりのお手伝い
当方12月になると土曜日、日曜日はその作成のお手伝いに毎年行っています。もう10年以上は経過しましたので、いわゆる年中行事となっています。12月は親戚のみかん切りと家庭菜園の白菜、大根、キャベツの収穫もありますので、ほとんどスケジュールが埋まってしまいます。今年は、12月の土曜日が静岡県立大学の社会人講座で3回とられてしまい、実質妻の実家に行けるのが先週の日曜日と、今度の日曜日しか行けません。妻は土曜日も行っています。
お正月のしめ縄飾りと言っても種類が多くあります。玄関先に飾るものでも半間のもの、一間のもの、そしてこのところ多くなったのがドアに取り付けるものです。その他、輪飾りといって、小さなものもあります。
お正月のしめ縄飾りや、おせち料理にはそれぞれ意味があるようで、しめ縄に付いているゆずり葉は「家計が絶えない」、うらじろは「長寿」、橙は「代々続くようにとのことで繁栄」との意味があるそうです。今回の作業は、まずうらじろとゆずり葉を輪ゴムを使い一つにする下準備を午前中しました。そして午後からは編んだしめ縄に橙と共にその下準備したうらじろセットを取り付け完成品としました。すべて手作業であり、この工程では機械化できるものがありません。よって人頼みと言うことになります。この縁起物である、お正月の飾りも、中国で作らせている業者が出てきたそうです。藁で作ったしめ縄以外はプラスチックを利用するものもあるようです。今は少なくなりましたが、自動車につけているものでそのようなものを見た記憶があります。縁起物もコストで中国製になってしまうのかと思うとやるせないですよね。時代は移っていますが、こればかりは伝統的なものですのでずっと残したいと思うのですが.....
妻の実家では12/25ごろまでは出荷作業で大忙しです。
ゆずり葉 うらじろ




完成品

2007年12月19日
195) 聞く力をアップさせる(新人営業研修では)
顧客とのコミュニケーションを深めるためには「聞く」スキルがなければ進みません。聞き上手になるには、まずは「はい」と返事をして、「はい」の返事が単調になったら時々相槌をいれ「なるほど」、「ほんとですか」と肯定的な雰囲気で表現を変えてみることだそうです。ただ、若い人の間で良く使用される「マジッスカー」は顧客に不快感を与える禁句であるとのこと。「マジッスカー」が口癖になっている営業担当者がいたら、徹底的に注意して言葉遣いを指導しなければなりません。
状況によって、うかつに「はい」がいえない場合は「違います」とも言えず、困りますよね。その場合は「なるほど、そういう見方もありますね」、「そういう考えもありますね」と返せば「イエス」でもなく「ノー」でもない表現となります。顧客が質問の回答に困り黙ってしまった場合は、あせって墓穴を掘る場合があるので、ただ黙って待ってれば良いそうです。当方も経験がありますが「この沈黙を何とかしたい」と思い、余計なことを言って、もっと気まずくなったことがあります。相手も長時間黙っているわけにもいかず、何かを言い出すのを待っていれば良いそうです。はたしてそれが出来るかどうかですが....。とかく営業担当者にはおしゃべりが多いの我慢できるかどうか見ものですね。
顧客の本心を察するにはちょっとしたしぐさにも注意を払いましょうとのこと。無意識に出るしぐさに心理が隠されています。
例えば
貧乏ゆすり:不安、苛立ち、落ち着きがない
唇をなめる:緊張、気持ちが悪い
首をすくめる:受け入れ拒否、不信・不安
腕を組む:相手を拒否、自分の枠を守る
耳をかく:相手のことを受け入れない
何かをいじる:不安、緊張、面白くない
とのことだそうです。思い当たる節がありませんか?
以前、当方も重要な依頼で上司と客先に訪問したとき客先から「はい、はい、わかりました」と返事をもらったことがあります。客先を出たあと、上司に「今回の依頼はだめでしたね」と言ったところ、上司は「『わかった』と言ったじゃないか」と言いましたが、「『はい、はい』と繰り返しましたので、うんざりしているのですよ」と答えたことがあります。ほんとに、しぐさ、言葉遣いから察する心理は難しいですが、当方はとても面白いと思っています。それを理解して、今後どのように展開するかそこが営業の醍醐味であり、腕の見せ所なのではないでしょうか?
貴方の会社の営業担当者、聞き上手になっていますか?
2007年12月18日
194) 風邪をひいた
先生の問診を終え、熱があることから「インフルエンザの検査をしましょう」とのことで、鼻の奥深い粘液を採取されました。結果、インフルエンザではなく、単なる風邪でした。菌がおなかに入っているとのことで、本日の昼食まで計3回食事抜きを言われ、また、水分補給のために食事時にポカリスエットを飲むよう言われました。家に帰ってすぐ横になりました。今日は朝いつもどおりに起き、犬の散歩をして出勤しました。そして、本日の夕食はおかゆを食べた次第です。3回食事を抜けば少しはやせるかなと思いましたが、たいした変化はなく、又、3回抜いたにもかかわらず、夕飯時はたいして空腹感もありませんでした。どうなってるんだろう?今までの1日3度の食事はなんだったんだろうと。
折角土曜日に届いた液晶テレビもまだ、1時間と観ていません。結局37インチにしたのですが、それで正解でした。その上のサイズであった大き過ぎたと思います。当方ケーブルテレビですので、ケーブルテレビのチューナーの電源を入れないと、地上波6局がデジタル放送で映ります。東京12チャンネルのみは地上波扱いとのことでデジタルでは見れません。その画質は、以前のブラウン管テレビの方が観やすかったという状況です。BS放送はなぜかNHKの3局のみノイズが入ってしまうため、ケーブルテレビのカスタマーセンターに問い合わせました。「たまに、入出力端子の接続が逆だと可能性がありますので再度調べて下さい」とのことでしたが、調べてみても逆になっておらず、その点が現在不満です。一度サービスマンにチェックしてもらおうと思っています。
そんなわけで、体調も戻りましたので、又、いつもどおりのブログを再開したいと思います。
2007年12月16日
193)お休みブログ
作成のお手伝いをしたのですが、帰りに急に寒気がしてしまい、軽い夕飯を摂って
すぐ休みました。少し楽になりましたので、この記事を書いていますが、今日は
ここまでとさせていただきます。
2007年12月15日
192) ライフコーチ、キャリアコーチ
当方も以前よりコーチングはかじっており、知り合いのコーチが藤枝の公民館でコーチングの講座を開催するとのことで、今年の5月から毎月1回計8回の講座にお手伝いとして参加しました。一昨日はその最終回であり、又、本日は打ち上げを兼ねた忘年会が藤枝で開催されました。コーチングの基本はうなづき・傾聴です。そして回答を本人自らが出すようにすることです。いろいろな先生の講義を聞きましたが、人それぞれの経験に基づいた話を聞くことが出来、今回もお手伝いと言っても、先生の話を聴講して自分も勉強になったといったほうが多いのではないかと思っております。今回の講座を通じて「誉める」重要性を学びました。「おだて」との違いの「誉める」です。普段誉めることのない当方にとってはこれはとても難しいことですが、家族に対して少しづつ試みてみようと思います。「黄金の水」と「泥水」のたとえがありましたが、どちらかと言うと「泥水」を浴びせていたと思います。すると「泥水」が返ってきますよね。だから、何とかして「黄金の水」を与える努力をしたいと思っています。
ライフコーチ・キャリアコーチの話に戻しますが、アメリカではキャリアコーチの数は爆発的に増加しており、キャリアコーチの国際的業界団体、国際コーチ連盟(ICF)によれば、同連盟の加入者数は毎月400~500人のペースで増加しているといいます。ICFが今年2月に発表した初の集計結果では、全世界で3万人ほどのキャリアコーチがいると推定され(ICF非加入者を含む)、全体の売上規模は15億ドル近くに上り、その約半分が米国内で稼ぎ出されているとのことです。「キャリアコーチ」とは何か?どのような資格で職業人としての生活設計に助言をしているかと言うと、実は多くのキャリアコーチは認定資格など持っていないそうです。「誰でも看板を出し、『私はアドバイザーだ』と名乗ることができる」そうです。現在ではテキサス大学のほか、ジョージタウン大学(Georgetown University:ワシントンDC)とコロンビア大学(Columbia University:ニューヨーク)に教育課程があり、いずれもICFの認可を受けているそうですが、ほとんどが未認可のようです。最も安いキャリアコーチの場合でも料金は1時間当たり100ドル前後ということですので、やっている人は笑いが止まりませんね。それほど、アメリカでは需要があるということですので驚きです。
キャリアコーチの業務内容は「依頼人が輝かしく、堂々と見えるように磨きをかける。将来の展望を見出せるようにし、行き詰まっていた場所から脱出させてあげること。面接の心得を一から十まで指導し、典型的な口頭試問を検討しただけでなく、クライアントが自分をどう売り込むべきかについても話し合い、プレゼンテーションのシナリオを作り上げる」ことのようです。なぜ金を出してまで、その答えを他人に求めるのか? そう思う人もいると思いますが、「一見わけもなさそうに見えて、実は非常に難しいのが自分の行動を変えること。そこら辺にキャリアコーチの出番があるようです。依頼人が自分の世界を新たな視点で見られるように支援することだそうです。それは依頼人に、本当の自分は何者かを問いかけることなのだ」と言うことのようです。
日本は、いろいろな面でアメリカと比較すると10年遅れているといわれますが、後何年かすると、キャリアコーチと言う名刺を持った人が現れてくるのでしょうか?もしかしたら、もうすでに活動していて笑いが止まらないかもしれません。
2007年12月14日
191)サクラブロガーにならないために
「このようなサービスが生まれるのは自然の成り行きであり、自らの名誉にかけて信頼に足る情報発信を本懐とするブロガーや、個人発のブログ情報に信認を寄せるネットワーカーにとっては少々迷惑な話でもある。」ということです。
そこで久米氏は「心あるブロガー」が「サクラブロガー」に間違われないためにどうしたらよいか7ヶ条を考えてくれました。
1.とにかく実名とプロフィール
2.体感なくして賞賛なし
3.顔の見える商品を勧めよ
4.裏事情までオープンソース
5.商品名検索で石橋を叩いて渡れ
6.品物の先にある企業理念を見よ
7.目先の小遣いより百年後の評価
詳しくは以下を参照ください。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071113/287057/?set=bpn
当方も痛いところを付かれて項目もあり、少し反省しなければなりませんが、「情報の提供」と「自分の考え」をこのブログに掲載してきたつもりです。体験、体感していないが話題になりそうな商品を取り上げたりしましたが、ほとんど当方の主観であり、外部からの依頼、要請はありません(要請があるほどの実力者になればいいのですが、タイトルが『モノローグ(独り言)』ですし、インパクトがありませんよね)。この中で「7.目先の小遣いより百年後の評価」の説明コメントには久米氏の考えが大きく反映していると思いました。「少々大げさで現実的ではないが、ブログを書くときに『この記事を100年後の子孫が読んだらどう思うか』と考えることがある。すると自ずと背筋が伸びて、心が改まるからである。そして目先の小遣い稼ぎや10年後のビジネスのことよりも、今、人として何を書くべきかに心がフォーカスするのである。」と。このように言われると「モノローグだから」と言うことで逃げるわけには行かなくなります。もう少し続けたいと思っていますので、背筋を伸ばさなければと思った次第です。
最後に久米氏は以下に結んでいました。
「来るべき一億総ブログ時代において、個人ブログは大切な名刺や履歴書代わりになる。即ち、個人としての「信用の証」にもなるのだ。かくも重要な役割を担う個人ブログが、小遣い稼ぎのサクラだと思われては、何とも寂しい限りだと思うのだが、いかがだろうか?」
2007年12月13日
190) 東京プライス(東京の人が安く買うために)
価格に関しては、一軒目のお店ではポイント分も引いたと仮定すると171,000円となりました。「東京では、ポイントを考慮すると160,000円であり、送料を入れてもまだ安い。貴量販店は全国展開しているし、購入・販売数量も多い故、価格を近づけることが出来るはずだと思うが?」と問い合わせたところ、「東京は商圏が大きいし、販売数量も違うため価格が異なる」とのこと「静岡のお店がFCではないはずだから、仕入れ価格は同じはずでしょ?」との問いに「東京価格があり、こちらとは仕入れ価格が違う」とのことでした。
量販店と一般小売のお店では仕入れ価格が異なることは理解できますが、地域による価格差は理解できません。輸送費が極端に異なるのであれば納得できますが、今回は当てはまりません。首都圏は競争が激しく、又、量が出るため、安いということはおかしな話です。店舗の人件費、不動産の賃料、その他固定費は我々静岡よりかかるはずです。経費が高く、しかも売価が安いということは、メーカーからの仕入れ価格は15%以上安いということになります。もしかしたら20%違うかもしれません。ご存知のように静岡は東京と比べると、賃金家賃等の固定費は安いです。よって、固定費が下がりますので同じ商品であれば安くなってもおかしくありません。しかし、高いと言うことは地方でメーカー、販売店の利益を補填しているということになります。これっておかしくありませんか?
「格差」と言う言葉が昨年よりいろいろなところで使用されていますが、地方の所得格差、経済活動の格差がある中で、逆に高いものを購入しなければならないという格差も生じていることになります。以前、アメリカのすべての商品の価格は安く、ヨーロッパは高いということを書きましたが、この小さな日本の国の中でも同じことがされているとは思ってもみませんでした。昔から、静岡は物価が高いと言われてきましたが、百貨店で値引きを依頼しない県民性があるとも言われてきました。しかし、県民性ではなく、政策的に高くさせられていたことに気がついていなかったということになります。WEB通販が盛んになり、県民皆が東京価格で安く購入したら、静岡の消費は減っていきます。ここで、又、消費の低迷による格差が増えてしまいます。東京都民に商品を安く買ってもらうために、我々が働き、消費活動をしているわけではありません。そのような事実があることを知ってほしいと思います。
ちなみに、2軒目のお店で東京より15,000円高(送料と設置手数料を入れれば12,000円高ですが)の175,000円で購入しました。東京の人に安く買ってもらうために.....
2007年12月12日
189) 日テレホワイトロード
日本テレビは以前麹町にあったのではなかったかと記憶していますが、この汐留のタワービルに移転してきました。16:00前にこのホールを通ったときに人が集まっており、「写真禁止」と書かれたカードを持った人がいました。良く見るとDondokoDonのぐっさんがいました。何かの中継が始まるのでしょう。ズームイン朝は見ないため解かりませんが、もしかしたらあの場所は宣伝プラカードを持った人が集まる場所ではないかと思った次第です。東京にいるとふとした場所で撮影に出くわしますよね。
この日テレホワイトロード」は11月30日から12月25日まで開催されるようです。1面白色のLEDを使用した白のイルミネーションでした。多くの人が写真を撮っていましたので、当方も思わず携帯電話で写真を撮ってしまいました。イルミネーションは以前でしたら豆電球を使用していましたが、白色LEDの発明により、今までなかった色が表現できるようになりました。又、省エネ効果、電球切れの心配もなくなりました。先日、テレビの情報番組で外国人が購入する人気アイテムのNo.1はLEDを使用したイルミネーションとのことでした。諸外国(自国)で購入するよりも価格が半額で、しかもLEDを使用したアイテムの多さに多くの外国人がこの時期お土産に購入するようです。もし、この時期外国に行くとき何かお土産に迷ったらLEDのイルミネーションを購入するのが良いかも知れませんね。きっと良いでしょう!東京では、丸の内のイルミネーションが有名ですよね。今年は、六本木の東京ミッドタウンでもイルミネーションのイベントが開催されるようです。イルミネーションめぐりも良いかも知れません。
昨日は、その後友人と有楽町で待ち合わせしました。時間が少しあった為、ビックカメラで液晶テレビを見たのですが、シャープの37インチ120コマ、フルハイビジョンHD、206万画素が194,800円でした。さらに18%のポイント還元。計算すると16万円ほどでしたので安いと思い静岡までの送料を聞くと2,000円でした。きっと、静岡で購入するより安いかもしれないと思いましたが、まずは静岡価格を調べることにした後で決定することにしました。静岡経済に少しでも貢献したほうが良いと思ったからです。でも、2~3万円違ったら東京で購入するかも知れません。友人を待っている間に日本経済新聞社の質問を受け、来年の景気に関しては少しは悪くなるだろうと回答しました。消費動向が悪くなると思ったからです。
すでにボーナスが出た人もいると思いますが、貴方は何を購入しますか?
日テレホワイトロード http://www.ntv.co.jp/shiodome/event/2007xmas/index.html
東京ミッドタウン http://www.tokyo-midtown.com/jp/xmas/index.html
丸の内イルミネーション http://www.marunouchi.com/special/07_08illumination/

2007年12月11日
188)ホットワイン(メルシャン&エスビー)
知らなかったのですが、ホットワインはフランスでは「ヴァン・ショー」、ドイツでは「グリューワイン」と呼ばれ、ヨーロッパの家庭では冬の代表的なホットカクテルだそうです。本来はフルーツのスライスや、スパイスをグラスにいれ、温めたワインを注ぐそうですが、ヱスビーが開発したものは「スパイスバック」となる、ティーパックのようなものをワインに入れて電子レンジで温めるようです。メルシャンワインでは白ワイン用に色を損なわないエルダーフラワーとローズヒップ、温めると酸味が増す赤ワイン用にはシナモン、オレンジピール、クローブを配合した「スパイスバック」を付けるサービスを来年1月7日から開始するようです。
当方の感覚では、温めて飲むお酒としては、日本酒、焼酎、紹興酒ぐらいかと思っていましたが、まさかワインを温めるという発想はありませんでした。ヨーロッパの家庭で代表的であるものがなぜ、今までこの日本に紹介されてこなかったのかが不思議でなりません。赤ワインを暖かくしたものを想像しただけで、なんとなく口当たり、かおり、味がわかりませんか?多分違和感がないと思います。それにプラスしてハーブ、スパイスを入れるのですから、変わった感覚でよいかも知れません。ただ、料理にどのように合わすかは難しいでしょうね。
以前、コラボレーションのことを書きましたが、これからの消費多様化の時代は企業単独で新製品、新しい販売方法を作ることは難しいはずです。どの企業も、コンサルタントも、日経トレンディでもコラボレーション、アライアンスをなくして新製品を語れないと言っています。又、我々の全く知らない、食べ物、食べ方・飲み方が世界中にはあるかも知れません。もしかしたら、我が家独自の料理、食べ方もメジャーになるかも知れません。そのような意味で、情報を集め、議論するのも面白いですね。
先週訪問した焼津の会社の新製品開発のヒントが出せるのではないかとも思っています。