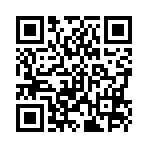2007年12月21日
197) 社員が辞めるのは上司の責任 -声かけ-
日経BP Netに連載している株式会社武蔵野の小山社長のコラムで、又、参考になったものがありましたので引用します。
それは、「社員が辞めるのは上司の責任である」との意見です。小山氏曰く「社員は待遇や仕事内容に不満があっても、それだけでは辞めない。むしろ、人間関係がしんどいとか社内の風通しが悪いとかコミュニケーション不全に由来する退職のほうがずっと多い」ということです。心当たりありませんか?
コミュニケーション不全は多くの場合、上司に責任があります。一般社員のコミュニケーションスキルが低いのはある意味で当然であり、それを上手くフォローすることが大切です。いや「大切」というよりは、「上に立つ者としての当然の義務」です。 「周囲に溶け込んでいないな」と見れば溶け込む工夫をし、「人間関係に悩んでいる」と判断すれば相談に乗る。こういうキメ細かな配慮をし、部下がやりがいや充実感をもって仕事ができる環境をつくることが上司の仕事です。よく「部下に辞められると自分のマネジメント能力が問われる」と渋い顔をする管理職がいます。そういう人は、果たして自分が上司としての務めをしっかり果たしていたかどうかをまずは自問するべきです。上司としての仕事をおざなりにして自己保身に走るとは笑止千万もいいところです。と言っています。
そこで、小山氏は毎日、部下全員に声をかけることを日課としたそうです。しかし、上手くいかなかったようです。というのは当時の部下にしてみれば「上司から声をかけられる」は、「面倒な仕事を押し付けられる」「説教される」と思ったからです。しかし、あきらめずに毎日声かけをしたところ、社内のコミュニケーションは非常に良くなり、辞める社員は飛躍的に減ったようです。「小山は説教をするわけではない」「大部分は馬鹿話だ」ということが分かり、話しかけられることを嫌がる社員がいなくなったと言うことです。
コーチングでは、うなずき、承認、聞き上手になることを教わりますが、超えかけも重要な要素になっています。小山氏のやられていることは、そのままそっくりコーチングに当てはまっています。だから、小山氏はよきコーチであり、よき社長であることがわかります。小山氏の講演、セミナーはいつも「満員御礼」のようですが、わかる気がします。当方にも、挨拶が出来ない(しない)スタッフがいますが、当方もあきらめずに日課として続けていこうと思います。声かけについても、コーチングのセミナーで習った時は試みるのですが、何時しか適当になってしまっています。反省し、心して取り組みたいと思います。
小山氏は最後に以下のように結んでいました。「勉強するのは、もちろん良いことです。しかし人は、勉強しただけでは変わりません。勉強したことを実行して初めて変わるのです。人が変わらなければ、組織は絶対に良くなりません。ここを誤解してはいけません。」と。
人を変える前に、まず自分から変え、組織を良くしたいものですね。
それは、「社員が辞めるのは上司の責任である」との意見です。小山氏曰く「社員は待遇や仕事内容に不満があっても、それだけでは辞めない。むしろ、人間関係がしんどいとか社内の風通しが悪いとかコミュニケーション不全に由来する退職のほうがずっと多い」ということです。心当たりありませんか?
コミュニケーション不全は多くの場合、上司に責任があります。一般社員のコミュニケーションスキルが低いのはある意味で当然であり、それを上手くフォローすることが大切です。いや「大切」というよりは、「上に立つ者としての当然の義務」です。 「周囲に溶け込んでいないな」と見れば溶け込む工夫をし、「人間関係に悩んでいる」と判断すれば相談に乗る。こういうキメ細かな配慮をし、部下がやりがいや充実感をもって仕事ができる環境をつくることが上司の仕事です。よく「部下に辞められると自分のマネジメント能力が問われる」と渋い顔をする管理職がいます。そういう人は、果たして自分が上司としての務めをしっかり果たしていたかどうかをまずは自問するべきです。上司としての仕事をおざなりにして自己保身に走るとは笑止千万もいいところです。と言っています。
そこで、小山氏は毎日、部下全員に声をかけることを日課としたそうです。しかし、上手くいかなかったようです。というのは当時の部下にしてみれば「上司から声をかけられる」は、「面倒な仕事を押し付けられる」「説教される」と思ったからです。しかし、あきらめずに毎日声かけをしたところ、社内のコミュニケーションは非常に良くなり、辞める社員は飛躍的に減ったようです。「小山は説教をするわけではない」「大部分は馬鹿話だ」ということが分かり、話しかけられることを嫌がる社員がいなくなったと言うことです。
コーチングでは、うなずき、承認、聞き上手になることを教わりますが、超えかけも重要な要素になっています。小山氏のやられていることは、そのままそっくりコーチングに当てはまっています。だから、小山氏はよきコーチであり、よき社長であることがわかります。小山氏の講演、セミナーはいつも「満員御礼」のようですが、わかる気がします。当方にも、挨拶が出来ない(しない)スタッフがいますが、当方もあきらめずに日課として続けていこうと思います。声かけについても、コーチングのセミナーで習った時は試みるのですが、何時しか適当になってしまっています。反省し、心して取り組みたいと思います。
小山氏は最後に以下のように結んでいました。「勉強するのは、もちろん良いことです。しかし人は、勉強しただけでは変わりません。勉強したことを実行して初めて変わるのです。人が変わらなければ、組織は絶対に良くなりません。ここを誤解してはいけません。」と。
人を変える前に、まず自分から変え、組織を良くしたいものですね。
Posted by walt at 22:14│Comments(0)