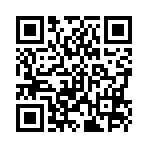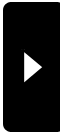2007年10月31日
147)お寺の役割 Vol.2(地域コミュニティ)
6年前に父親が亡くなるまで、お寺には1年に1回行くかどうかでした。行かない年もあったと思います。子供の頃は良く両親に連れられて墓参りに行った記憶があります。父親がなくなってからは、母親が墓参りに行く都度、母親の足としてお墓に盆と彼岸、そして年末に行くようになりました。そして、地区役員となり3年目となりましたが、総会や、お寺のイベントに参加するようになり、又、院報の編集委員のため、年3回行くようになりました。ただ、当家のお墓に行くのは年4日ほどしかありませんが....地区役員は支部が20ほどあり、その為20名ほどの役員がいます。当方は年齢的に言うと若い方から5本の指に入るのではないでしょうか?ほとんどの方が60歳以上であり、70歳を超えた方々も多くいます。
当院は昨年開山450年の法要が営まれました。檀家も750ほどあると聞いています。昔は墓守のボランティアがいたようですが今では、そのような方がいらっしゃらず、お墓に活けた花がそのままで、次に行ったときに悪臭を放つほどになっているといった状況です。本来であれば、こまめに墓参りに行かない当方が悪いのですが.....お盆の時は、和尚さんが必ず来てくれましたが、数年前からは、日にちを決めてお寺に行き、供養してもらうようになりました。初盆のときのみ自宅に来てくれます。
檀家さんも年配者ばかりとなり、又、息子、娘夫婦が同居しておらず、その為お盆のときの法要も足がないからお寺に行けないといった檀家さんも増えています。又、檀家さんが市内には住んでおらず市外、県外に住んでいる方々も増えています。全体的な傾向のようですが。いわゆる檀家と言う仕組み・シズテムが崩れつつあると聞きました。それは、個人で墓を持つようになったこと。戒名をもらわなくなったこと。先祖代々の墓を守るといった風習がなくなりつつあること等があるようです。その為、お寺はお布施で運営されてきたものが、根底から崩れかけはじめているということでした。
当方の自宅近所にはなぜかお寺の数が多く、母親は近所のお寺に写経に通うようになりました。これはとても良いことと思っています。檀家ではないのにお寺が受け入れてくれているわけです。これもひとつのお寺の役割ではないでしょうか?妻の実家のお寺では、毎年お茶会がお寺で開催されているようです。お茶農家の多い地区であり、檀家さんがお茶農家の方々が多いため、昔からお茶会を開催しているのかも知れません。妻は興味がない為、過去一度も参加したことがないと言っていましたが
今年は11月に開催されるようですので、参加してどのように行われるのか偵察を依頼しました。
築地本願寺でのレストランの開店、仏教関連の講和、光明寺での「お寺カフェ」の開店。そして、多くの人の利用を考えると世の中に疲弊した人々が、心のよりどころを探しているのかも知れません。今後檀家と言う考えが薄くなりお寺運営の方法を再考しなければならない時代が来ると思われます。そのような意味で、当方のお寺は閑静な場所にあり、信徒会館、座禅堂もあります。しかし、毎日利用されているわけではありません。施設の有効利用も考え、又、我々人間に提供できる禅の精神、教えを体験できる場の提供が檀家のみならず、近隣住民にも出来るのではないでしょうか?地域コミュニケーションを考える素材がたくさんあるお寺ではないかと思っております。そんな仕掛け・仕組みを考え、和尚さんに相談してみたいと思ってます。
皆さんもお寺の役割に関して一度考えてみませんか?
当院は昨年開山450年の法要が営まれました。檀家も750ほどあると聞いています。昔は墓守のボランティアがいたようですが今では、そのような方がいらっしゃらず、お墓に活けた花がそのままで、次に行ったときに悪臭を放つほどになっているといった状況です。本来であれば、こまめに墓参りに行かない当方が悪いのですが.....お盆の時は、和尚さんが必ず来てくれましたが、数年前からは、日にちを決めてお寺に行き、供養してもらうようになりました。初盆のときのみ自宅に来てくれます。
檀家さんも年配者ばかりとなり、又、息子、娘夫婦が同居しておらず、その為お盆のときの法要も足がないからお寺に行けないといった檀家さんも増えています。又、檀家さんが市内には住んでおらず市外、県外に住んでいる方々も増えています。全体的な傾向のようですが。いわゆる檀家と言う仕組み・シズテムが崩れつつあると聞きました。それは、個人で墓を持つようになったこと。戒名をもらわなくなったこと。先祖代々の墓を守るといった風習がなくなりつつあること等があるようです。その為、お寺はお布施で運営されてきたものが、根底から崩れかけはじめているということでした。
当方の自宅近所にはなぜかお寺の数が多く、母親は近所のお寺に写経に通うようになりました。これはとても良いことと思っています。檀家ではないのにお寺が受け入れてくれているわけです。これもひとつのお寺の役割ではないでしょうか?妻の実家のお寺では、毎年お茶会がお寺で開催されているようです。お茶農家の多い地区であり、檀家さんがお茶農家の方々が多いため、昔からお茶会を開催しているのかも知れません。妻は興味がない為、過去一度も参加したことがないと言っていましたが
今年は11月に開催されるようですので、参加してどのように行われるのか偵察を依頼しました。
築地本願寺でのレストランの開店、仏教関連の講和、光明寺での「お寺カフェ」の開店。そして、多くの人の利用を考えると世の中に疲弊した人々が、心のよりどころを探しているのかも知れません。今後檀家と言う考えが薄くなりお寺運営の方法を再考しなければならない時代が来ると思われます。そのような意味で、当方のお寺は閑静な場所にあり、信徒会館、座禅堂もあります。しかし、毎日利用されているわけではありません。施設の有効利用も考え、又、我々人間に提供できる禅の精神、教えを体験できる場の提供が檀家のみならず、近隣住民にも出来るのではないでしょうか?地域コミュニケーションを考える素材がたくさんあるお寺ではないかと思っております。そんな仕掛け・仕組みを考え、和尚さんに相談してみたいと思ってます。
皆さんもお寺の役割に関して一度考えてみませんか?
Posted by walt at
22:20
│Comments(0)
2007年10月30日
146) お寺の役割 Vol.1(カフェ・ド・シンラン)
日本国内にコンビニが何店舗ほどあるかご存知ですか? 25,000店ほどあるといわれておりますが、国内にあるお寺はどのくらいあるでしょうか?なんとコンビニの数より多いお寺があるということです。するとコンビニ店長の数より多い、僧侶がいるという計算になります。従来よりお寺はその檀家さんたちで成り立っています。檀家さんとは辞書では「ある寺の信徒となり、布施などの経済的援助を持続して行い、葬式・法事などを行なってもらう家」と書かれております。檀家のお布施によって、お寺の運営がされていると言うことです。
先日、ニュースで東京の築地本願寺境内に「カフェ・ド・シンラン」というイタリアンレストランが期間限定で9/21にオープンして賑わっていることを知りました。又、日経BPオンラインでも記事が掲載されました。この「カフェ・ド・シンラン」は「仏の教えはロハス(環境や健康を優先した生活)」をテーマに自然食材を使用し、フードマイレージ(生産地と消費地が近いと、輸送に関係するエネルギー(CO2など)を削減できるという考え方)の観点から、国産にこだわった食材で、国内産16種雑穀米や農家から直送される無農薬・減農薬野菜を中心に、「旬の食材を使ったヘルシーなメニューを揃えている」レストランのようです。又、ランチは「本格インドカレー」のみで(なぜこれがイタリアンレストランであるか不思議)、1日限定60食、ディナーは肉や魚料理をメインにパスタも充実させ1日平均40~60人が来店しているそうです。店舗面積30坪、席数28で12月間で営業し、その後撤去されるようです。1日の売り上げ目標を25万円に設定しているとのこと。
お寺は宗教法人であり、その為、レストラン事業をするための敷居は高かったに違いありません。勿論すべての檀家さんたちに納得してもらったと思います。お寺側は「ここにレストランができるのは当然の流れ」築地本願寺の山内教嶺(きょうれい)副輪番は、話されたとのこと。今後、本願寺やその関連団体がモーニング・ヨガや精進料理クッキング、モーニング/イブニング法話会、仏像ガイダンス講座などのイベント開催も予定するようです。本願寺宗務首都センター国内伝道推進部担当者は同店について、「環境保全へ向けた新たなライフスタイルを提唱することやレストランの趣旨に賛同するとともに、レストランによって親鸞聖人の許に生まれるにぎわいが新たな仏縁となることを願い運営協力した」と話しています。
東京タワーが間近に見える港区虎ノ門のオフィス街「神谷町オープンテラス」とチョークで書かれた小さな黒板があるお寺光明寺があるそうです。その黒板には「無線LAN完備」「飲食持ち込み自由」の文字もあり本堂の外階段を上るとコンクリートのテラスが広がり、テーブルやベンチでくつろぐ人たちがいます。ここは「お寺カフェ」とも呼ばれ連日多くの人で賑わっています。利用代金はお賽銭箱に志を入れる仕組みのようです。また、光明寺の本堂で音楽の生演奏を楽しみ、自らの法話と参加者全員でお経を上げる音楽会も不定期で開くようになっているようです。
昔からお寺が地域のコミュニティの役割をはたしていました。相談所でもあり、学ぶ場所でもあり、救済所の役割も担ってきたと思います。それが、現代社会となりお寺が単にお葬式、法事のときのみしか利用しなくなってしまいました。檀家と言ういわゆる顧客からのお布施のみで運営される組織体となってしまいました。この築地本願寺、光明寺は形こそ違いますが、人の集まる場所を提供をすることにより、地域コミュニティの一環としての役割を果たしているのではないでしょうか?当方、お寺の地区役員をやっており、行事ごとにお寺に行っていますが、当方のお寺は檀家数も多く、立派な信徒会館に座禅所もあります。座禅会は催されておりますが、地域コミュニティの役割はまだまだです。今後時を見て和尚さんに、今後のお寺の役割りに関して話をしたいと思っております。次回地域コミュニティに関して述べたいと思います。
先日、ニュースで東京の築地本願寺境内に「カフェ・ド・シンラン」というイタリアンレストランが期間限定で9/21にオープンして賑わっていることを知りました。又、日経BPオンラインでも記事が掲載されました。この「カフェ・ド・シンラン」は「仏の教えはロハス(環境や健康を優先した生活)」をテーマに自然食材を使用し、フードマイレージ(生産地と消費地が近いと、輸送に関係するエネルギー(CO2など)を削減できるという考え方)の観点から、国産にこだわった食材で、国内産16種雑穀米や農家から直送される無農薬・減農薬野菜を中心に、「旬の食材を使ったヘルシーなメニューを揃えている」レストランのようです。又、ランチは「本格インドカレー」のみで(なぜこれがイタリアンレストランであるか不思議)、1日限定60食、ディナーは肉や魚料理をメインにパスタも充実させ1日平均40~60人が来店しているそうです。店舗面積30坪、席数28で12月間で営業し、その後撤去されるようです。1日の売り上げ目標を25万円に設定しているとのこと。
お寺は宗教法人であり、その為、レストラン事業をするための敷居は高かったに違いありません。勿論すべての檀家さんたちに納得してもらったと思います。お寺側は「ここにレストランができるのは当然の流れ」築地本願寺の山内教嶺(きょうれい)副輪番は、話されたとのこと。今後、本願寺やその関連団体がモーニング・ヨガや精進料理クッキング、モーニング/イブニング法話会、仏像ガイダンス講座などのイベント開催も予定するようです。本願寺宗務首都センター国内伝道推進部担当者は同店について、「環境保全へ向けた新たなライフスタイルを提唱することやレストランの趣旨に賛同するとともに、レストランによって親鸞聖人の許に生まれるにぎわいが新たな仏縁となることを願い運営協力した」と話しています。
東京タワーが間近に見える港区虎ノ門のオフィス街「神谷町オープンテラス」とチョークで書かれた小さな黒板があるお寺光明寺があるそうです。その黒板には「無線LAN完備」「飲食持ち込み自由」の文字もあり本堂の外階段を上るとコンクリートのテラスが広がり、テーブルやベンチでくつろぐ人たちがいます。ここは「お寺カフェ」とも呼ばれ連日多くの人で賑わっています。利用代金はお賽銭箱に志を入れる仕組みのようです。また、光明寺の本堂で音楽の生演奏を楽しみ、自らの法話と参加者全員でお経を上げる音楽会も不定期で開くようになっているようです。
昔からお寺が地域のコミュニティの役割をはたしていました。相談所でもあり、学ぶ場所でもあり、救済所の役割も担ってきたと思います。それが、現代社会となりお寺が単にお葬式、法事のときのみしか利用しなくなってしまいました。檀家と言ういわゆる顧客からのお布施のみで運営される組織体となってしまいました。この築地本願寺、光明寺は形こそ違いますが、人の集まる場所を提供をすることにより、地域コミュニティの一環としての役割を果たしているのではないでしょうか?当方、お寺の地区役員をやっており、行事ごとにお寺に行っていますが、当方のお寺は檀家数も多く、立派な信徒会館に座禅所もあります。座禅会は催されておりますが、地域コミュニティの役割はまだまだです。今後時を見て和尚さんに、今後のお寺の役割りに関して話をしたいと思っております。次回地域コミュニティに関して述べたいと思います。
Posted by walt at
22:04
│Comments(0)
2007年10月29日
145) ホスピタリティ (カシータ)
東京青山にある「カシータ」というお店ご存知ですか?高橋 滋氏が経営するレストランですが、130席のレストランは予約でいつも埋まって言うという超人気店です。何が人気化と言うと、料理はおいしいのは当たり前ですが、接客・サービスの良さではまねのできないオペレーションをしているということです。ランチはやっていませんので、ディナーだけ(オープン当時は六本木にありランチもやっていたと記憶しています)で、客単価は最低10,000円にはなる高級店ですが明らかに他店とは違うことは誰しも経験するようです。
先週、ビックサイトで開催された展示会のセミナーで高橋氏の講演があり聞く機会を得ました。このお店、この高橋氏を知ったのは3年前で、知人から「I am a man」という高橋氏の著書を借りたことから始まります。当時我々の仲間がレストランをオープンすることなり、その接客、サービス、お店作りの勉強会で「カシータ」を知りました。高橋氏のお店作りの原点がアマンリゾート」というホテルチェーンに宿泊したことがきっかけとなっています。東南アジアでは、タイ、インドネシア、フィリッピンにリゾートホテルがあったと思います。このアマンリゾートですが当方は10年程前より泊まってみたいホテルのナンバーワンでした。当時で1泊450ドルほどしました。ロケーションのすばらしさ、施設、設備の良さ、ゆったりくつろげる空間に憧れつつ、10年の歳月が経過し、再び高橋氏を通じてアマンリゾートのことを思い出しました。高橋氏曰く、現在では1泊700ドルするそうです。
このアマンリゾートに滞在して、高橋氏は、サービスの良さ、お客様に満足を与えることがホテルのモットーであることに感動し、レストランの経営に踏み切ったようです。高橋氏は「カシータ」はレストラン(飲食業)ではなくサービス業であると言っています。この「カシータ」では、お客様が満足をしてくれるためにありとあらゆることをしてくれるようです。お店はビルの3階にあるようですが、1階のビルの前にはコンシェルジェがいるようで、お店を探しているような人がいれば、声掛けをして、お店に案内するようです。お店の入り口ではお迎えのスタッフがいて、お客様の名前を言いにこやかに挨拶して、席にお連れするようです。テーブルには「Reserved」のたてがあるのではなく、さりげなくウェルカムメッセージが添えられているようです。お帰りの際は、感謝の意を表して深々とお辞儀をして、階下のビルの入り口まで見送るそうです。そのようなサービスには照れてしまいそうですが、又、次のご来店をお待ちしているというメッセージがこめられていると思われます。
高橋氏は日本のホテルではリッツカールトン大阪、飛行では全日空のサービス、顧客満足度が高いことを強調しておりました。両社とも、如何にお客様が満足してくれることを念頭にすべての行動をしているようです。リッツカールトンホテル、全日空を利用することで、多くのことを学び、それをお店にすぐ展開しているとのこと。全日空のビジネスクラスでは席をはずした時、掛けてあった毛布が席に戻ったとききちんとたたまれていること。それをヒントに、お店でお客様が席を立ったときナフキンをきちんとたたんで席に置くこと指示したこと。他の高級レストランで経験した予約したお店に15分ぐらい早く着い
ても「準備中」であるということを理由にお店に入れてもらうことが出来なかったことから、その場でカシータに電話しカシータは18:00の開店ですが、それより前に来てしまったお客様がいれば、必ずお店に入っていただくよう指示したこと等話されました。
多くのことを書くことが出来ませんが、高橋氏は「すべてのサービスがお客様の都合ではなく、サービスをする方の都合で行われていること。それに、我々は慣れてしまっており、本当のサービスを提供されていないことに気がつくべきだ」と言っておられました。「ホスピタリティ」、日本語では「親切にもてなすこと」ということになります。この高橋氏の講演を聞き改めて、おもてなしの意味合いを知りました。サービス業ではなくても、すべてのビジネスシーンで同じことが言えます。仕事はお客様が満足してもらうために行っているわけであり、我々の給料は、その代価としてお客様から頂いているわけです。
仕事のあり方も変えようと思った次第です。「想いは伝わる」と最後に高橋氏から言っていただきました。いつか必ず「カシータ」に行き、また、アマンリゾートに泊まってみたいと思います。余談ですが、アマンリゾートでは敷地内の丘の上で夕日を見ながらディナーを楽しみたいと言えば、その場所にテーブルのセッティングをしてくれるそうです。お客様が満足してくれるために.....
カシータ:http://www.casita.jp/
先週、ビックサイトで開催された展示会のセミナーで高橋氏の講演があり聞く機会を得ました。このお店、この高橋氏を知ったのは3年前で、知人から「I am a man」という高橋氏の著書を借りたことから始まります。当時我々の仲間がレストランをオープンすることなり、その接客、サービス、お店作りの勉強会で「カシータ」を知りました。高橋氏のお店作りの原点がアマンリゾート」というホテルチェーンに宿泊したことがきっかけとなっています。東南アジアでは、タイ、インドネシア、フィリッピンにリゾートホテルがあったと思います。このアマンリゾートですが当方は10年程前より泊まってみたいホテルのナンバーワンでした。当時で1泊450ドルほどしました。ロケーションのすばらしさ、施設、設備の良さ、ゆったりくつろげる空間に憧れつつ、10年の歳月が経過し、再び高橋氏を通じてアマンリゾートのことを思い出しました。高橋氏曰く、現在では1泊700ドルするそうです。
このアマンリゾートに滞在して、高橋氏は、サービスの良さ、お客様に満足を与えることがホテルのモットーであることに感動し、レストランの経営に踏み切ったようです。高橋氏は「カシータ」はレストラン(飲食業)ではなくサービス業であると言っています。この「カシータ」では、お客様が満足をしてくれるためにありとあらゆることをしてくれるようです。お店はビルの3階にあるようですが、1階のビルの前にはコンシェルジェがいるようで、お店を探しているような人がいれば、声掛けをして、お店に案内するようです。お店の入り口ではお迎えのスタッフがいて、お客様の名前を言いにこやかに挨拶して、席にお連れするようです。テーブルには「Reserved」のたてがあるのではなく、さりげなくウェルカムメッセージが添えられているようです。お帰りの際は、感謝の意を表して深々とお辞儀をして、階下のビルの入り口まで見送るそうです。そのようなサービスには照れてしまいそうですが、又、次のご来店をお待ちしているというメッセージがこめられていると思われます。
高橋氏は日本のホテルではリッツカールトン大阪、飛行では全日空のサービス、顧客満足度が高いことを強調しておりました。両社とも、如何にお客様が満足してくれることを念頭にすべての行動をしているようです。リッツカールトンホテル、全日空を利用することで、多くのことを学び、それをお店にすぐ展開しているとのこと。全日空のビジネスクラスでは席をはずした時、掛けてあった毛布が席に戻ったとききちんとたたまれていること。それをヒントに、お店でお客様が席を立ったときナフキンをきちんとたたんで席に置くこと指示したこと。他の高級レストランで経験した予約したお店に15分ぐらい早く着い
ても「準備中」であるということを理由にお店に入れてもらうことが出来なかったことから、その場でカシータに電話しカシータは18:00の開店ですが、それより前に来てしまったお客様がいれば、必ずお店に入っていただくよう指示したこと等話されました。
多くのことを書くことが出来ませんが、高橋氏は「すべてのサービスがお客様の都合ではなく、サービスをする方の都合で行われていること。それに、我々は慣れてしまっており、本当のサービスを提供されていないことに気がつくべきだ」と言っておられました。「ホスピタリティ」、日本語では「親切にもてなすこと」ということになります。この高橋氏の講演を聞き改めて、おもてなしの意味合いを知りました。サービス業ではなくても、すべてのビジネスシーンで同じことが言えます。仕事はお客様が満足してもらうために行っているわけであり、我々の給料は、その代価としてお客様から頂いているわけです。
仕事のあり方も変えようと思った次第です。「想いは伝わる」と最後に高橋氏から言っていただきました。いつか必ず「カシータ」に行き、また、アマンリゾートに泊まってみたいと思います。余談ですが、アマンリゾートでは敷地内の丘の上で夕日を見ながらディナーを楽しみたいと言えば、その場所にテーブルのセッティングをしてくれるそうです。お客様が満足してくれるために.....
カシータ:http://www.casita.jp/
Posted by walt at
21:57
│Comments(0)
2007年10月28日
144) FAZのお祭り
国道1号線を東に向かって走り52号線の手前の高架から埠頭側(右側)に「FAZ」という建物があります。倉庫であることは間違いありません。そのFAZの祭りが本日あり、初めて参加しました。当方が今年から会員となった「清水茶手揉み保存会」が出展してその手伝いに行ったわけです。この祭りも8回目だそうです。倉庫で開催されるお祭りなので、輸入関連の展示即売会と思っていましたが、どちらかというと一般的な物産展でした。手揉みのお茶の出展を考えると内容がわかる気がします。
何年か前から一般人は埠頭に入れなくなりました。昔は日の出埠頭、袖師埠頭、興津埠頭は釣りをする人で一杯でしたが、今では立ち入り禁止となっており、清水つり公園のみでしか釣りをすることができません。確か安全の問題だったと記憶しています。その興津埠頭での催しであり、フリーマーケットも同時開催されていたため多くのお客さんが来場されました。
ふと、FAZとは何かと思い、調べたところForeign Access Zoneの略であり、「平成4年に施行された「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(FAZ法)」に基づき、輸入の円滑化を図るため港湾・空港及びその周辺地域において輸入関連事業者の事業活動を促進させる輸入促進地域を設定して、輸入に関連するインフラ整備等を行い輸入関連業者を集積させ、効果的に輸入の促進を図ろうとするもの。現在、全国で22のFAZ地域が指定されている。」とのことであった。平成8年にFAZ事業の事業主体として、静岡県、旧清水市、地元経済界が中心となり第3セクター「清水港振興株式会社」が誕生、日の出マリンビルもこの「清水港振興株式会社」の管轄のようです。日の出マリンビルでは、輸入促進の催しが良く開催されているのでFAZ事業の一環といえるでしょう。
このようないわゆる物産展が色々な場所で開催されますが、何処も来場者で一杯です。特に安いというわけでもなく、珍しいものが買えるというわけでもありませんが、多くの人で賑わいます。特に飲食コーナーが人気のようです。いわゆる屋台ということになります。以前、清水七夕祭りの時、屋台で一番儲かることを書きましたが、我々は屋台好きということになるのではないでしょうか?すると、定期的な屋台通り、屋台村を商店街で催すことが活性化になるのではないでしょうか?そんなことを考えてみました。
何年か前から一般人は埠頭に入れなくなりました。昔は日の出埠頭、袖師埠頭、興津埠頭は釣りをする人で一杯でしたが、今では立ち入り禁止となっており、清水つり公園のみでしか釣りをすることができません。確か安全の問題だったと記憶しています。その興津埠頭での催しであり、フリーマーケットも同時開催されていたため多くのお客さんが来場されました。
ふと、FAZとは何かと思い、調べたところForeign Access Zoneの略であり、「平成4年に施行された「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(FAZ法)」に基づき、輸入の円滑化を図るため港湾・空港及びその周辺地域において輸入関連事業者の事業活動を促進させる輸入促進地域を設定して、輸入に関連するインフラ整備等を行い輸入関連業者を集積させ、効果的に輸入の促進を図ろうとするもの。現在、全国で22のFAZ地域が指定されている。」とのことであった。平成8年にFAZ事業の事業主体として、静岡県、旧清水市、地元経済界が中心となり第3セクター「清水港振興株式会社」が誕生、日の出マリンビルもこの「清水港振興株式会社」の管轄のようです。日の出マリンビルでは、輸入促進の催しが良く開催されているのでFAZ事業の一環といえるでしょう。
このようないわゆる物産展が色々な場所で開催されますが、何処も来場者で一杯です。特に安いというわけでもなく、珍しいものが買えるというわけでもありませんが、多くの人で賑わいます。特に飲食コーナーが人気のようです。いわゆる屋台ということになります。以前、清水七夕祭りの時、屋台で一番儲かることを書きましたが、我々は屋台好きということになるのではないでしょうか?すると、定期的な屋台通り、屋台村を商店街で催すことが活性化になるのではないでしょうか?そんなことを考えてみました。
Posted by walt at
23:34
│Comments(0)
2007年10月27日
143) 1年ぶりの胃カメラ
あっという間に台風が過ぎ去った一日でした。エスパルスとガンバのサッカーの試合はできないと思いましたが試合開始時刻には雨が小降りとなり、風も無くなり、雨が上がって試合ができました。結果は3-1で4年ぶりの勝利でした。
毎年恒例の胃カメラを飲む季節がやってきました。毎年11月なのですが、10月中旬に予約を入れたところ、たまたま本日が空いていたため、急遽10月となりました。以前このブログでカメラのことを書きましたが、鼻から挿入するカメラをやりました。今回で3回目です。近所の床屋さんのマスターが検診で飲んだカメラでポリープ(胃がん)が見つかり、早期発見で無事だったという事例がありました。
胃カメラの飲むには順序があります。まず、前日の21:00以降は食事を摂ってはいけません。勿論当日の朝もです。胃の動きを抑えるための注射を打ちます。肩にうつのですがなんとまあ痛いこと。その後、鼻から麻酔の入った液体を入れます。鼻と喉に麻酔をかけるわけです。そして横になり鼻からカメラを挿入していきます。麻薬が効いているといっても、勿論違和感はありますし鼻、喉を通過するときは吐き気がして、苦しいです。胃の中に入れば余裕でモニターを見ることができます。カメラの他にバキュームと細胞を取るハンドも付いています。
今回の結果は昨年と同じようにビランというものがありましたが、特に問題がないとのことでした。カメラを入れている時間はおよそ2分ほどで終わり、カメラを抜いた後写真を観ながら説明してくれました。鼻血を出すことも無く1時間で終わり帰りました。朝食を抜いてきたので、血液検査もついでに頼みました。毎年、会社の健康診断が3月にあり、結果を基に先生に相談し、再度採血をして確認をとっていましたが、今年はやり忘れたため採血した次第です。
やはり胃カメラは好きになれませんが、これからも毎年続ける予定です。大腸検査の内視鏡もそろそろやらなければならないかなと思っておりますが、アレはちょっとといった感じです。言っておきますが、当方は内視鏡フェチではありませんから.....
40歳を過ぎたら、検査は毎年やりましょうね。

毎年恒例の胃カメラを飲む季節がやってきました。毎年11月なのですが、10月中旬に予約を入れたところ、たまたま本日が空いていたため、急遽10月となりました。以前このブログでカメラのことを書きましたが、鼻から挿入するカメラをやりました。今回で3回目です。近所の床屋さんのマスターが検診で飲んだカメラでポリープ(胃がん)が見つかり、早期発見で無事だったという事例がありました。
胃カメラの飲むには順序があります。まず、前日の21:00以降は食事を摂ってはいけません。勿論当日の朝もです。胃の動きを抑えるための注射を打ちます。肩にうつのですがなんとまあ痛いこと。その後、鼻から麻酔の入った液体を入れます。鼻と喉に麻酔をかけるわけです。そして横になり鼻からカメラを挿入していきます。麻薬が効いているといっても、勿論違和感はありますし鼻、喉を通過するときは吐き気がして、苦しいです。胃の中に入れば余裕でモニターを見ることができます。カメラの他にバキュームと細胞を取るハンドも付いています。
今回の結果は昨年と同じようにビランというものがありましたが、特に問題がないとのことでした。カメラを入れている時間はおよそ2分ほどで終わり、カメラを抜いた後写真を観ながら説明してくれました。鼻血を出すことも無く1時間で終わり帰りました。朝食を抜いてきたので、血液検査もついでに頼みました。毎年、会社の健康診断が3月にあり、結果を基に先生に相談し、再度採血をして確認をとっていましたが、今年はやり忘れたため採血した次第です。
やはり胃カメラは好きになれませんが、これからも毎年続ける予定です。大腸検査の内視鏡もそろそろやらなければならないかなと思っておりますが、アレはちょっとといった感じです。言っておきますが、当方は内視鏡フェチではありませんから.....
40歳を過ぎたら、検査は毎年やりましょうね。

Posted by walt at
22:20
│Comments(0)
2007年10月26日
142) ビール事業だけで将来が不安
キリンホールディングスが友好的TOBで協和発酵を買収することとなりました。協和発酵は医薬品、バイオケミカル、化学、食品を主に扱う会社で売上高3,542億円、純利益126億円の優良企業です。キリングループは1兆6,600億円の企業であり、協和発酵がグループに加わることにより、2兆円の企業が誕生するわけです。ビールと医薬品とがどのように結びつくのかと思いましたら、キリングループには、売上高672億円のキリンファーマという医薬品の製造販売会社があったわけです。今回のTOBにより協和発酵とキリンファーマが合併し、協和発酵キリン株式会社としてキリンのグループ会社になるようです。
キリンが協和発酵と友好的TOBに踏み切ったのは、将来の売り上げ拡大を目指すのは勿論ですが、飲料事業、特にビール事業の縮小と営業利益率の低さが原因のようです。キリン、アサヒ戦争でマーケットシェアをアサヒに奪われたこともありますが、国内の酒類市場環境が激変したようです。少子高齢化、消費者ニーズの多様化で酒類市場の規模が10年前に比べ20%も下がっており、ビール飲料も同じく20%縮小したようです。今年も1月~9月ベースの出荷量はこの夏の暑さにもかかわらず前年同期比1.3%の減とのことです。現状営業利益の7割を飲料事業で稼いでいるのですが、今後も維持できるかは不透明のようです。又、酒類の8%、飲料の5%の営業利益率と比較するとキリンファーマの医薬関連商品は18%と高い水準にあることも、選択と集中の矛先になったと思われます。
アサヒビールも売り上げの7割が飲料であり、将来的には6割までに下げたいと言っているようです。サッポロビールも7割強がビールの売り上げを占めています。サントリーは食品の比率が高く、ビールは4割ほど占めているようです。サントリーはウィスキーの割合が高いと思われる人がいると思いますが、ウィスキー(サントリーだるま)は全盛期と比較すると現在の売り上げは1/20にまで減っているそうです。よって、ウィスキーを飲む人がほとんどいなくなったことを意味しています。先日、若者がビールを飲まなくなったとテレビで放送していましたが、居酒屋でも「とりあえずビール」が聞けなくなりつつあるようです。人口の減少のみならず、嗜好が変わることによるビール消費の減少を捉え、ビール飲料メーカーは次の成長の種を蒔いているということです。
「135)コラボレーション」をテーマに先週ブログを書きましたが、コラボレーションのみならずM&Aをしなければ生き残れない事業がこれから多くなるのではないでしょうか?昨日の静鉄ストアのチラシに「ぶりしゃぶ」が載っていました。大分産のぶりのスライスでしたが、これから冬にかけてミツカン酢とぶりのスライスで「ぶりしゃぶ」をする広告が増えることでしょう。
キリンが協和発酵と友好的TOBに踏み切ったのは、将来の売り上げ拡大を目指すのは勿論ですが、飲料事業、特にビール事業の縮小と営業利益率の低さが原因のようです。キリン、アサヒ戦争でマーケットシェアをアサヒに奪われたこともありますが、国内の酒類市場環境が激変したようです。少子高齢化、消費者ニーズの多様化で酒類市場の規模が10年前に比べ20%も下がっており、ビール飲料も同じく20%縮小したようです。今年も1月~9月ベースの出荷量はこの夏の暑さにもかかわらず前年同期比1.3%の減とのことです。現状営業利益の7割を飲料事業で稼いでいるのですが、今後も維持できるかは不透明のようです。又、酒類の8%、飲料の5%の営業利益率と比較するとキリンファーマの医薬関連商品は18%と高い水準にあることも、選択と集中の矛先になったと思われます。
アサヒビールも売り上げの7割が飲料であり、将来的には6割までに下げたいと言っているようです。サッポロビールも7割強がビールの売り上げを占めています。サントリーは食品の比率が高く、ビールは4割ほど占めているようです。サントリーはウィスキーの割合が高いと思われる人がいると思いますが、ウィスキー(サントリーだるま)は全盛期と比較すると現在の売り上げは1/20にまで減っているそうです。よって、ウィスキーを飲む人がほとんどいなくなったことを意味しています。先日、若者がビールを飲まなくなったとテレビで放送していましたが、居酒屋でも「とりあえずビール」が聞けなくなりつつあるようです。人口の減少のみならず、嗜好が変わることによるビール消費の減少を捉え、ビール飲料メーカーは次の成長の種を蒔いているということです。
「135)コラボレーション」をテーマに先週ブログを書きましたが、コラボレーションのみならずM&Aをしなければ生き残れない事業がこれから多くなるのではないでしょうか?昨日の静鉄ストアのチラシに「ぶりしゃぶ」が載っていました。大分産のぶりのスライスでしたが、これから冬にかけてミツカン酢とぶりのスライスで「ぶりしゃぶ」をする広告が増えることでしょう。
Posted by walt at
21:05
│Comments(0)
2007年10月25日
141) 交渉のテクニック
慶応大学榊教授は社会心理学の立場で説得や交渉について研究してきた結果、日本人は世界の多くの民族の中でも、交渉に関しては「弱気の遺伝子」と呼んでもいいほどの乏しい力しか持っていないと言っています。 外国や支配者などの強者に対して、平均的日本人はおとなしく、声高にものを言わず、後ずさりする傾向にあるようです。平均的日本人は性格が穏やかで喧嘩も交渉もできない。ところが諸外国を見ていると、欧米であれ、中東であれ、交渉に臨む場面では、「勝ってやろう」という気迫が顔つきや声だけではなく、全身にみなぎっているのが感じられるとのこと。身近なところでは買い物で値切りの交渉をするところから、大きくは国家間の交渉に至るまで、日本人のおとなしさ、淡白さに比べ、諸外国の人々は「何が何でも勝つ」という発想で、交渉に臨む姿勢はしたたかでもあります。
「こうした差はなぜ生じたのか。人類がアフリカで誕生してから、中東、南欧、中欧へと人々は移動し、さらに東のアジア大陸へ移動し、中国大陸の東端や朝鮮半島を経て、日本列島へとたどり着いたのがわれわれの祖先です。強い者たちはその地に住み着いて生活しますが、弱い者たちはその地では食べていけず、ほかの土地へ移動せざるを得なかった。その仮説に基づけば、ユーラシア大陸を東進し、さらに東端の日本列島へと至った我々の祖先は、争いに勝った経験は少なく、負けて新天地を目指した人、あるいは性格が温厚で争い事を好まない人の集まりだったのではないかと思われます。その子孫である私たちは、外部との争いや交渉が苦手なのも無理はないのかもしれません。」と榊教授は述べています。そうかなと思えばそうですし、面白い研究内容だと思いますが、違うといえば違うのではないかと思うようなことです。戦国時代を考えると、一番弱い、争いを好まない祖先同士が領地獲得のため、天下統一のため争ったということになります。
戦後の日本経済の発展は、製品力のみで勝ち得てきたのでしょうか?交渉下手は認めるところが多くありますが、下手は下手なりにうまくやってきたと思います。過去の経験、うまくいったからと言って、将来も同じでよいとは思いませんが、今後も環境に合わせてそれなりにうまくやるのではないでしょうか?交渉下手がいるから、交渉上手がいることになります。皆が交渉上手で勝った、負けたの世界だけですと勝ち負けが中心となってしまうのではないかと危惧してしまいます。
尚、榊教授は、社会心理学で研究・分類されている交渉テクニックをいくつか紹介していました。
(1)フット・イン・ザ・ドア・テクニック(FITD)
小さな要請から始めて、次に大きな要請をする段階説得法。人は一度小さな要請に応じれば、次のより大きな要請に対しても応じやすくなるという心理傾向に基づく
(2)ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック(DITF)
最初の要求が応じかねるほど大きな時は人はその要請を断るが、その後に小さな要請があれば応じやすくなるという心理傾向に基づく。人は譲歩した相手に対しては、自分も譲歩する傾向がある。
(3)ザッツ・ノット・オール・テクニック
DITFの変形。DITFと異なる点は、相手の拒否の返事を待たずに要請水準を下げていく、または相手にプラスになるものを付け加えていくという点。テレビショッピングで「今日はさらにこれとこれをおつけして同じお値段」という宣伝文句がこれに該当する。
(4)ロー・ボール・テクニック
相手が取りやすいボールを投げてまず取らせてしまう、つまり決定させてしまい、後で良い条件を取り除いたり、逆に悪い条件を付加するという方法。人は一度ある決定をしてしまうと、後でその内容が変わっても――すなわち良い条件が取り除かれたり、逆に悪い条件が追加されたりしても――なかなか決定を変えようとしないという心理傾向を利用。
(5)フォー・ウォールズ・テクニック
「イエス」「イエス」と答えさせておいて、最後にも「イエス」と答えさせる方法。
(6)ブーメラン・テクニック
相手の考えと同じ考えをわざと強調してブーメラン反応(当初の意見とは逆の意見が頭に浮かんでくること)を誘い、相手を逆方向に意見変容させる技法。
もしかしたら知らず知らずのうちに同じようなことをしているかも知れませんね。いずれにしても、我々日本人は交渉術を学ばなければならないかもしれません。今後人口の現象による日本経済が縮小する傾向にあることは間違いありません。世界を相手にビジネスを考えなければならないはずです。とあるジャーナリストが言っていましたがアメリカのサブプライムローンで失敗した日本の金融機関は野村證券だけだったようです。他の金融機関は、賢かったのではなくサブプライムローンのことを知らなかっただけのようです。なんともお粗末なことではないでしょうか?
まずは国際コミュニケーションから学ぶのが良いと思います。
「こうした差はなぜ生じたのか。人類がアフリカで誕生してから、中東、南欧、中欧へと人々は移動し、さらに東のアジア大陸へ移動し、中国大陸の東端や朝鮮半島を経て、日本列島へとたどり着いたのがわれわれの祖先です。強い者たちはその地に住み着いて生活しますが、弱い者たちはその地では食べていけず、ほかの土地へ移動せざるを得なかった。その仮説に基づけば、ユーラシア大陸を東進し、さらに東端の日本列島へと至った我々の祖先は、争いに勝った経験は少なく、負けて新天地を目指した人、あるいは性格が温厚で争い事を好まない人の集まりだったのではないかと思われます。その子孫である私たちは、外部との争いや交渉が苦手なのも無理はないのかもしれません。」と榊教授は述べています。そうかなと思えばそうですし、面白い研究内容だと思いますが、違うといえば違うのではないかと思うようなことです。戦国時代を考えると、一番弱い、争いを好まない祖先同士が領地獲得のため、天下統一のため争ったということになります。
戦後の日本経済の発展は、製品力のみで勝ち得てきたのでしょうか?交渉下手は認めるところが多くありますが、下手は下手なりにうまくやってきたと思います。過去の経験、うまくいったからと言って、将来も同じでよいとは思いませんが、今後も環境に合わせてそれなりにうまくやるのではないでしょうか?交渉下手がいるから、交渉上手がいることになります。皆が交渉上手で勝った、負けたの世界だけですと勝ち負けが中心となってしまうのではないかと危惧してしまいます。
尚、榊教授は、社会心理学で研究・分類されている交渉テクニックをいくつか紹介していました。
(1)フット・イン・ザ・ドア・テクニック(FITD)
小さな要請から始めて、次に大きな要請をする段階説得法。人は一度小さな要請に応じれば、次のより大きな要請に対しても応じやすくなるという心理傾向に基づく
(2)ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック(DITF)
最初の要求が応じかねるほど大きな時は人はその要請を断るが、その後に小さな要請があれば応じやすくなるという心理傾向に基づく。人は譲歩した相手に対しては、自分も譲歩する傾向がある。
(3)ザッツ・ノット・オール・テクニック
DITFの変形。DITFと異なる点は、相手の拒否の返事を待たずに要請水準を下げていく、または相手にプラスになるものを付け加えていくという点。テレビショッピングで「今日はさらにこれとこれをおつけして同じお値段」という宣伝文句がこれに該当する。
(4)ロー・ボール・テクニック
相手が取りやすいボールを投げてまず取らせてしまう、つまり決定させてしまい、後で良い条件を取り除いたり、逆に悪い条件を付加するという方法。人は一度ある決定をしてしまうと、後でその内容が変わっても――すなわち良い条件が取り除かれたり、逆に悪い条件が追加されたりしても――なかなか決定を変えようとしないという心理傾向を利用。
(5)フォー・ウォールズ・テクニック
「イエス」「イエス」と答えさせておいて、最後にも「イエス」と答えさせる方法。
(6)ブーメラン・テクニック
相手の考えと同じ考えをわざと強調してブーメラン反応(当初の意見とは逆の意見が頭に浮かんでくること)を誘い、相手を逆方向に意見変容させる技法。
もしかしたら知らず知らずのうちに同じようなことをしているかも知れませんね。いずれにしても、我々日本人は交渉術を学ばなければならないかもしれません。今後人口の現象による日本経済が縮小する傾向にあることは間違いありません。世界を相手にビジネスを考えなければならないはずです。とあるジャーナリストが言っていましたがアメリカのサブプライムローンで失敗した日本の金融機関は野村證券だけだったようです。他の金融機関は、賢かったのではなくサブプライムローンのことを知らなかっただけのようです。なんともお粗末なことではないでしょうか?
まずは国際コミュニケーションから学ぶのが良いと思います。
Posted by walt at
21:53
│Comments(0)
2007年10月24日
140) ヒール、サンダル、革靴
今日、会社を休んで長野県駒ヶ根市にある駒ケ岳に行ってきました。先週より天気図とにらめっこをして、先週は天気が安定せず、金曜日に降った雨が、駒ケ岳では雪となってしまいました。当日富士山も雪になり、土曜日には冠雪した富士山が見られました。その後天気が安定し、本日行くことに決定した次第です。中央アルプス駒ケ岳はロープウェーで2,612mまで上ります。そこが千畳敷と呼ばれる場所です。
朝5:30に同僚に迎えに来てもらい、国道52号線を走り、増穂町から中部横断道路に乗り、双葉
JCから中央高速道路に入り、駒ヶ根ICで降りました。中部縦貫道路ができていたのは驚きでしたが、中央高速までの約15kmほどの間にすれ違った車はたった2台でした。地元の人が使用しないと言うことが良くわかりました。この中部縦貫道路は静岡にとっては欲しい道です。増穂ICの係員に「何時になったら静岡まで延びますか?」と聞いたところ「10年かかるよ」と言われました。何故増穂までできていて、その先および静岡側は全くてつかずで理解に苦しみます。
菅の台バスセンター駐車場に車を置き(駐車料400円)、バスとロープウェーの往復セット料金3,800円を払いました。駒ケ岳は上高地や尾瀬と同じようにマイカー規制しています。ここは観光バスも乗り換えなければなりません。しらびだいらから61人乗りのロープウェーに乗り約8分で千畳敷に着きました。10時に到着しましたので調度4時間半かかったということになります。快晴で雲ひとつ無い天候にこのうえも無い感激を覚え大満足でした。2時間かけて山頂まで上りそこからは360度すべて見渡す事ができました。南は富士山、北岳、南アルプスの山々、東には八ヶ岳、北には御岳山、乗鞍岳、穂高連峰、槍ヶ岳の穂先まで見ることができました。
ほとんどの人たちが登山靴、トレッキングシューズを履いているのですが、団体旅行客の多くはスニーカーで途中まで登っていました。中には、ヒールの女性、サンダルの男性、革靴の男性、スカートを履いた女性までおり、驚く限りです。見かねて、あぶないからと伝えましたが、聞く耳持たずといった態度でした。登山経験者ならわかると思いますが、登りより下りの方が危ないのです。登ってはみたものの下るに苦労するはずですし、怖いと感じることもあります。足元が危なすぎます、そのような履物では。添乗員さんは、強く指導すべきと思います。事故になってからでは遅いはずです。危機管理
ができていないことには残念です。
2,600mという別世界を多くの人に体験してもらうことは、とても良い事ですが、最低限のルール、マナーは守ってもらいたいものです、楽しい旅にするためにも。
2612m中央アルプス千畳敷: http://www17.ocn.ne.jp/~komagane/hataraku/syokuba.htm


朝5:30に同僚に迎えに来てもらい、国道52号線を走り、増穂町から中部横断道路に乗り、双葉
JCから中央高速道路に入り、駒ヶ根ICで降りました。中部縦貫道路ができていたのは驚きでしたが、中央高速までの約15kmほどの間にすれ違った車はたった2台でした。地元の人が使用しないと言うことが良くわかりました。この中部縦貫道路は静岡にとっては欲しい道です。増穂ICの係員に「何時になったら静岡まで延びますか?」と聞いたところ「10年かかるよ」と言われました。何故増穂までできていて、その先および静岡側は全くてつかずで理解に苦しみます。
菅の台バスセンター駐車場に車を置き(駐車料400円)、バスとロープウェーの往復セット料金3,800円を払いました。駒ケ岳は上高地や尾瀬と同じようにマイカー規制しています。ここは観光バスも乗り換えなければなりません。しらびだいらから61人乗りのロープウェーに乗り約8分で千畳敷に着きました。10時に到着しましたので調度4時間半かかったということになります。快晴で雲ひとつ無い天候にこのうえも無い感激を覚え大満足でした。2時間かけて山頂まで上りそこからは360度すべて見渡す事ができました。南は富士山、北岳、南アルプスの山々、東には八ヶ岳、北には御岳山、乗鞍岳、穂高連峰、槍ヶ岳の穂先まで見ることができました。
ほとんどの人たちが登山靴、トレッキングシューズを履いているのですが、団体旅行客の多くはスニーカーで途中まで登っていました。中には、ヒールの女性、サンダルの男性、革靴の男性、スカートを履いた女性までおり、驚く限りです。見かねて、あぶないからと伝えましたが、聞く耳持たずといった態度でした。登山経験者ならわかると思いますが、登りより下りの方が危ないのです。登ってはみたものの下るに苦労するはずですし、怖いと感じることもあります。足元が危なすぎます、そのような履物では。添乗員さんは、強く指導すべきと思います。事故になってからでは遅いはずです。危機管理
ができていないことには残念です。
2,600mという別世界を多くの人に体験してもらうことは、とても良い事ですが、最低限のルール、マナーは守ってもらいたいものです、楽しい旅にするためにも。
2612m中央アルプス千畳敷: http://www17.ocn.ne.jp/~komagane/hataraku/syokuba.htm


Posted by walt at
22:08
│Comments(0)
2007年10月23日
139) 日産GT-R
東京モーターショーが10/26から11/11(一般公開は10/27から)までの17日間開催されます。17日間も開催される展示会は日本では唯一のものです。会社の展示会に出展したことが何度もありますが、ほとんど3日間でしたが、それでも最終日はくたくたに疲れてしまいましたので、17日間はあまりにも長いと思います。勿論出展企業は超大手ですので、展示会開催中は上手にローテーションを組んでいることと思います。でも、仕事を請け負っている業者さんはぶっ通しで働かなければならないいでしょう。お察しいたします。
この展示会の入場料は大人前売り券1,100円、当日券1,300円のようですが、前売り券が購入できないと言っていた人がいますが本当でしょうか?購入できなかった為、11月末から開催される大阪モーターショーのチケットを購入したと言っていました。17日間で何人の入場者があるのでしょうか?驚くほどの数でしょうね。
日曜日の夜のニュース番組で日産自動車の新車「日産GT-R」のことを特集していました。GT-Rといえば、そうスカイラインGT-Rですね。2002年に販売中止となり5年ぶりの復活のようです。スカイラインの名前が無くなり「日産GT-R」と新たな名前となりました。日産の力の入れようがわかります。テレビではゴーン社長が登場し、このGT-Rのすばらしさを語っていました。10/26からの東京モーターショーを控えたこの時点にGT-Rをスタジオに乗り入れたわけです。ゴーン社長はドイツのアウトバーンで310Kmのスピードで走ったと言っていました。勿論日本では100kmしかスピードを出せないですが... 価格は780万円とのこと。ゴーン社長はしきりにスーパーカーと呼んでいました。又、月産1,000台しか生産できないとのことのようです。
1,000台しかとの表現でしたが、実際1,000台も売れるのでしょうか?何年か前に同じくフェアレディZが販売され、注目を浴びましたが、このGT-Rはどのようなものでしょうか?自動車専門誌の記者は注目に値すると言っておりましたが.... 我々の世代はGT-Rにあこがれた世代ではありません。もう少し年配の方々の憧れの車だったと思います。すると、当時をかえりみて乗ってみたいと思う人たちが多いかも知れません。それにしても2ドアのクーペ、4人乗れるとのことですが基本的には2人乗りですよね。当方は興味がありませんが、果たしてその行方はどうなることでしょうか。
日産GT-R: http://www.gtrnissan.com/
この展示会の入場料は大人前売り券1,100円、当日券1,300円のようですが、前売り券が購入できないと言っていた人がいますが本当でしょうか?購入できなかった為、11月末から開催される大阪モーターショーのチケットを購入したと言っていました。17日間で何人の入場者があるのでしょうか?驚くほどの数でしょうね。
日曜日の夜のニュース番組で日産自動車の新車「日産GT-R」のことを特集していました。GT-Rといえば、そうスカイラインGT-Rですね。2002年に販売中止となり5年ぶりの復活のようです。スカイラインの名前が無くなり「日産GT-R」と新たな名前となりました。日産の力の入れようがわかります。テレビではゴーン社長が登場し、このGT-Rのすばらしさを語っていました。10/26からの東京モーターショーを控えたこの時点にGT-Rをスタジオに乗り入れたわけです。ゴーン社長はドイツのアウトバーンで310Kmのスピードで走ったと言っていました。勿論日本では100kmしかスピードを出せないですが... 価格は780万円とのこと。ゴーン社長はしきりにスーパーカーと呼んでいました。又、月産1,000台しか生産できないとのことのようです。
1,000台しかとの表現でしたが、実際1,000台も売れるのでしょうか?何年か前に同じくフェアレディZが販売され、注目を浴びましたが、このGT-Rはどのようなものでしょうか?自動車専門誌の記者は注目に値すると言っておりましたが.... 我々の世代はGT-Rにあこがれた世代ではありません。もう少し年配の方々の憧れの車だったと思います。すると、当時をかえりみて乗ってみたいと思う人たちが多いかも知れません。それにしても2ドアのクーペ、4人乗れるとのことですが基本的には2人乗りですよね。当方は興味がありませんが、果たしてその行方はどうなることでしょうか。
日産GT-R: http://www.gtrnissan.com/
Posted by walt at
21:47
│Comments(2)
2007年10月22日
138)ストレスを貯めない方法
株式会社武蔵野の小山社長が日経BPのコラムで「悩まない、ストレスを貯めない」と言っておられました。勿論我々と同じように悩み、苦しむようですが、それをストレスとせず、貯めないということでした。その方法(悩みを忘れる仕組み)として2点あり、一点は「悩む暇もないくらい忙しくすること」、二点目は「現在のつらさは将来大きな財産になる」と考え行動するということだそうです。
小山氏の言葉を借りると、「悩む暇もないくらい忙しくすること」については、「ひとつ仕事が終われば次の仕事、それが終わればまた次の仕事という具合に、スケジュールを入れる。すると、悩んでいる暇がなくなる。人間は、暇だとたいていろくなことをしません。なまじ自省する時間があるから思考の隘路(あいろ)に陥って「出口なし」になる。 「考える」とは、過去の自分の経験を引っ張り出してくることに他ならない。 つまり、今現在ある悩みが解決できないでいるとすれば、いくら考えたところでほとんど無意味であり、そんなことで時間を無駄に費やすくらいなら、まず行動して自分の体験の幅を広げたほうがよほど確実です。」と
「現在の辛さは将来大きな財産になる」については、「止まない雨も明けない夜も、今まで一度もなかった。今、あなたが抱えている悩みや苦しみだって、わたしの経験した悩みと同じことです。歯を食いしばってやり過ごし、そして乗り越えることで、その辛い体験はあなたにとってかけがえのない財産になる。そう考えることができれば、あらゆる人にとって「無駄な過去」は存在しない。過去はすべて善です。他人と過去は変えられない。しかし自分と未来は変えられる。今の悩みや苦しみも、いつかは
過去のものになります。それが今後の糧となるか否かは、その悩みや苦しみの中から何をつかみ取れるかにかかっています。」と。
当方過去50年を振り返ってみると、忙しい時、暇な時が勿論ありました。忙しいときは、やはり悩んでいる暇がありませんでした。言い換えれば、悩んでいても仕方ないということだったのではないでしょうか?その反面、悩んでばかりいることがありました。しかし今思えば、遠い過去のことであり、現在があるのは何とか解決したと言うことになります。どなただったか忘れてしまいましたが、とあるコーチングの先生が「困難、苦境に遭遇したのなら、それは、自分が成長する上で必要なことであり、喜びでありそのことに感謝しましょう」と、言っていました。勿論困難、苦境に立ち向かうことは誰でも嫌なことです。しかし、毎日が平々凡々としているはずがありません。それが、人生と思えば、もしかして、運命と言うレールに乗っていることかも知れないと思うと、乗り越えるしかありません。
小山氏のコラムを読み、そんなことをふと考えました。又、何かにチャレンジしなければと思った次第です。
小山氏の言葉を借りると、「悩む暇もないくらい忙しくすること」については、「ひとつ仕事が終われば次の仕事、それが終わればまた次の仕事という具合に、スケジュールを入れる。すると、悩んでいる暇がなくなる。人間は、暇だとたいていろくなことをしません。なまじ自省する時間があるから思考の隘路(あいろ)に陥って「出口なし」になる。 「考える」とは、過去の自分の経験を引っ張り出してくることに他ならない。 つまり、今現在ある悩みが解決できないでいるとすれば、いくら考えたところでほとんど無意味であり、そんなことで時間を無駄に費やすくらいなら、まず行動して自分の体験の幅を広げたほうがよほど確実です。」と
「現在の辛さは将来大きな財産になる」については、「止まない雨も明けない夜も、今まで一度もなかった。今、あなたが抱えている悩みや苦しみだって、わたしの経験した悩みと同じことです。歯を食いしばってやり過ごし、そして乗り越えることで、その辛い体験はあなたにとってかけがえのない財産になる。そう考えることができれば、あらゆる人にとって「無駄な過去」は存在しない。過去はすべて善です。他人と過去は変えられない。しかし自分と未来は変えられる。今の悩みや苦しみも、いつかは
過去のものになります。それが今後の糧となるか否かは、その悩みや苦しみの中から何をつかみ取れるかにかかっています。」と。
当方過去50年を振り返ってみると、忙しい時、暇な時が勿論ありました。忙しいときは、やはり悩んでいる暇がありませんでした。言い換えれば、悩んでいても仕方ないということだったのではないでしょうか?その反面、悩んでばかりいることがありました。しかし今思えば、遠い過去のことであり、現在があるのは何とか解決したと言うことになります。どなただったか忘れてしまいましたが、とあるコーチングの先生が「困難、苦境に遭遇したのなら、それは、自分が成長する上で必要なことであり、喜びでありそのことに感謝しましょう」と、言っていました。勿論困難、苦境に立ち向かうことは誰でも嫌なことです。しかし、毎日が平々凡々としているはずがありません。それが、人生と思えば、もしかして、運命と言うレールに乗っていることかも知れないと思うと、乗り越えるしかありません。
小山氏のコラムを読み、そんなことをふと考えました。又、何かにチャレンジしなければと思った次第です。
Posted by walt at
22:28
│Comments(0)
2007年10月21日
137) 久しぶりの手揉み茶
今年から、清水手揉み茶保存会の会員となり、イベントの参加や手揉みの練習に行っています。一人前になるには10年ほどかかるようですが、何も手に技術の無い当方にとっては、頑張ってみたいと思っております。
今日久しぶりに練習をする機会がありました。前回は6月でしたので4ヶ月ぶりとなります。お茶は一番茶が4月末でn二番茶が6月となります。9月に秋のお茶が採れますが、摘んだお茶を揉むのではなく、練習用は春摘んだものを一次工程(お茶の葉を蒸し、粗揉という揉み工程)を済ませ冷凍したものを回答して使用します。昔は練習用にはお茶使わず、わらを5cmほどにカットして使用していたとのことです。冷凍技術の進歩と共に、このようなことまで利用できるようになりました。冷凍といえば、赤福の問題がありましたね。解凍日が製造日にして、又、日をまたいでパッケージングして当日製造にしていたこと、再度パッケージングして販売していたことなど発覚しました。製造日の記載ではなく、賞味期限を記載したら問題にならなかったのでしょうか?そういえばクリスマスケーキの日付けの記載はどうなっているのでしょうか?冷凍技術の進歩によって良いことも悪いこともあるようですね。
現在は機械でお茶を作りますが、手揉みは技術の伝承と、お茶文化となります。手揉みでお茶を作るに時間がかかりますのでビジネスとしては成り立ちません。100g当たり数千円となってしまうからです。品評会ではお祝儀相場にもなっており、高額で取引されるようですが、手揉みをしている人たち(多くが生産者)は良いお茶を作ることを目標に努力しています。献上茶は勿論手揉みのようです。
手揉みはほい炉と呼ばれる台(下から火で暖める)を使用して作ります。11月に開催される世界お茶まつりで手揉みの実演がされるそうです。どうやって作るか興味のある方は是非見に行っていただきたいと思います。
ほい炉


今日久しぶりに練習をする機会がありました。前回は6月でしたので4ヶ月ぶりとなります。お茶は一番茶が4月末でn二番茶が6月となります。9月に秋のお茶が採れますが、摘んだお茶を揉むのではなく、練習用は春摘んだものを一次工程(お茶の葉を蒸し、粗揉という揉み工程)を済ませ冷凍したものを回答して使用します。昔は練習用にはお茶使わず、わらを5cmほどにカットして使用していたとのことです。冷凍技術の進歩と共に、このようなことまで利用できるようになりました。冷凍といえば、赤福の問題がありましたね。解凍日が製造日にして、又、日をまたいでパッケージングして当日製造にしていたこと、再度パッケージングして販売していたことなど発覚しました。製造日の記載ではなく、賞味期限を記載したら問題にならなかったのでしょうか?そういえばクリスマスケーキの日付けの記載はどうなっているのでしょうか?冷凍技術の進歩によって良いことも悪いこともあるようですね。
現在は機械でお茶を作りますが、手揉みは技術の伝承と、お茶文化となります。手揉みでお茶を作るに時間がかかりますのでビジネスとしては成り立ちません。100g当たり数千円となってしまうからです。品評会ではお祝儀相場にもなっており、高額で取引されるようですが、手揉みをしている人たち(多くが生産者)は良いお茶を作ることを目標に努力しています。献上茶は勿論手揉みのようです。
手揉みはほい炉と呼ばれる台(下から火で暖める)を使用して作ります。11月に開催される世界お茶まつりで手揉みの実演がされるそうです。どうやって作るか興味のある方は是非見に行っていただきたいと思います。
ほい炉


Posted by walt at
22:50
│Comments(2)
2007年10月20日
136) 「辻利、綾鷹、おーいお茶プレミアム」飲み比べ
「急須で入れたお茶を」をキャッチフレーズにペット茶大手がこの秋、続々と新製品を発売しました。ビールが今年プレミアムブームだったように、お茶もその傾向と京都の老舗とのコラボレーションが注目を浴びています。辻利がJT、綾鷹はコカコーラ、おーいお茶プレミアムは伊藤園です。迎え撃つサントリーの福寿園は静観といったところでしょうか?
本日、我々のしずおか日本茶アドワンクラブの定例会が開催されました。昨年10/1に日本茶インストラクター協会のアドバイザーに認定され、結成されたクラブです。早いもので1年が経過し、クラブも1周年となりました。活動報告、会計報告、来年度の行動計画などが話し合われ、その後、皆でこれら新製品のお茶3種と、シェアーNo.1の伊藤園の「おーいお茶」、そしてサントリーの福寿園計5種の飲み比べをしました。問うクラブでは定例会の時に、色々なお茶を飲み比べていましたが、ペットのお茶の飲み比べは今回が初めてです。
まずは、ペット茶シェアNo.1の伊藤園「おーいお茶」を基準として最初に飲みました。当方「おーいお茶」はほとんど飲んだことが無かったため、飲んでみて、ちょっとほうじ茶っぽい口当たりがしました。その後、同じく「おーいお茶」のプレミアムを飲みました。一般的なペットのお茶は500mlですが、これはスマートボトルで350mlです。価格もコンビニで158円だったと思います。10円高いということです。(コカコーラの綾鷹が158円だったかもしれません)このプレミアムが何処で購入できるか伊藤園のお客様窓口に問い合わせたところ、セブンイレブンには無く、ファミマ、ローソンにあるとのことでした。又、特徴を聞くと、火入れが違うとのことでした。実際飲んでみると、なるほど、このプレミアムもほうじ茶の香り(火入れが強い)がしましたので、言う通りだと思いました。
辻利は癖が無く飲みやすいといった感じでした。がぶ飲みするには良いかも。綾鷹はキャッチフレーズに、濁りを謳っていますが、その通り、綾鷹のみ濁っていました。12名で飲み比べしましたが、比較的偏った好みとなりました。この秋発売されたものは、「急須で入れた」をポイントとしています。勿論茶葉を急須で入れたと同じような、味、水色は、香りは無理ですが、しいて言えば綾鷹が近いのではといった感想でした。
京都老舗とのコラボレーションのお茶、プレミアムのお茶は一過性のものか?それとも今後も継続され、定番となるか?その鍵は我々消費者が握っています。貴方はこれらのお茶をどう思いますか?

本日、我々のしずおか日本茶アドワンクラブの定例会が開催されました。昨年10/1に日本茶インストラクター協会のアドバイザーに認定され、結成されたクラブです。早いもので1年が経過し、クラブも1周年となりました。活動報告、会計報告、来年度の行動計画などが話し合われ、その後、皆でこれら新製品のお茶3種と、シェアーNo.1の伊藤園の「おーいお茶」、そしてサントリーの福寿園計5種の飲み比べをしました。問うクラブでは定例会の時に、色々なお茶を飲み比べていましたが、ペットのお茶の飲み比べは今回が初めてです。
まずは、ペット茶シェアNo.1の伊藤園「おーいお茶」を基準として最初に飲みました。当方「おーいお茶」はほとんど飲んだことが無かったため、飲んでみて、ちょっとほうじ茶っぽい口当たりがしました。その後、同じく「おーいお茶」のプレミアムを飲みました。一般的なペットのお茶は500mlですが、これはスマートボトルで350mlです。価格もコンビニで158円だったと思います。10円高いということです。(コカコーラの綾鷹が158円だったかもしれません)このプレミアムが何処で購入できるか伊藤園のお客様窓口に問い合わせたところ、セブンイレブンには無く、ファミマ、ローソンにあるとのことでした。又、特徴を聞くと、火入れが違うとのことでした。実際飲んでみると、なるほど、このプレミアムもほうじ茶の香り(火入れが強い)がしましたので、言う通りだと思いました。
辻利は癖が無く飲みやすいといった感じでした。がぶ飲みするには良いかも。綾鷹はキャッチフレーズに、濁りを謳っていますが、その通り、綾鷹のみ濁っていました。12名で飲み比べしましたが、比較的偏った好みとなりました。この秋発売されたものは、「急須で入れた」をポイントとしています。勿論茶葉を急須で入れたと同じような、味、水色は、香りは無理ですが、しいて言えば綾鷹が近いのではといった感想でした。
京都老舗とのコラボレーションのお茶、プレミアムのお茶は一過性のものか?それとも今後も継続され、定番となるか?その鍵は我々消費者が握っています。貴方はこれらのお茶をどう思いますか?

Posted by walt at
22:35
│Comments(0)
2007年10月19日
135) コラボレーション
世の中はコラボレーションが盛んに行われています。消費者の多様化に伴い、各メーカーは自社のみの技術では、新しいものを開発する、新商品を企画開発する力がなくなっています。又、消費者のニーズ、ウォンツに対応するためにはコラボレーションが必要となってきています。アサヒとカゴメが開発したトマトジュースのお酒もその良い例です。
今、食品メーカー各社がコラボレーションによる「クール」な展開をしているようです。サントリーはこれまでコーンスープなどしかなかった缶入りスープを東ハトが展開する「ハバネロ」ブランドを利用しようと、サントリーが持ちかけ、辛いスープを開発した要です。異業種とのコラボレーションで新たに市場を開拓することが狙いのようです。又、サントリーは先月からロッテと組んで、ウイスキーとチョコレートを各店舗の同じ売り場に並べて売る試みも始めたそうです。来年のバレンタインでの拡販も狙っているようです。
この冬の鍋は「ぶりしゃぶ」がヒットするに違いありません。鍋に使う水、ポン酢、ビール3社が「ぶりしゃぶ」を共通テーマにした広告戦略を11月からスタートさせるようです。「費用を3社で等分できるので、コスト面でも助かる」ということもありますがコラボレーションによって、付加価値的な要素の広告ができ、消費者にアピールできることが最大のメリットのようです。水、ポン酢、ビール3社で折角宣伝を打っても、肝心な「ぶり」が手に入らなければお手上げですよね。今年のぶりは、お手頃になるでしょうか?
又、百貨店の老舗、三越とインターネット大手のヤフーが企画した業界初のイベントが今週から始まりました。それは出店数1万6,000店舗のヤフーショッピングの中で、人気の高いのがお取り寄せグルメの中から、その上位ランキングの総菜やスイーツなど、全国12の店舗を三越が選びました。ネット利用者のみならず、店頭で販売する試みのようです。三越は全国ネットで情報網を持っているが、バイヤーも知らなかった商品も数多くあり、相乗効果も期待できるようです。
食品業界のみならず、いろいろな分野でコラボレーションが始まっています。すでにご存知のことですが、パナソニックがデジカメの開発でドイツのカメラの老舗ライカと組みました。ライカといえばカメラファンにとっては逸品です。先日開催されたエレクトロニクスの展示会CEATECでも「貴方達は競合ではなかったの?」と思われる会社同士が、得意分野の技術を合わせた開発コンセプトモデルを展示していました。いまや、各社自社技術のみでは、新製品の開発がスムースに出来ず、又開発工数、日数も非常にかかり開発コストのアップにつながっています。以前より「選択と集中」と言われてきましたが、どちらかと言うと日本企業は同じような技術を同じように数社で開発してきました。良い例が携帯電話であり、国内メーカーは多くありますがこのところ共同開発や技術の売却が進んでいます。日本国内で同じように競争してきたため、世界市場では日本のメーカーがシェアを取れない状況にもなってしまいました。今後益々「選択と集中」の基、益々コラボレーションが盛んになるでしょう?
異業種のコラボレーション考えてみませんか?
今、食品メーカー各社がコラボレーションによる「クール」な展開をしているようです。サントリーはこれまでコーンスープなどしかなかった缶入りスープを東ハトが展開する「ハバネロ」ブランドを利用しようと、サントリーが持ちかけ、辛いスープを開発した要です。異業種とのコラボレーションで新たに市場を開拓することが狙いのようです。又、サントリーは先月からロッテと組んで、ウイスキーとチョコレートを各店舗の同じ売り場に並べて売る試みも始めたそうです。来年のバレンタインでの拡販も狙っているようです。
この冬の鍋は「ぶりしゃぶ」がヒットするに違いありません。鍋に使う水、ポン酢、ビール3社が「ぶりしゃぶ」を共通テーマにした広告戦略を11月からスタートさせるようです。「費用を3社で等分できるので、コスト面でも助かる」ということもありますがコラボレーションによって、付加価値的な要素の広告ができ、消費者にアピールできることが最大のメリットのようです。水、ポン酢、ビール3社で折角宣伝を打っても、肝心な「ぶり」が手に入らなければお手上げですよね。今年のぶりは、お手頃になるでしょうか?
又、百貨店の老舗、三越とインターネット大手のヤフーが企画した業界初のイベントが今週から始まりました。それは出店数1万6,000店舗のヤフーショッピングの中で、人気の高いのがお取り寄せグルメの中から、その上位ランキングの総菜やスイーツなど、全国12の店舗を三越が選びました。ネット利用者のみならず、店頭で販売する試みのようです。三越は全国ネットで情報網を持っているが、バイヤーも知らなかった商品も数多くあり、相乗効果も期待できるようです。
食品業界のみならず、いろいろな分野でコラボレーションが始まっています。すでにご存知のことですが、パナソニックがデジカメの開発でドイツのカメラの老舗ライカと組みました。ライカといえばカメラファンにとっては逸品です。先日開催されたエレクトロニクスの展示会CEATECでも「貴方達は競合ではなかったの?」と思われる会社同士が、得意分野の技術を合わせた開発コンセプトモデルを展示していました。いまや、各社自社技術のみでは、新製品の開発がスムースに出来ず、又開発工数、日数も非常にかかり開発コストのアップにつながっています。以前より「選択と集中」と言われてきましたが、どちらかと言うと日本企業は同じような技術を同じように数社で開発してきました。良い例が携帯電話であり、国内メーカーは多くありますがこのところ共同開発や技術の売却が進んでいます。日本国内で同じように競争してきたため、世界市場では日本のメーカーがシェアを取れない状況にもなってしまいました。今後益々「選択と集中」の基、益々コラボレーションが盛んになるでしょう?
異業種のコラボレーション考えてみませんか?
Posted by walt at
21:43
│Comments(0)
2007年10月18日
134) 「ワンコイン」商品
少し前まではワンコインで自動販売機の清涼飲料、コーヒーが買えましたが、現在ワンコインで購入できるものは何があるでしょうか?このところファーストフード大手各社は100円、500円硬貨1枚で購入できる「ワンコイン商品」を強化しているようです。
ケンタッキーフライドチキンは10/18から500円のチキンセットを期間限定(10/18~11/28)で通常670円のチキンセット(チキン2ピース、フリフリポテト)を販売するそうです。又、ロッテリアはすでに10/12より「OTOKU\100」メニューを導入して、ハンバーガー、フレンチフライS、シナモンアップルパイ、新製品の「スナックチキン」たこ焼きスナック「ふるタコ」の5商品を100円で販売しています。両社ともワンコイン商品は価格がわかりやすく、おつりがいらないことから人気があり、又、マクドナルドが100円商品で業績を拡大させているため、対抗手段としての位置づけもあるようです。
マクドナルドは今年1月から9月まで連続して短月売り上げが過去最高を記録しており、100円メニューの導入が功を奏しているため、同業他社のファーストフード各社は戦略上無視できないようです。当方、ハンバーガーもフライドチキンも嫌いではありませんが、ほとんど食べる機会がありません。仕事の外出時お昼に時間がないときマックに行くことはありますが、休日に行くことはありません。年に1度か2度ほどケンタッキーのスパイシーチキンが食べたくなり、妻と休日行くことはありますが、それ以外は全くありません。500円になったからと言って「行ってみよう」とは思いません。ロッテリアは、100円商品が増えれば来客数は増えると思いますが、利益減分を数量でカバーできるかどうかわかりません。いずれにしても、一度下げた価格を上げることは容易ではありませんので、将来各社どのような戦略に転ずるか見ものです。
ワンコイン商品といえば、東京に500円タクシーが走っていましたが、現在も継続しているでしょうか?確かトヨタのヴィッツガベースのタクシーだったと記憶しています。日本のタクシーは「鶏卵論」となっています。先日値上げ申請が出されたようですが、利用客が少ないから値上げしなければならないのか、価格が高いから利用しないのかどちらでしょうか。当方の場合、タクシーに乗ることはめったにありません。ただ、安くなれば多分利用します。先日当方の犬が調子が悪くなったとき、母親は近所の獣医さんまでタクシーに乗せて行ったようです。乗せてくれたタクシーも良くOKしてくれたなと
思いますが、母親もタクシーで行くことを良く決心したと思います。ちなみに行った獣医さんは臨時休診で結局家まで犬と歩いて帰ってきたとのことでした。
このところ、いろいろな商品が値上げされていますが、価格を上げるより内容量を10%下げてもらったほうが当方は納得いくのですが、貴方は如何でしょうか?「100円ショップ」は105円ではなく100円がいいですね。
ケンタッキーフライドチキンは10/18から500円のチキンセットを期間限定(10/18~11/28)で通常670円のチキンセット(チキン2ピース、フリフリポテト)を販売するそうです。又、ロッテリアはすでに10/12より「OTOKU\100」メニューを導入して、ハンバーガー、フレンチフライS、シナモンアップルパイ、新製品の「スナックチキン」たこ焼きスナック「ふるタコ」の5商品を100円で販売しています。両社ともワンコイン商品は価格がわかりやすく、おつりがいらないことから人気があり、又、マクドナルドが100円商品で業績を拡大させているため、対抗手段としての位置づけもあるようです。
マクドナルドは今年1月から9月まで連続して短月売り上げが過去最高を記録しており、100円メニューの導入が功を奏しているため、同業他社のファーストフード各社は戦略上無視できないようです。当方、ハンバーガーもフライドチキンも嫌いではありませんが、ほとんど食べる機会がありません。仕事の外出時お昼に時間がないときマックに行くことはありますが、休日に行くことはありません。年に1度か2度ほどケンタッキーのスパイシーチキンが食べたくなり、妻と休日行くことはありますが、それ以外は全くありません。500円になったからと言って「行ってみよう」とは思いません。ロッテリアは、100円商品が増えれば来客数は増えると思いますが、利益減分を数量でカバーできるかどうかわかりません。いずれにしても、一度下げた価格を上げることは容易ではありませんので、将来各社どのような戦略に転ずるか見ものです。
ワンコイン商品といえば、東京に500円タクシーが走っていましたが、現在も継続しているでしょうか?確かトヨタのヴィッツガベースのタクシーだったと記憶しています。日本のタクシーは「鶏卵論」となっています。先日値上げ申請が出されたようですが、利用客が少ないから値上げしなければならないのか、価格が高いから利用しないのかどちらでしょうか。当方の場合、タクシーに乗ることはめったにありません。ただ、安くなれば多分利用します。先日当方の犬が調子が悪くなったとき、母親は近所の獣医さんまでタクシーに乗せて行ったようです。乗せてくれたタクシーも良くOKしてくれたなと
思いますが、母親もタクシーで行くことを良く決心したと思います。ちなみに行った獣医さんは臨時休診で結局家まで犬と歩いて帰ってきたとのことでした。
このところ、いろいろな商品が値上げされていますが、価格を上げるより内容量を10%下げてもらったほうが当方は納得いくのですが、貴方は如何でしょうか?「100円ショップ」は105円ではなく100円がいいですね。
Posted by walt at
21:38
│Comments(2)
2007年10月17日
133) ごみがなくなる生ごみ処理機
知人の紹介で、本日ツインメッセで開催された「第5回しずおか信用金庫 ビジネスマッチング商談会」に行ってきました。特に招待券なし、無料とのことでしたので気楽に受付に行き、名刺を2枚出しました。すると、「お取引の支店名を教えてください」と質問され「ありません」と答えました。当方の取引銀行は給与振込みが都市銀行、住宅ローンが地方銀行であり、信用金庫との取引は全くありません。一度だけTOTOの当選金受け取りに行ったことがあるだけです。そして、入り口では案内の人が「支店ブースが左にありますので、まずはそちらに行ってください」と言われ、又「ありません」と回答した次第です。何かちょっと「ばつが悪い」と感じました。(「ばつが悪い」って、ふと方言ではないかと思い、ネットの辞書で検索したところ載っていましたので安心しました。)
知人が紹介してくれたものは、犬のウンチがバイオの力でなくなる機械と言うことでしたが、実際は家庭用生ごみ処理機でした。生ごみ処理機は何種類かあり、生ごみが固形肥料となるのが一般的と思っていましたがこの商品は、97%生ごみが分解されて(バイオのバクテリアが食べて)なくなってしまうものです。個体がなくなる、いわゆる気化することだろうと思いますが、当方にはどうしても理解できませんでした。実際、機器にバイオ材が入っており、その中にお弁当のご飯、焼き魚、キャベツの千切り、揚げ物を100gほど入れて10分ほど経って、そのバイオ材をかき混ぜたのですが、それらしき固体・物体が見当たりませんでした。多少残ってはいましたが、匂いもなく、ほんと驚きでした。この機器は1日あたり800gまで生ごみを処理できバイオ材がその分増えることもなく、又、通常の使用であれば、バイオ材も取り替えたり、追加することも必要ないとのことでした。
当方、どちらかと言うと疑い深い性格のため、このような生ごみがなくなってしまうということが気になります。多少何らかの物体が残れば納得するかも知れませんし、又、そんなに早い時間でなくなるのが疑問です。マジックを見るのが好きですが、見ながらタネを考えることが好きです。そんなわけで今回のこの機器は欠点がなく、その為疑わしいさが増すのですが納得せざるを得ません。マルチ的な販売方法でもなく、極端に高価ではなく、一般的な生ごみ処理機と同等な価格です。自治体の補助も得られるようです。
疑いつつも、あったら良いかなと思うことは洗脳されてしまった証拠でしょうか?
興味ある方は以下のWEBを参照ください。
株式会社東北環境: http://www.touhokukankyou.com/
知人が紹介してくれたものは、犬のウンチがバイオの力でなくなる機械と言うことでしたが、実際は家庭用生ごみ処理機でした。生ごみ処理機は何種類かあり、生ごみが固形肥料となるのが一般的と思っていましたがこの商品は、97%生ごみが分解されて(バイオのバクテリアが食べて)なくなってしまうものです。個体がなくなる、いわゆる気化することだろうと思いますが、当方にはどうしても理解できませんでした。実際、機器にバイオ材が入っており、その中にお弁当のご飯、焼き魚、キャベツの千切り、揚げ物を100gほど入れて10分ほど経って、そのバイオ材をかき混ぜたのですが、それらしき固体・物体が見当たりませんでした。多少残ってはいましたが、匂いもなく、ほんと驚きでした。この機器は1日あたり800gまで生ごみを処理できバイオ材がその分増えることもなく、又、通常の使用であれば、バイオ材も取り替えたり、追加することも必要ないとのことでした。
当方、どちらかと言うと疑い深い性格のため、このような生ごみがなくなってしまうということが気になります。多少何らかの物体が残れば納得するかも知れませんし、又、そんなに早い時間でなくなるのが疑問です。マジックを見るのが好きですが、見ながらタネを考えることが好きです。そんなわけで今回のこの機器は欠点がなく、その為疑わしいさが増すのですが納得せざるを得ません。マルチ的な販売方法でもなく、極端に高価ではなく、一般的な生ごみ処理機と同等な価格です。自治体の補助も得られるようです。
疑いつつも、あったら良いかなと思うことは洗脳されてしまった証拠でしょうか?
興味ある方は以下のWEBを参照ください。
株式会社東北環境: http://www.touhokukankyou.com/
Posted by walt at
21:25
│Comments(0)
2007年10月16日
132) メタボ市場向け機器
いまやメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を知らない人がいないほど認知された言葉となりました。又、気にしているお父さん達も多くいると思います。実際男性の場合ウエストが85cm以上は要注意と言いますが身長にもよって、ウエストは変わりますので85cmあったからと言っても何も心配することはないと思います。マスコミの報道でその点が気にかかります。
花王のヘルシアという飲料がヒットしてから、注目を浴びるようになったと記憶しています。又、来年
2008年4月から特定健診・特定保健指導の義務化があり、各保険組合はその対応に追われているのではないかと思います。実際メタボ対策がどれほど病気治療のための健康保険支出に影響するかわかりませんが、健康保険関連事業者はメタボ市場参入に期待をかけているようです。当方が加入している健康組合でも一作年前から、摂取カロリーと消費カロリーを毎日記入して、日々の体調管理をするシステムを専門業者とタイアップして行っています。又、昨年から遠隔健診(生活習慣病9のプログラムや24時間健康相談のプログラムも実施しています。
昨年からじわじわとヒットしてきた乗馬型フィットネス機器を製造販売している松下電工がメタボ市場向けに身体活動量計を発表しました。いわゆる従来型歩数計(ちなみに万歩計はヤマサ社の商標です)の高級版といった商品と思います。3軸の加速度センサを搭載したもので、この加速度センサはいわゆるショックセンサを兼ねており、又、姿勢状態を知ることが出来るためこのような機器に使用されるようになったわけです。ちなみに加速度センサはすべてのエアーバックに搭載されています。基本的には歩数をこのセンサでカウントして、又、座っているのか、寝ているのかなどの状態・運動を検出し、カロリーを計算する仕組みと推測されます。この松下電工の機器(活動量計と松下電工は呼ぶようですが)とデータを解析するソフトウェアを開発し、パソコンで日々の管理をするようです。従来の歩数計販売の家電量販店のみならず、健康組合に積極的に販路を開拓するようです。もしかしたら、来年春にお父さんがこれら運動量計測計を持って帰ってくるかも知れません。
すでに歩数計では最大大手のオムロンが数年前から、データをパソコンに取り入れる運動管理をしています。今後は歩数計を扱っているメーカーがこぞってこの運動管理サービスを付帯した機器の発売にこぎつけることと思います。もし、当方の手元にこれらの機器が入ってきたと仮定すると、二日坊主の当方ですので、辛いものがありますが、データを毎日ブログに記入していけば何とかなるかなと思った次第です。
花王のヘルシアという飲料がヒットしてから、注目を浴びるようになったと記憶しています。又、来年
2008年4月から特定健診・特定保健指導の義務化があり、各保険組合はその対応に追われているのではないかと思います。実際メタボ対策がどれほど病気治療のための健康保険支出に影響するかわかりませんが、健康保険関連事業者はメタボ市場参入に期待をかけているようです。当方が加入している健康組合でも一作年前から、摂取カロリーと消費カロリーを毎日記入して、日々の体調管理をするシステムを専門業者とタイアップして行っています。又、昨年から遠隔健診(生活習慣病9のプログラムや24時間健康相談のプログラムも実施しています。
昨年からじわじわとヒットしてきた乗馬型フィットネス機器を製造販売している松下電工がメタボ市場向けに身体活動量計を発表しました。いわゆる従来型歩数計(ちなみに万歩計はヤマサ社の商標です)の高級版といった商品と思います。3軸の加速度センサを搭載したもので、この加速度センサはいわゆるショックセンサを兼ねており、又、姿勢状態を知ることが出来るためこのような機器に使用されるようになったわけです。ちなみに加速度センサはすべてのエアーバックに搭載されています。基本的には歩数をこのセンサでカウントして、又、座っているのか、寝ているのかなどの状態・運動を検出し、カロリーを計算する仕組みと推測されます。この松下電工の機器(活動量計と松下電工は呼ぶようですが)とデータを解析するソフトウェアを開発し、パソコンで日々の管理をするようです。従来の歩数計販売の家電量販店のみならず、健康組合に積極的に販路を開拓するようです。もしかしたら、来年春にお父さんがこれら運動量計測計を持って帰ってくるかも知れません。
すでに歩数計では最大大手のオムロンが数年前から、データをパソコンに取り入れる運動管理をしています。今後は歩数計を扱っているメーカーがこぞってこの運動管理サービスを付帯した機器の発売にこぎつけることと思います。もし、当方の手元にこれらの機器が入ってきたと仮定すると、二日坊主の当方ですので、辛いものがありますが、データを毎日ブログに記入していけば何とかなるかなと思った次第です。
Posted by walt at
21:54
│Comments(0)
2007年10月15日
131) 人生銀行
「人生銀行」って、聞いたことありますか?先週「イオン銀行」が認可されましたので、セブンイレブン銀行と共にスーパーが親会社の銀行が又ひとつ増えましたが、この「人生銀行」はタカラトミー社の貯金箱です。入社3年目の遠藤女史がアイディアを出したユニークな貯金箱で、貯金を開始するときに、目標金額と期間、シナリオを選択。小型液晶ディスプレーが付いていて、順調に貯金ができれば、3畳一間からスタートした「貯金箱の住人」の人生がハッピーライフに変わっていく仕組みです。液晶に表示された「住民」の生活を見ながら、最大10万円を貯めることができます。
この貯金箱は500円硬貨を貯金するもので、昨年12月28日の発売から当初1年間の出荷計画は10万台と想定しましたが、今年6月時点で、20万台の出荷を達成したヒット商品です。遠藤女史のものづくりのコンセプトは、「面倒なことを、楽しくしたい」ということで、このユニークな商品を生み出し、貯金箱としては異例のヒットにつながったようです。
その昔、竹の節で切断し硬貨を入れる簡単な貯金箱を作ってもらい、竹を割って硬貨を取りました。急にお金が必要になった時は、定規を差込み、その上に乗ったコインを静かに引き出したことが思い浮かばれます。その後、陶器の貯金箱や、ブリキの貯金箱、プラスチックの貯金箱などを使用した記憶があります。そして、大学生の時は1リットルのコーラのビンにコインを入れたりしました。その後いつの間にか貯金箱は忘れ去られてしまいました。
しかし、当方妻は、何時からかわかりませんが500円貯金をしており、「100枚貯まったので銀行に持っていってくれ」と頼まれたことがあります。硬貨を100枚銀行に持っていき、現金自動預け払い機(ATM)に入れたところ機械がストップしてしまいました。係員が来て後ろから、コインを出してきたのですが、「100枚なかったらどうしよう?クレームを言っても証拠がないな」とかふと考えてしまいました。幸い100枚あったのですが、又、機会がストップすると困るため、20枚ずつ5回に分けて入金処理しました。今思えば、こっけいです。全く機械に入れる意味のないことをやってしまいました。
そんなこともあり、それから妻が引き続き500円貯金をしているかどうか解かりませんが、もし、継続しているのであれば、この人生銀行を買ってあげようかなと思った次第です。
それにしても貯金箱もエレクトロニクスになったとは驚きですし、いろいろなことが商品化できるのだなとつくづく思いました。
人生銀行: http://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei-ginko/index.html
この貯金箱は500円硬貨を貯金するもので、昨年12月28日の発売から当初1年間の出荷計画は10万台と想定しましたが、今年6月時点で、20万台の出荷を達成したヒット商品です。遠藤女史のものづくりのコンセプトは、「面倒なことを、楽しくしたい」ということで、このユニークな商品を生み出し、貯金箱としては異例のヒットにつながったようです。
その昔、竹の節で切断し硬貨を入れる簡単な貯金箱を作ってもらい、竹を割って硬貨を取りました。急にお金が必要になった時は、定規を差込み、その上に乗ったコインを静かに引き出したことが思い浮かばれます。その後、陶器の貯金箱や、ブリキの貯金箱、プラスチックの貯金箱などを使用した記憶があります。そして、大学生の時は1リットルのコーラのビンにコインを入れたりしました。その後いつの間にか貯金箱は忘れ去られてしまいました。
しかし、当方妻は、何時からかわかりませんが500円貯金をしており、「100枚貯まったので銀行に持っていってくれ」と頼まれたことがあります。硬貨を100枚銀行に持っていき、現金自動預け払い機(ATM)に入れたところ機械がストップしてしまいました。係員が来て後ろから、コインを出してきたのですが、「100枚なかったらどうしよう?クレームを言っても証拠がないな」とかふと考えてしまいました。幸い100枚あったのですが、又、機会がストップすると困るため、20枚ずつ5回に分けて入金処理しました。今思えば、こっけいです。全く機械に入れる意味のないことをやってしまいました。
そんなこともあり、それから妻が引き続き500円貯金をしているかどうか解かりませんが、もし、継続しているのであれば、この人生銀行を買ってあげようかなと思った次第です。
それにしても貯金箱もエレクトロニクスになったとは驚きですし、いろいろなことが商品化できるのだなとつくづく思いました。
人生銀行: http://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei-ginko/index.html
Posted by walt at
21:36
│Comments(2)
2007年10月14日
130)放置茶園の手入れ
昨年よりお茶の仲間と始めた「放置茶園再生プロジェクト」の茶園の手入れにいってきました。ゴールデンウィークに茶摘(手摘み)をして20Kg程の製茶に仕上がりました。その後6月に一旦枝を落として整枝しました。それから暑い夏の日になった為、作業は保留しておりました。お茶園を見に行った仲間が、「雑草に覆われていて大変なことになっている」いうことで、雑草取りを兼ねて秋の整枝を行いました。お茶の木は秋の整枝をするため予定通りの手入れということになります。
場所は藤枝の蓮花寺公園の一角で、ハイキングコースのわきにあります。お茶園に訪れた参加者は絶句。なんと茶畑が雑草、羊歯で覆われ何処にあるかわからない状態でした。ほんと目を見張る状況でした。雑草と羊歯を取り除き、その後お茶を整枝する機械で刈り取りました。実は、放置されていた茶園のため、あのかまぼこ型のお茶の木にはなっておらず少しづつ手入れして、今後きれいなかまぼこ型にする予定です。9時半から作業を開始して、14時までかかってしまいました。勿論昼食は摂りましたが....。
今年は初めての茶摘で、手摘みしたため(素人のこともあり)生葉で55kgしか採れませんでした。そのため、来年は100kg程は収穫したいと思っていますので、お茶摘みのやり方も考えなければなりません。今回肥料も撒いてきましたが来年の春までに、追加肥料撒き、手入れもまだまだしなければならないと思っています。
来月11月2日から4日までグランシップで「世界お茶まつり」が開催されます。前回はツインメッセとグランシップで開催されましたが、今回は1箇所でおこなわれます。内容も濃くなっているとのことですので、茶のことをもっと知る上でも是非皆さんも予定していただければと思います。
Before


場所は藤枝の蓮花寺公園の一角で、ハイキングコースのわきにあります。お茶園に訪れた参加者は絶句。なんと茶畑が雑草、羊歯で覆われ何処にあるかわからない状態でした。ほんと目を見張る状況でした。雑草と羊歯を取り除き、その後お茶を整枝する機械で刈り取りました。実は、放置されていた茶園のため、あのかまぼこ型のお茶の木にはなっておらず少しづつ手入れして、今後きれいなかまぼこ型にする予定です。9時半から作業を開始して、14時までかかってしまいました。勿論昼食は摂りましたが....。
今年は初めての茶摘で、手摘みしたため(素人のこともあり)生葉で55kgしか採れませんでした。そのため、来年は100kg程は収穫したいと思っていますので、お茶摘みのやり方も考えなければなりません。今回肥料も撒いてきましたが来年の春までに、追加肥料撒き、手入れもまだまだしなければならないと思っています。
来月11月2日から4日までグランシップで「世界お茶まつり」が開催されます。前回はツインメッセとグランシップで開催されましたが、今回は1箇所でおこなわれます。内容も濃くなっているとのことですので、茶のことをもっと知る上でも是非皆さんも予定していただければと思います。
Before


Posted by walt at
22:17
│Comments(0)
2007年10月14日
129) 芦家 いちぞう (Part 2)
今日久しぶりに、草薙の「芦家いちぞう」に行ってきました。久しぶりと言っても8月にブログに書いて以来3回目ですが.....。静岡県立大学の社会人ビジネス講座が本日あり、その仲間10人と懇親会を兼ねて行ったというわけです。料理、3,000円、飲み放題2時間2,000円計5,000円のコースでお願いしました。飲み放題は以前と同じく、生ビールがキリンのプレミアム、瓶ビールはエビスでした。又、焼酎、日本酒の種類もあり満足できるものでした。
実は、昨日、静岡のとあるお店に会社の同僚と行ったのですが、その店は個室風の店で、雰囲気も良く、料理も多少凝っており、以前妻が友だちと行ってお勧めだと言うことで行ったわけです。雰囲気、料理は合格点でしたが、ホールスタッフの対応がいまいちでした。事前にお勧め料理を頼んでおいたのですが、「何か?」と聞いてみても答えられず、焼酎のボトルを頼んだのですが、麦焼酎なのか、芋焼酎なのかわからず、同僚はお湯割を頼み、当方は緑茶割を頼んだのですが出てきたコップが取っ手付のもので、どう見てもお湯割のものです。そのスタッフに「氷と緑茶で割るグラスがこの取っ手付のグラスですか?当方としては納得できないのですが?」と聞いたのですが、答えられず、「聞いてくれ!」と依頼した次第です。他のスタッフが他のグラスに氷を入れて持ってきました。
そのようなこともあり、そのお店にはがっかりしたため、「いちぞう」の店長に。そのような経験をしたので、スタッフの教育には充分気をつけた方が良い旨伝えました。勿論「いちぞう」のスタッフではそのようなことはありませんでしたが....。飲食業では接客というサービスが重点の一つです。店主はその点も充分わきまえているとは思うのですが、できていないお店があります。多分、現場を見ていないからではないかと思います。10月22日より東京ビックサイトで「東京ビジネスサミット」という、企業マッチングの展示会があります。東京六本木の「カシータ」というレストランのオーナーの高橋氏の講演があります。カシータは接客のすばらしさで有名なお店です。当方が一度行って見たいお店であり、その
オーナーの講演があるため、その展示会に行ってみたいと思っています。
「いちぞう」は今日も込んでいました。2ヶ月経過しましたが滑り出しは上々ではないでしょうか?Googleで「芦家いちぞう」と検索したところ、以前書いた当方のブログとホットペッパーの記事がヒットしたため、なぜか恥ずかしいやらうれしいやらといった複雑な感覚です。当方はちょっとお気に入りのお店のため今後も応援したいと思っております。

実は、昨日、静岡のとあるお店に会社の同僚と行ったのですが、その店は個室風の店で、雰囲気も良く、料理も多少凝っており、以前妻が友だちと行ってお勧めだと言うことで行ったわけです。雰囲気、料理は合格点でしたが、ホールスタッフの対応がいまいちでした。事前にお勧め料理を頼んでおいたのですが、「何か?」と聞いてみても答えられず、焼酎のボトルを頼んだのですが、麦焼酎なのか、芋焼酎なのかわからず、同僚はお湯割を頼み、当方は緑茶割を頼んだのですが出てきたコップが取っ手付のもので、どう見てもお湯割のものです。そのスタッフに「氷と緑茶で割るグラスがこの取っ手付のグラスですか?当方としては納得できないのですが?」と聞いたのですが、答えられず、「聞いてくれ!」と依頼した次第です。他のスタッフが他のグラスに氷を入れて持ってきました。
そのようなこともあり、そのお店にはがっかりしたため、「いちぞう」の店長に。そのような経験をしたので、スタッフの教育には充分気をつけた方が良い旨伝えました。勿論「いちぞう」のスタッフではそのようなことはありませんでしたが....。飲食業では接客というサービスが重点の一つです。店主はその点も充分わきまえているとは思うのですが、できていないお店があります。多分、現場を見ていないからではないかと思います。10月22日より東京ビックサイトで「東京ビジネスサミット」という、企業マッチングの展示会があります。東京六本木の「カシータ」というレストランのオーナーの高橋氏の講演があります。カシータは接客のすばらしさで有名なお店です。当方が一度行って見たいお店であり、その
オーナーの講演があるため、その展示会に行ってみたいと思っています。
「いちぞう」は今日も込んでいました。2ヶ月経過しましたが滑り出しは上々ではないでしょうか?Googleで「芦家いちぞう」と検索したところ、以前書いた当方のブログとホットペッパーの記事がヒットしたため、なぜか恥ずかしいやらうれしいやらといった複雑な感覚です。当方はちょっとお気に入りのお店のため今後も応援したいと思っております。

Posted by walt at
00:03
│Comments(0)
2007年10月12日
128) 日本の動漫(アニメ・漫画)人気
毎年日中関係、日韓関係、日米関係に関し、アンケートが行われその結果が発表されます。今年の結果はうる覚えですが「日中関係が良くなった」と思っている人の割合が増えたのではないかと記憶しています。毎年繰り広げる日中関係の悪化の記事にはうんざりしていますが、昨年前安部首相が首相になってすぐに中国を訪問し、世論調査では関係が良くなりつつあると報じられました。ただ、根底には多くのことが蓄積されており、いつ又爆発するかわからないといった状況であることは確かです。そのような中、日経BPオンラインの遠藤 誉氏のコラムに中国での日本のアニメ・漫画が支持を得ていて、若者を中心に文化の受け入れのみならず日本人観まで変わりつつあることを読み、日本のみならず、中国も時代が変わりつつあるのだと感心しました。遠藤氏は中国で一番有名な検索サイト「百度(パイドゥ)」にある投稿型の検索サイト「百度知道(バイドゥ・ズーダオ)」に掲載された面白い問答を参考に、そのコラムを書いています。
当方の認識では、日本の漫画・アニメは中国で人気があり、あらゆるものが出版されており(合法・非合法を問わず)、いわゆる漫画に登場するキャラクターのコスプレも人気があり、全国大会まで開催されるほど熱中しているくらいです。それも、一部(一部と言っても日本のファン以上の人数と思います)のファンの間だけと思っておりました。しかし、中国の有名な大学である清華大学には「日本漫画研究会」があり、かなりの会員数と実績を持っているとのことも最近知りました。
中国の漫画事情は「中国の動漫は幼児向けで幼稚な内容だけど、それだけじゃなく、いつも党に忠誠を誓い、人民に忠誠を誓わせるものばかり(コラムより引用)」のようで、日本の漫画は「ストーリー展開がよく、中国の普通の人達と共通する思考が反映されていて、尚且つ登場人物の内面の葛藤を正直に描いている。そのうえで、主人公は常にどんな困難にも打ち勝ち、最後に成功を遂げる。そんなストーリー展開が私たち視聴者の心を揺さぶり、励ましてくれる」ようです。
1981年に鉄腕アトムが初めて中国に紹介され、1990年代になるとバスケットボールをテーマにした「スラムダンク」に男の子達は夢中になり、女の子達は「セーラームーン」に魅了されたようです。現在アメリカのバスケットボールNBAに4名の中国人プレーヤーが参加していますが、彼らは「スラムダンク」を読んで育ったようです。中国リーグで活躍するプレーヤーもこの漫画に影響され、バスケに夢中になったとのことです。
日中関係は、歴史的な問題を抱えつつ、経済という名の基で協力してきました。お金で解決してきたと言っても過言ではありません。しかし、これからは、漫画という手段を通じてでも、もっと日本を解かってもらい誤解の生じない日中関係ができればと思います。
当方の認識では、日本の漫画・アニメは中国で人気があり、あらゆるものが出版されており(合法・非合法を問わず)、いわゆる漫画に登場するキャラクターのコスプレも人気があり、全国大会まで開催されるほど熱中しているくらいです。それも、一部(一部と言っても日本のファン以上の人数と思います)のファンの間だけと思っておりました。しかし、中国の有名な大学である清華大学には「日本漫画研究会」があり、かなりの会員数と実績を持っているとのことも最近知りました。
中国の漫画事情は「中国の動漫は幼児向けで幼稚な内容だけど、それだけじゃなく、いつも党に忠誠を誓い、人民に忠誠を誓わせるものばかり(コラムより引用)」のようで、日本の漫画は「ストーリー展開がよく、中国の普通の人達と共通する思考が反映されていて、尚且つ登場人物の内面の葛藤を正直に描いている。そのうえで、主人公は常にどんな困難にも打ち勝ち、最後に成功を遂げる。そんなストーリー展開が私たち視聴者の心を揺さぶり、励ましてくれる」ようです。
1981年に鉄腕アトムが初めて中国に紹介され、1990年代になるとバスケットボールをテーマにした「スラムダンク」に男の子達は夢中になり、女の子達は「セーラームーン」に魅了されたようです。現在アメリカのバスケットボールNBAに4名の中国人プレーヤーが参加していますが、彼らは「スラムダンク」を読んで育ったようです。中国リーグで活躍するプレーヤーもこの漫画に影響され、バスケに夢中になったとのことです。
日中関係は、歴史的な問題を抱えつつ、経済という名の基で協力してきました。お金で解決してきたと言っても過言ではありません。しかし、これからは、漫画という手段を通じてでも、もっと日本を解かってもらい誤解の生じない日中関係ができればと思います。
Posted by walt at
23:56
│Comments(0)