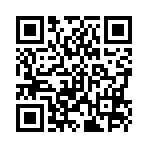2008年07月30日
416) ホタルがもたらす環境破壊
本日の日経ビジネスオンラインで、ちょっと気になる記事に目が留まりました。写真家・作家でも
ある宮嶋 康彦氏の「『ホタルで町おこし』の大きな間違い。『環境ブーム』が引き起こした取り返し
のつかない自然破壊」という記事です。毎年6月になると蛍鑑賞をしている当方にとって、とても
気になるタイトルでした。
数年前より6月の初旬になると中伊豆の天城湯ヶ島蛍まつりに行っています。「出合橋」からたくさん
のホタルが舞うのを見ることができるからです。ここのホタルは地元で幼虫から飼育して蛹になる頃
川の砂地にもっていくとのことでした。雨が降った翌日の暑い日に沢山出ると聞いていました。
前日に湯ヶ島の旅館に泊まって見に行ったこともあります。今年は親戚の叔母さんから、「家の前の
小川にもホタルがいて、毎年たくさん飛んでいるよ」と聞き、伊豆に行くのは止め、6月上旬に見に
行きましたが、「今年は5月下旬が最盛期だった」と聞き、数匹のホタルしか観ることができません
でした。そこは静岡市の某所で飼育している蛍を放つというわけではないので野生のホタルということ
になります。当方子供のころから虫好きでしたが、ホタルを観る環境にはいませんでした。東京で働い
ていた頃、目白の椿山荘(現フォーシーズンホテル)で「蛍の夕べ」というイベントがあり、食事を
して、庭園に放たれた蛍を見たことがあります。今思えば、蛍を購入して庭に放していたのだろうと思
われます。その後、蛍を見る機会がなく、伊豆に行くようになった次第です。
宮嶋氏のレポートでは、ふるさと創生の事業として、各地に「蛍の里」が作られたそうですが、ほとん
どが失敗しているとのこと。それは、そもそも生息しているはずのない地域で、源氏ボタルが飛んで
いるケースがあり、すべては、他県の生息地から移入した結果だったそうです。その多くは、生態調査
をせず、とりあえずホタルを飛ばそう、という素人考えが根底にあり、ホタルの里、と謳えば人が集まる
と勘違いしていたようです。安易に人を呼ぶための「ふるさと作り」は間違いだらけ。とりあえずホタルを
飛ばせば地域が活性するという間違った発想が、生態無視のホタルビジネスを生んだようです。
近ごろでは、とりあえずホタルの光を楽しんでもらいたい、と、商店や料亭、各種のイベントなどでホタ
ルが放されるようです。世の中はいつもいやしの対象を求めているようですが、違う場所から持ち込ま
れたホタルは、求愛活動のために光っているのではなく、ストレスによる光を見て本当に癒されるのか
と問題を提起しています。同じ蛍でも、 西日本と東日本で光り方に大きな違いがあるようです。西の
源氏ボタルは2秒間隔で明滅を繰り返すが、東日本では4秒と長い。生態の違いはないが、環境による
光り方が異なるのではないかといわれているようです。
又、ホタルの世界に重大な問題が起こっている用です。本来ホタルは「カワニナ」という巻貝を食べて
育ちますが、コモチカワツボというニュージーランド産の巻貝(体長5ミリ)が全国的に増えているそう
です。「この貝で育ったホタルは光が非常に弱い、雌雄がコミュニケーションをするために発光する
わけですから、光が弱ければ交尾に至らない。よって、ホタルが全滅してしまう恐れがある」そうです。
ホタルの里など、人工的に個体数を増やそうとしている生息地では、幼虫のエサになるカワニナが
不足し、近隣から、あるいは遠方からカワニナを移入することになります。そのときに、1匹でも、コモチ
カワツボが混入していた場合には、ホタルの絶滅につながる危険性があるというわけです。コモチカワ
ツボは雌雄同体。1個体がオスとメスの生殖器官を持っているようです。外見ではカワニナと見分ける
ことができないほど似ているため、善かれと行うエサの移入で、とんでもない結果を招くことになるよう
です。
もうじき8月になりますので、ホタルの観賞時期は過ぎていますが、環境問題を考え、ホタルの住む
清流を人工的に作っても、それがある意味での環境破壊につながっているとは思ってもみませんでし
た。世の中って、うまくいかないものですね。
日経ビジネスオンライの記事:http://cmad.nikkeibp.co.jp/?4_25814_470745_125
ある宮嶋 康彦氏の「『ホタルで町おこし』の大きな間違い。『環境ブーム』が引き起こした取り返し
のつかない自然破壊」という記事です。毎年6月になると蛍鑑賞をしている当方にとって、とても
気になるタイトルでした。
数年前より6月の初旬になると中伊豆の天城湯ヶ島蛍まつりに行っています。「出合橋」からたくさん
のホタルが舞うのを見ることができるからです。ここのホタルは地元で幼虫から飼育して蛹になる頃
川の砂地にもっていくとのことでした。雨が降った翌日の暑い日に沢山出ると聞いていました。
前日に湯ヶ島の旅館に泊まって見に行ったこともあります。今年は親戚の叔母さんから、「家の前の
小川にもホタルがいて、毎年たくさん飛んでいるよ」と聞き、伊豆に行くのは止め、6月上旬に見に
行きましたが、「今年は5月下旬が最盛期だった」と聞き、数匹のホタルしか観ることができません
でした。そこは静岡市の某所で飼育している蛍を放つというわけではないので野生のホタルということ
になります。当方子供のころから虫好きでしたが、ホタルを観る環境にはいませんでした。東京で働い
ていた頃、目白の椿山荘(現フォーシーズンホテル)で「蛍の夕べ」というイベントがあり、食事を
して、庭園に放たれた蛍を見たことがあります。今思えば、蛍を購入して庭に放していたのだろうと思
われます。その後、蛍を見る機会がなく、伊豆に行くようになった次第です。
宮嶋氏のレポートでは、ふるさと創生の事業として、各地に「蛍の里」が作られたそうですが、ほとん
どが失敗しているとのこと。それは、そもそも生息しているはずのない地域で、源氏ボタルが飛んで
いるケースがあり、すべては、他県の生息地から移入した結果だったそうです。その多くは、生態調査
をせず、とりあえずホタルを飛ばそう、という素人考えが根底にあり、ホタルの里、と謳えば人が集まる
と勘違いしていたようです。安易に人を呼ぶための「ふるさと作り」は間違いだらけ。とりあえずホタルを
飛ばせば地域が活性するという間違った発想が、生態無視のホタルビジネスを生んだようです。
近ごろでは、とりあえずホタルの光を楽しんでもらいたい、と、商店や料亭、各種のイベントなどでホタ
ルが放されるようです。世の中はいつもいやしの対象を求めているようですが、違う場所から持ち込ま
れたホタルは、求愛活動のために光っているのではなく、ストレスによる光を見て本当に癒されるのか
と問題を提起しています。同じ蛍でも、 西日本と東日本で光り方に大きな違いがあるようです。西の
源氏ボタルは2秒間隔で明滅を繰り返すが、東日本では4秒と長い。生態の違いはないが、環境による
光り方が異なるのではないかといわれているようです。
又、ホタルの世界に重大な問題が起こっている用です。本来ホタルは「カワニナ」という巻貝を食べて
育ちますが、コモチカワツボというニュージーランド産の巻貝(体長5ミリ)が全国的に増えているそう
です。「この貝で育ったホタルは光が非常に弱い、雌雄がコミュニケーションをするために発光する
わけですから、光が弱ければ交尾に至らない。よって、ホタルが全滅してしまう恐れがある」そうです。
ホタルの里など、人工的に個体数を増やそうとしている生息地では、幼虫のエサになるカワニナが
不足し、近隣から、あるいは遠方からカワニナを移入することになります。そのときに、1匹でも、コモチ
カワツボが混入していた場合には、ホタルの絶滅につながる危険性があるというわけです。コモチカワ
ツボは雌雄同体。1個体がオスとメスの生殖器官を持っているようです。外見ではカワニナと見分ける
ことができないほど似ているため、善かれと行うエサの移入で、とんでもない結果を招くことになるよう
です。
もうじき8月になりますので、ホタルの観賞時期は過ぎていますが、環境問題を考え、ホタルの住む
清流を人工的に作っても、それがある意味での環境破壊につながっているとは思ってもみませんでし
た。世の中って、うまくいかないものですね。
日経ビジネスオンライの記事:http://cmad.nikkeibp.co.jp/?4_25814_470745_125
Posted by walt at
21:18
│Comments(1)