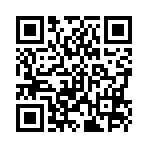2008年12月22日
561)スポンサー
昨日、トヨタカップ、クラブワールドカップ2008の決勝戦がありヨーロッパチャンピョンの
英国マンチェスターユナイテッドが南米代表のエクアドル リガ・デ・キトを1-0で破り、
予想通り優勝し、500万ドルの賞金とクラブ世界1の栄誉を手に入れました。アジア代表の
ガンバ大阪も昨年の浦和レッズ同様3位となり250万ドルの賞金を得ました。マンチェスター
ユナイテッドのユニフォームの胸のスポンサーが「AIG」であったことが気になりました。
このところ、モータースポーツをはじめ各種スポーツの廃部、休部が相次いでいます。先週
アイスホッケーの名門西武(前身はコクド)が今季限りで休部となることを発表しました。
又、アメリカンフットボールのオンワードも今季限りだそうです。モータースポーツにおい
てはホンダがF撤退を表明し、富士重工、スズキはそろって世界ラリー選手権参戦の休止を
発表しました。ホンダの場合、F1では年間500億~600億円の経費がかかり、その経費削減に
今回の撤退となったようです。富士重工、スズキの場合は経費削減効果は数十億円だそうです。
日産の場合、J1の横浜マリノスの親会社ですが、中村俊輔の獲得に予算が取れず、スコット
ランドリーグ終了後に延期されたようです。昨年のアメリカのサブプライムローンから始まり
今年9月のリーマンショックから世界同時不況となり、その影響がスポーツにまで及んでいます。
ちなみに日本サッカー協会の今年度の予算がいくらか知っていますか?何と178億円です。
同じスポーツでも、北京オリンピックで金メダルを取った女子ソフトボールは、来年度の予算
が500万円となり物議をかもしだしました。結局1億円ほどになったようですが....その差は
何でしょうか?アマチアのスポーツはほとんどの場合、企業のクラブが進化したものです。
運営は企業のスポンサー頼りということです。企業の経営状況によってスポーツクラブの存続
が左右されるという図式です。スポーツ振興といいますが、結局国民に人気があり、お金が
集まるスポーツだけが残るということでしょうか?とある見識人は日本のスポーツが企業中心
であることが問題だと指摘していますが、では、どのような組織であれば理想なのでしょうか?
今年のJリーグは鹿島アントラーズが2連覇しました。その結果スポンサー料が来年は20%アップ
すると言われています。これも経済の原理からすれば当たり前のことです。ただ、スポンサーが
あっての事です。来年は、今年のスポンサーが継続できるのか、それとも新しいスポンサーが
見つかるのかまだわからないでしょう。清水エスパルスのホームスタジアム日本平が来年から
命名権の販売で「アウトソーシングスタジアム日本平」となります。アウトソーシング社が命名権を
購入しました。アウトソーシング社は駿河区にある派遣会社です。派遣会社は派遣社員がなくなれ
ば売り上げがなくなります。今回の製造業を中心とした派遣社員の契約継続の中止による業績の
影響はないものでしょうか?すでに、静岡市もエスパルスも命名権の販売による収入の使い道を
予算化しています。今後何もないことを祈るばかりです。
さて、2009年のスポーツ界もどうなることでしょうか?
英国マンチェスターユナイテッドが南米代表のエクアドル リガ・デ・キトを1-0で破り、
予想通り優勝し、500万ドルの賞金とクラブ世界1の栄誉を手に入れました。アジア代表の
ガンバ大阪も昨年の浦和レッズ同様3位となり250万ドルの賞金を得ました。マンチェスター
ユナイテッドのユニフォームの胸のスポンサーが「AIG」であったことが気になりました。
このところ、モータースポーツをはじめ各種スポーツの廃部、休部が相次いでいます。先週
アイスホッケーの名門西武(前身はコクド)が今季限りで休部となることを発表しました。
又、アメリカンフットボールのオンワードも今季限りだそうです。モータースポーツにおい
てはホンダがF撤退を表明し、富士重工、スズキはそろって世界ラリー選手権参戦の休止を
発表しました。ホンダの場合、F1では年間500億~600億円の経費がかかり、その経費削減に
今回の撤退となったようです。富士重工、スズキの場合は経費削減効果は数十億円だそうです。
日産の場合、J1の横浜マリノスの親会社ですが、中村俊輔の獲得に予算が取れず、スコット
ランドリーグ終了後に延期されたようです。昨年のアメリカのサブプライムローンから始まり
今年9月のリーマンショックから世界同時不況となり、その影響がスポーツにまで及んでいます。
ちなみに日本サッカー協会の今年度の予算がいくらか知っていますか?何と178億円です。
同じスポーツでも、北京オリンピックで金メダルを取った女子ソフトボールは、来年度の予算
が500万円となり物議をかもしだしました。結局1億円ほどになったようですが....その差は
何でしょうか?アマチアのスポーツはほとんどの場合、企業のクラブが進化したものです。
運営は企業のスポンサー頼りということです。企業の経営状況によってスポーツクラブの存続
が左右されるという図式です。スポーツ振興といいますが、結局国民に人気があり、お金が
集まるスポーツだけが残るということでしょうか?とある見識人は日本のスポーツが企業中心
であることが問題だと指摘していますが、では、どのような組織であれば理想なのでしょうか?
今年のJリーグは鹿島アントラーズが2連覇しました。その結果スポンサー料が来年は20%アップ
すると言われています。これも経済の原理からすれば当たり前のことです。ただ、スポンサーが
あっての事です。来年は、今年のスポンサーが継続できるのか、それとも新しいスポンサーが
見つかるのかまだわからないでしょう。清水エスパルスのホームスタジアム日本平が来年から
命名権の販売で「アウトソーシングスタジアム日本平」となります。アウトソーシング社が命名権を
購入しました。アウトソーシング社は駿河区にある派遣会社です。派遣会社は派遣社員がなくなれ
ば売り上げがなくなります。今回の製造業を中心とした派遣社員の契約継続の中止による業績の
影響はないものでしょうか?すでに、静岡市もエスパルスも命名権の販売による収入の使い道を
予算化しています。今後何もないことを祈るばかりです。
さて、2009年のスポーツ界もどうなることでしょうか?
Posted by walt at
21:12
│Comments(0)
2008年12月22日
560) 有機栽培理論の講義
このブログでもお茶のことやミカン切りのことなどを書きましたが、実はカテゴリーで「50代から
の痛快ライフ」があり、そこでも家庭菜園のことを書いています。そんなわけで当方農業関連にも
興味を持っているわけであります。今日、株式会社ジャパンビオファーム小祝社長の有機に関
する貴重な話を聞くことが出来ました。
本日とある団体の農業に関する講座があり、そのゲスト講師として小祝氏が講演したものです。
40名ほどの生産者、流通業者が集まりました。小祝先生は10年以上前から「有機栽培の科学」
にせまり、単なる経験や勘ではなく、データに基づいた施肥設計を確立し、有機栽培でも無機栽培
以上の立派な作物ができることを実証してきた方です。現在では農協、大学、外食産業などから
講演依頼を受け、年間300回以上の講演を全国でおこなうという非常に多忙な方でもあります。
本日の講義を聴いて、今までの有機の考え方が根本的に違っていたことをつくづく感じました。
小祝先生の話し方は何処となく武田鉄也さんに似ていると思ったのは私だけだったでしょうか?
一般的に言うと有機栽培は無農薬で化学肥料を使用せず、近隣農地からの農薬の飛散もなく
決められた期間に条件内の値以下であることと理解していましたが、小祝先生の理論は、勿論、
無農薬で、化学肥料は使用しないことですが、①正しい土壌分析、②正しい施肥設計③正しい堆肥
の作り方 の知識を身につけ、安全でおいしい作物を作ることというものです。
特に土壌管理によって、適切な肥料を入れ、植物の成長の理論に合わせ高品質で多収穫生産シス
テムを確立するということでした。それは、無農薬であるから害虫が集まるのではなく悪い施肥の
仕方によって作物の抵抗力がなくなり害虫が集まるということ実証したものです。
又、作物の栄養素の1951年と2001年の成分分析の比較表には驚かされました。例えばほうれん草
の場合100g中のビタミンAは1951年では8,000㎎であったのが2001年では1/10の700㎎に
なっており、鉄分は13㎎が2㎎とのことでした。ほうれん草の場合鉄分は根っこの部分の赤いところ
に大く含まれているそうですが、昔のほうれん草はその部分が赤かったのですが、今のほうれん草
は赤くないようです。言われてみて、「そういえば昔のほうれん草は根っこの部分が赤く、食べた記憶
があった」と思い出した次第です。みかんではもっと驚くべき数字でした。ビタミンAが1951年では
2,000㎎あったのが2001年では14㎎しかなかったということです。現在のミカンを142個食べなけれ
ば同じビタミンAの栄養素が摂取でき無いということです。生産性の向上による品種改良によって栄養
素の含有量が減少したということです。
当方農業生産者ではありませんが、小祝理論を基に作物の収穫量が大幅に増えたという生産者が
多くいること、安全・安心な作物でおいしく栄養素の豊富な作物は我々の生命活動に大きな影響がある
こと、予防医学にも関係することなどを学び、現在趣味の菜園ではありますが、非常に考えさせられる
ものでした。
生きていくうえには食物は必要です。我々消費者の作物の価値を再考することによって、本来の作物
のおいしさ、栄養素を摂り入れることができるのではないでしょうか?
ふらのオーガニックアカデミー:http://www.organicacademy.org/
の痛快ライフ」があり、そこでも家庭菜園のことを書いています。そんなわけで当方農業関連にも
興味を持っているわけであります。今日、株式会社ジャパンビオファーム小祝社長の有機に関
する貴重な話を聞くことが出来ました。
本日とある団体の農業に関する講座があり、そのゲスト講師として小祝氏が講演したものです。
40名ほどの生産者、流通業者が集まりました。小祝先生は10年以上前から「有機栽培の科学」
にせまり、単なる経験や勘ではなく、データに基づいた施肥設計を確立し、有機栽培でも無機栽培
以上の立派な作物ができることを実証してきた方です。現在では農協、大学、外食産業などから
講演依頼を受け、年間300回以上の講演を全国でおこなうという非常に多忙な方でもあります。
本日の講義を聴いて、今までの有機の考え方が根本的に違っていたことをつくづく感じました。
小祝先生の話し方は何処となく武田鉄也さんに似ていると思ったのは私だけだったでしょうか?
一般的に言うと有機栽培は無農薬で化学肥料を使用せず、近隣農地からの農薬の飛散もなく
決められた期間に条件内の値以下であることと理解していましたが、小祝先生の理論は、勿論、
無農薬で、化学肥料は使用しないことですが、①正しい土壌分析、②正しい施肥設計③正しい堆肥
の作り方 の知識を身につけ、安全でおいしい作物を作ることというものです。
特に土壌管理によって、適切な肥料を入れ、植物の成長の理論に合わせ高品質で多収穫生産シス
テムを確立するということでした。それは、無農薬であるから害虫が集まるのではなく悪い施肥の
仕方によって作物の抵抗力がなくなり害虫が集まるということ実証したものです。
又、作物の栄養素の1951年と2001年の成分分析の比較表には驚かされました。例えばほうれん草
の場合100g中のビタミンAは1951年では8,000㎎であったのが2001年では1/10の700㎎に
なっており、鉄分は13㎎が2㎎とのことでした。ほうれん草の場合鉄分は根っこの部分の赤いところ
に大く含まれているそうですが、昔のほうれん草はその部分が赤かったのですが、今のほうれん草
は赤くないようです。言われてみて、「そういえば昔のほうれん草は根っこの部分が赤く、食べた記憶
があった」と思い出した次第です。みかんではもっと驚くべき数字でした。ビタミンAが1951年では
2,000㎎あったのが2001年では14㎎しかなかったということです。現在のミカンを142個食べなけれ
ば同じビタミンAの栄養素が摂取でき無いということです。生産性の向上による品種改良によって栄養
素の含有量が減少したということです。
当方農業生産者ではありませんが、小祝理論を基に作物の収穫量が大幅に増えたという生産者が
多くいること、安全・安心な作物でおいしく栄養素の豊富な作物は我々の生命活動に大きな影響がある
こと、予防医学にも関係することなどを学び、現在趣味の菜園ではありますが、非常に考えさせられる
ものでした。
生きていくうえには食物は必要です。我々消費者の作物の価値を再考することによって、本来の作物
のおいしさ、栄養素を摂り入れることができるのではないでしょうか?
ふらのオーガニックアカデミー:http://www.organicacademy.org/
Posted by walt at
00:29
│Comments(2)