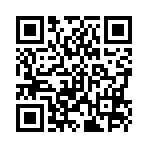2008年06月19日
375) フェアトレード
「本当のコーヒーの価格を知っていますか?」と、日経BPネット「日経レストラン」の吹田恵子記者の
問いからコラムが始まりました。ドキュメンタリー映画「おいしいコーヒーの真実」が、東京・渋谷の
アップリンクなどで現在公開されており、アップリンクでは、週末は20代、30代の若い観客を集めて
満席が続き、急遽レイトショー上映も決定したほどの盛況だそうです。一般の消費者だけでなく飲食
店の関係者であっても意外と知らないであろうコーヒーを取り巻く世界の現実を教えてくれるそうです。
「2008年6月18日今、目の前に1杯330円のコーヒーがあるとする。そのうちコーヒー農家が
コーヒー豆の代金として手にする金額が3~9円だと聞いたら、多くの人は驚くに違いない。どうして
そんなに安いのか、では残りの金額は一体どこへ? そもそもコーヒー豆の価格はいつ、誰が、どこ
で、どのように決めているのだろうか?」と投げかけています。コーヒー豆は生産農家から消費者に
届くまで、非常に複雑なルートをたどります。そしてコーヒーの価格は、ニューヨークとロンドンの
商品取引所において、農家の取り分にはまったく関係なく決められるため、生産現場は貧窮にあえい
でいるという事実が明らかにされています。映画はコーヒー発祥の地であるエチオピア連邦民主共和
国の農民たちが貧窮にあえぐ現状を映し出しており、「これでは子供を学校に行かせることもできない」
と嘆く家族、「コーヒーは儲からないから、チャット(ヨーロッパの多くや米国では違法薬物に指定される
植物)の生産に切り替える」という青年が登場するそうです。又、大手コーヒーチェーンに豆を提供して
いる地区では飢餓が発生し、子供たちが栄養失調に苦しんでいるとのことです。
こうした状況を打破するため、複雑な流通ルートを簡略化し、農民が適切な価格で直接焙煎業者に
コーヒー豆を売れるように同国オロミア州のコーヒー農協連合会代表タデッセ・メスケラ氏が奮闘して
いるようです。メスケラ氏のこのような活動の原点は、日本の農協で氏が受けた2カ月間の共同運営
の研修に始まり、ここで中間業者や輸入業者に支払われている多額の金を、農業者が受け取ることが
できる協同組合というシステムの存在に深い感銘を受け、それを実現すべく、1999年故郷のエチオピ
アにコーヒー農協連合会を設立したそうです。
今日の日経産業新聞に「フェアトレード」のことが掲載されていました。「フェアトレード」とは、途上国の
生産者から農産物を適正な価格で購入し、持続可能な生活を支援することです。日本でも少しづつ
増えてきていますが、国際比較をすると、国民一人当たりの購入金額は先進国の中では最低であり、
年間購入金額が8円にも満たないそうです。トップはスイスであり3,000円以上購入しているそうです。
日本では国際的な認証マーク付きの商品を扱う企業が50社に達し、イオンやスターバックスジャパン
も入っているようです。フィリッピンのバナナを支援する会社が東京にあり、昨年2,300トンを輸入した
そうです。その9割が生協向けとのことで、趣旨に生協が賛同してくれたようです。生協といえば、
今回の中国餃子問題でクローズアップされましたが、このような支援もしていることをマスコミは取り
上げてもらいたいものです。
このフェアトレードは以前からも言われてきましたが、大手企業の参入が増えていることは良いこと
ですね。これからは、コーヒーを外で飲むならスターバックス、バナナを買うなら生協にして、少しでも
途上国支援をしませんか?
問いからコラムが始まりました。ドキュメンタリー映画「おいしいコーヒーの真実」が、東京・渋谷の
アップリンクなどで現在公開されており、アップリンクでは、週末は20代、30代の若い観客を集めて
満席が続き、急遽レイトショー上映も決定したほどの盛況だそうです。一般の消費者だけでなく飲食
店の関係者であっても意外と知らないであろうコーヒーを取り巻く世界の現実を教えてくれるそうです。
「2008年6月18日今、目の前に1杯330円のコーヒーがあるとする。そのうちコーヒー農家が
コーヒー豆の代金として手にする金額が3~9円だと聞いたら、多くの人は驚くに違いない。どうして
そんなに安いのか、では残りの金額は一体どこへ? そもそもコーヒー豆の価格はいつ、誰が、どこ
で、どのように決めているのだろうか?」と投げかけています。コーヒー豆は生産農家から消費者に
届くまで、非常に複雑なルートをたどります。そしてコーヒーの価格は、ニューヨークとロンドンの
商品取引所において、農家の取り分にはまったく関係なく決められるため、生産現場は貧窮にあえい
でいるという事実が明らかにされています。映画はコーヒー発祥の地であるエチオピア連邦民主共和
国の農民たちが貧窮にあえぐ現状を映し出しており、「これでは子供を学校に行かせることもできない」
と嘆く家族、「コーヒーは儲からないから、チャット(ヨーロッパの多くや米国では違法薬物に指定される
植物)の生産に切り替える」という青年が登場するそうです。又、大手コーヒーチェーンに豆を提供して
いる地区では飢餓が発生し、子供たちが栄養失調に苦しんでいるとのことです。
こうした状況を打破するため、複雑な流通ルートを簡略化し、農民が適切な価格で直接焙煎業者に
コーヒー豆を売れるように同国オロミア州のコーヒー農協連合会代表タデッセ・メスケラ氏が奮闘して
いるようです。メスケラ氏のこのような活動の原点は、日本の農協で氏が受けた2カ月間の共同運営
の研修に始まり、ここで中間業者や輸入業者に支払われている多額の金を、農業者が受け取ることが
できる協同組合というシステムの存在に深い感銘を受け、それを実現すべく、1999年故郷のエチオピ
アにコーヒー農協連合会を設立したそうです。
今日の日経産業新聞に「フェアトレード」のことが掲載されていました。「フェアトレード」とは、途上国の
生産者から農産物を適正な価格で購入し、持続可能な生活を支援することです。日本でも少しづつ
増えてきていますが、国際比較をすると、国民一人当たりの購入金額は先進国の中では最低であり、
年間購入金額が8円にも満たないそうです。トップはスイスであり3,000円以上購入しているそうです。
日本では国際的な認証マーク付きの商品を扱う企業が50社に達し、イオンやスターバックスジャパン
も入っているようです。フィリッピンのバナナを支援する会社が東京にあり、昨年2,300トンを輸入した
そうです。その9割が生協向けとのことで、趣旨に生協が賛同してくれたようです。生協といえば、
今回の中国餃子問題でクローズアップされましたが、このような支援もしていることをマスコミは取り
上げてもらいたいものです。
このフェアトレードは以前からも言われてきましたが、大手企業の参入が増えていることは良いこと
ですね。これからは、コーヒーを外で飲むならスターバックス、バナナを買うなら生協にして、少しでも
途上国支援をしませんか?
Posted by walt at
21:50
│Comments(4)