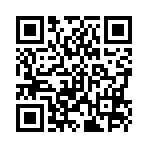2007年11月04日
151) 世界お茶まつり
11/2から始まった世界お茶まつりも本日終了しました。大道芸も本日で終了でしたよね。今回は2つのイベントが重なりましたので、静岡のホテルは何処も満員だったに違いありません。こんなことめったにありませんよね。当方昨日行ってきましたが、午後からだったため、あまり見ることが出きませんでした。
昨日、3日は普通の土曜日とばかり思っており、祝日であることをころっと忘れていました。9時から英会話学校へ行き、その後先週胃カメラを飲んだとき、ついでにやってもらった血液検査の結果を聞くために(少し、のどが痛く咳も出るため)お医者さんに行く予定を作り、そのため、グランシップの世界お茶まつりは午後からのスケジュールとしたわけです。それが、学校へ行ったら閉まっており、掲示板の休日案内には11/3は休講となっていました。そして、お医者さんへ行ったのですが、こちらも閉まっていました。なんと間抜けなことか。予定が変わってしまいましたが、仲間に13:00の待ち合わせをしていたため、変更することもできませんでした。
世界お茶まつりの会場はグランシップ全館を使用して催されました。3年に1度開催され、今回で3回目です。今回は、台湾、韓国からのお客様が目立ちました。台湾、韓国からの出展、インドネシア、ケニヤからの出展もあり国際色豊かでしたので、世界お茶まつりと呼ぶにふさわしいものと思われます。ただ、この催しの目的が広くお茶のことを知ってもらうことのようですので、海外からビジネスを目的に出展された会社の方々には、少し物足りないものであったのではないかと思います。世界お茶Expoのようなタイトルとして展示会形式として、土日は一般公開するような企画でも良いような気がします。お祭りは単なるフェスティバルであり、商談目的には程遠いと思います。日本の各産地のブースも多くありましたが、多くは煎茶であり、産地の特徴が出にくいものです。今回飲んだお茶がおいしいと言って、その場では購入したとしても一般消費者が産地を指定して再購入するまでは難しいのではないでしょうか?
コーヒー、紅茶では産地がブランドとなっています。そして、そのブランドを好み購入します。しかし、日本茶の場合まだそこまではなっていませんし、なれるかどうかわかりません。地域ブランドの必要性は言うまでもありませんがどのような特徴を出すか、そして消費者が判断できるような味にできるかが問題となります。それを考えると日本茶の難しさが改めて感じさせられます。
世界お茶まつりを通じて、生産者、流通業者、行政が今一度、静岡茶の普及の妨げとなるものをピックアップしそれを排除することに協力して欲しいと思います。サムスン経済研究所のミン氏も言っていたことに共通しますが.....
昨日、3日は普通の土曜日とばかり思っており、祝日であることをころっと忘れていました。9時から英会話学校へ行き、その後先週胃カメラを飲んだとき、ついでにやってもらった血液検査の結果を聞くために(少し、のどが痛く咳も出るため)お医者さんに行く予定を作り、そのため、グランシップの世界お茶まつりは午後からのスケジュールとしたわけです。それが、学校へ行ったら閉まっており、掲示板の休日案内には11/3は休講となっていました。そして、お医者さんへ行ったのですが、こちらも閉まっていました。なんと間抜けなことか。予定が変わってしまいましたが、仲間に13:00の待ち合わせをしていたため、変更することもできませんでした。
世界お茶まつりの会場はグランシップ全館を使用して催されました。3年に1度開催され、今回で3回目です。今回は、台湾、韓国からのお客様が目立ちました。台湾、韓国からの出展、インドネシア、ケニヤからの出展もあり国際色豊かでしたので、世界お茶まつりと呼ぶにふさわしいものと思われます。ただ、この催しの目的が広くお茶のことを知ってもらうことのようですので、海外からビジネスを目的に出展された会社の方々には、少し物足りないものであったのではないかと思います。世界お茶Expoのようなタイトルとして展示会形式として、土日は一般公開するような企画でも良いような気がします。お祭りは単なるフェスティバルであり、商談目的には程遠いと思います。日本の各産地のブースも多くありましたが、多くは煎茶であり、産地の特徴が出にくいものです。今回飲んだお茶がおいしいと言って、その場では購入したとしても一般消費者が産地を指定して再購入するまでは難しいのではないでしょうか?
コーヒー、紅茶では産地がブランドとなっています。そして、そのブランドを好み購入します。しかし、日本茶の場合まだそこまではなっていませんし、なれるかどうかわかりません。地域ブランドの必要性は言うまでもありませんがどのような特徴を出すか、そして消費者が判断できるような味にできるかが問題となります。それを考えると日本茶の難しさが改めて感じさせられます。
世界お茶まつりを通じて、生産者、流通業者、行政が今一度、静岡茶の普及の妨げとなるものをピックアップしそれを排除することに協力して欲しいと思います。サムスン経済研究所のミン氏も言っていたことに共通しますが.....
Posted by walt at
22:51
│Comments(0)