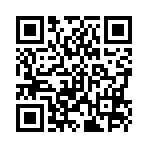2008年03月24日
289)死者との別れ
「自宅に帰らなくなった遺体」と題して雑誌『SOGI』編集長でもある碑文谷 創氏が日経
BPオンラインにコラムを書いていました。現在自宅で死亡する人は12%にすぎず、多くな
ったのは病院や老人施設での死亡であり、そのまま葬儀会館の霊安室や保冷庫に保管される
ケースが多くなったようです。ご遺体が魚屋、肉と同じように扱われていることになります。
従来90年代までは8割が自宅で亡くなっており、病院等で死亡した方の遺体は、病院で死後
の処置を施された後、自宅に送られ、安置され、遺体の周囲には枕飾りが施され、その前で
檀那寺の僧侶が枕経をあげてくれました。そして遺体は、一晩は家の布団に寝かされ、家族が
その周りを取り囲み、別れを惜しみ、そして翌日、家族が見守る中で納棺され、式場に送られ
ました。しかし2000年を過ぎたあたりから、この慣習が大きく変化したようです。
当方もこのところ、通夜、葬儀に参列する機会が増えました。隣組の高齢化、親戚の叔父・
叔母、同僚の父母などです。やはりお通夜を自宅で行うケースが極端に減ってきました。
葬儀会館・斎場で行われることが多くなりました。住宅事情の変化により、又、お通夜に
来られる交通機関の問題(駐車場の確保)等が原因だと思っていました。実際、参列者として
も、斎場で行われるお通夜のほうが気兼ねをしないことが事実なのですが....
しかし、碑文谷氏は住宅事情ではないと言っています。都心ではマンション等の共同住宅に
住む人が以前から多かったこと。地方の大きな邸宅でも遺体を自宅に戻さなくなったことが
挙げられるようです。その主な理由としては、自宅をかたずけることが面倒であること、
自宅に安置すれば、僧侶も来るし、親族も集まり家族の生活が制限されることが嫌だという
理由もあるようです。家事の負担が女性にかかる度合いが大きいのが実情で、亡くなる前の
介護や看病の負担もより多く女性にかかっており、その遺族の女性が自宅に遺体が戻るのを
拒み始めたのが理由のようです。そして、葬儀会館で葬式をするのが「普通」のことになった
ようです。
その気持ちは分かりますが、果たしてそれでよいのでしょうか?何でも便利になった現在に
おいて、「死」を見つめることなく、生活の中に死者を戻し、そしてその生活の中で死者と
別れる空間を失ってもよいのでしょうか?斎場に安置する場合、遺族は斎場に泊まるようです
が.... 自宅に遺体を安置し、死者と共にした家族、特に子どもや孫が、死者と触れて別れる
ことは、命をつなぐ意味からも大切なことではないでしょうか?その大切さを知っていたからこそ、
いままでは自宅で看取ることを理想とし、それが叶わなくても、いったんは遺体を自宅に戻し、
一晩は家族で過ごしたのではないでしょうか?
昨日、荒川沖駅で8人が死傷する事件が起きました。犯人は「誰でも良いから人を殺したかった」
と言っていたようです。生きることの尊さ、死に対する認識があまりにもおかしくなっています。
「人を殺したい、でも自分は殺されたくない」と思っているに違いありません。又、亡くなった
方の両親がインタビューに答えていましたが、淡々と答えていました。それを見て「どうして
そんな態度で答えられるのか?」と思った次第です。
「あなたはどこで死にたいですか?そして、どこでどのように家族と別れ、送られたいですか?」
と私も問いたい気持ちになりました。
BPオンラインにコラムを書いていました。現在自宅で死亡する人は12%にすぎず、多くな
ったのは病院や老人施設での死亡であり、そのまま葬儀会館の霊安室や保冷庫に保管される
ケースが多くなったようです。ご遺体が魚屋、肉と同じように扱われていることになります。
従来90年代までは8割が自宅で亡くなっており、病院等で死亡した方の遺体は、病院で死後
の処置を施された後、自宅に送られ、安置され、遺体の周囲には枕飾りが施され、その前で
檀那寺の僧侶が枕経をあげてくれました。そして遺体は、一晩は家の布団に寝かされ、家族が
その周りを取り囲み、別れを惜しみ、そして翌日、家族が見守る中で納棺され、式場に送られ
ました。しかし2000年を過ぎたあたりから、この慣習が大きく変化したようです。
当方もこのところ、通夜、葬儀に参列する機会が増えました。隣組の高齢化、親戚の叔父・
叔母、同僚の父母などです。やはりお通夜を自宅で行うケースが極端に減ってきました。
葬儀会館・斎場で行われることが多くなりました。住宅事情の変化により、又、お通夜に
来られる交通機関の問題(駐車場の確保)等が原因だと思っていました。実際、参列者として
も、斎場で行われるお通夜のほうが気兼ねをしないことが事実なのですが....
しかし、碑文谷氏は住宅事情ではないと言っています。都心ではマンション等の共同住宅に
住む人が以前から多かったこと。地方の大きな邸宅でも遺体を自宅に戻さなくなったことが
挙げられるようです。その主な理由としては、自宅をかたずけることが面倒であること、
自宅に安置すれば、僧侶も来るし、親族も集まり家族の生活が制限されることが嫌だという
理由もあるようです。家事の負担が女性にかかる度合いが大きいのが実情で、亡くなる前の
介護や看病の負担もより多く女性にかかっており、その遺族の女性が自宅に遺体が戻るのを
拒み始めたのが理由のようです。そして、葬儀会館で葬式をするのが「普通」のことになった
ようです。
その気持ちは分かりますが、果たしてそれでよいのでしょうか?何でも便利になった現在に
おいて、「死」を見つめることなく、生活の中に死者を戻し、そしてその生活の中で死者と
別れる空間を失ってもよいのでしょうか?斎場に安置する場合、遺族は斎場に泊まるようです
が.... 自宅に遺体を安置し、死者と共にした家族、特に子どもや孫が、死者と触れて別れる
ことは、命をつなぐ意味からも大切なことではないでしょうか?その大切さを知っていたからこそ、
いままでは自宅で看取ることを理想とし、それが叶わなくても、いったんは遺体を自宅に戻し、
一晩は家族で過ごしたのではないでしょうか?
昨日、荒川沖駅で8人が死傷する事件が起きました。犯人は「誰でも良いから人を殺したかった」
と言っていたようです。生きることの尊さ、死に対する認識があまりにもおかしくなっています。
「人を殺したい、でも自分は殺されたくない」と思っているに違いありません。又、亡くなった
方の両親がインタビューに答えていましたが、淡々と答えていました。それを見て「どうして
そんな態度で答えられるのか?」と思った次第です。
「あなたはどこで死にたいですか?そして、どこでどのように家族と別れ、送られたいですか?」
と私も問いたい気持ちになりました。
Posted by walt at 21:57│Comments(0)