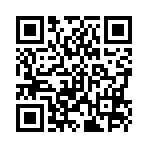2010年02月07日
945) 自然それとも異常
毎朝晩、犬の散歩をしています。朝は決まって巴川の江尻小学校付近の右岸、左岸を歩きます。
毎日巴川を見ていますが、このところちょっと気になることがあります。それは、鵜の存在です。
昨年巴川にも鵜が来るようになったのだ。水がきれいになり、魚が多くなったからだろうと思って
いました。現に町内会でハゼ釣り大会が行われたり、ルアーでシーバスを釣っている人を見か
けたこともあります。ボラも良く見かけます。鵜も数える程であり、水中にもぐり魚を撮る姿を観て
いたのですが、昨日は、その鵜の数に驚きました。何と40羽もいるのです。いつの間にかこんな
に増えたのだろうかと思いました。川面に漂う鵜を見ると、ここはあの巴川かと思うほどでした。
一匹が飛び立つと他の鵜も飛び立ち、群れをつくっているようにも思えました。
巴川は清水の中心をゆっくりと流れています。以前は折戸湾の貯木場から丸太が筏を組んで製材
所まで運ばれ、巴川の風物詩となっていました。その昔江戸時代は巴川が駿府への海上航路となっ
ており、駿府城の石垣も巴川を通って運ばれたようです。当方が子供のころは鮒釣りをしましたが
その後、生活用水の垂れ流し、製紙会社からの廃液で川は汚くなり、魚が住める川では無くなった
事もありましたが、環境整備により川がきれいになり、魚が増える現在に至っています。魚が増え
鳥が飛来することは自然の営みであり、良いことだとは思うのですが、このところ鵜の被害が多い
事が報道されています。折角育てて放流したアユを鵜が食べてしまうと言うことです。各地の漁協
はこの現象に頭を抱えているそうです。
日本各地では鵜飼いが観光名物となっています。以前はその程度のことしか知りませんでしたが、
これ程近くで目にすることとなり、ちょっとインターネットで調べてみました。日本ではウミウ、カワウ、
ヒメウ、チシマウガラス之4種類が生息するそうです。ウミウ、カワウが体調80cm程でヒメウは50cm
程で小型のようです。カワウは河川部や湖沼に生息し、数十から数百羽単位で行動するとのこと
ですので巴川にいるのはカワウであろうと推測されます。一夫一妻で、枯れ枝などを利用して樹上
や鉄塔などに巣を作り、卵は約1ヶ月程度で孵化し、40-50日で巣立つそうです。1羽で1日500gの
魚を食べると言われ、現在6万羽以上に増えたと推測されています。鵜による漁業の被害が増大し、
2007年3月、環境省は鳥獣保護法に基づく狩猟対象にする方針を決め、2007年6月1日以降には
狩猟鳥となり、狩猟可能な期間と地域であれば特別な許可なく捕獲できるようになったそうです。
只、鵜の肉にも羽毛にもたいした利用価値は無く、狩猟鳥になったとてハンターが積極的に本種を
狩猟するかどうかには疑わしいものがあり、狩猟による個体数の減少を期待するのは見当違いで
あるとの見解もあるようです。
巴川のカワウですが昨日観た40匹はほんの一部かもしれません。1日500gの魚を食べると言うこと
はこの40匹で1日20kg食べる事になります。折角増えた巴川の魚もいつの間にか食べ尽くされる
のではないかと心配してしまいます。この状況は自然が帰ってきたことでしょうか?当方はどうしても
異常としか思えないのですが.....
毎日巴川を見ていますが、このところちょっと気になることがあります。それは、鵜の存在です。
昨年巴川にも鵜が来るようになったのだ。水がきれいになり、魚が多くなったからだろうと思って
いました。現に町内会でハゼ釣り大会が行われたり、ルアーでシーバスを釣っている人を見か
けたこともあります。ボラも良く見かけます。鵜も数える程であり、水中にもぐり魚を撮る姿を観て
いたのですが、昨日は、その鵜の数に驚きました。何と40羽もいるのです。いつの間にかこんな
に増えたのだろうかと思いました。川面に漂う鵜を見ると、ここはあの巴川かと思うほどでした。
一匹が飛び立つと他の鵜も飛び立ち、群れをつくっているようにも思えました。
巴川は清水の中心をゆっくりと流れています。以前は折戸湾の貯木場から丸太が筏を組んで製材
所まで運ばれ、巴川の風物詩となっていました。その昔江戸時代は巴川が駿府への海上航路となっ
ており、駿府城の石垣も巴川を通って運ばれたようです。当方が子供のころは鮒釣りをしましたが
その後、生活用水の垂れ流し、製紙会社からの廃液で川は汚くなり、魚が住める川では無くなった
事もありましたが、環境整備により川がきれいになり、魚が増える現在に至っています。魚が増え
鳥が飛来することは自然の営みであり、良いことだとは思うのですが、このところ鵜の被害が多い
事が報道されています。折角育てて放流したアユを鵜が食べてしまうと言うことです。各地の漁協
はこの現象に頭を抱えているそうです。
日本各地では鵜飼いが観光名物となっています。以前はその程度のことしか知りませんでしたが、
これ程近くで目にすることとなり、ちょっとインターネットで調べてみました。日本ではウミウ、カワウ、
ヒメウ、チシマウガラス之4種類が生息するそうです。ウミウ、カワウが体調80cm程でヒメウは50cm
程で小型のようです。カワウは河川部や湖沼に生息し、数十から数百羽単位で行動するとのこと
ですので巴川にいるのはカワウであろうと推測されます。一夫一妻で、枯れ枝などを利用して樹上
や鉄塔などに巣を作り、卵は約1ヶ月程度で孵化し、40-50日で巣立つそうです。1羽で1日500gの
魚を食べると言われ、現在6万羽以上に増えたと推測されています。鵜による漁業の被害が増大し、
2007年3月、環境省は鳥獣保護法に基づく狩猟対象にする方針を決め、2007年6月1日以降には
狩猟鳥となり、狩猟可能な期間と地域であれば特別な許可なく捕獲できるようになったそうです。
只、鵜の肉にも羽毛にもたいした利用価値は無く、狩猟鳥になったとてハンターが積極的に本種を
狩猟するかどうかには疑わしいものがあり、狩猟による個体数の減少を期待するのは見当違いで
あるとの見解もあるようです。
巴川のカワウですが昨日観た40匹はほんの一部かもしれません。1日500gの魚を食べると言うこと
はこの40匹で1日20kg食べる事になります。折角増えた巴川の魚もいつの間にか食べ尽くされる
のではないかと心配してしまいます。この状況は自然が帰ってきたことでしょうか?当方はどうしても
異常としか思えないのですが.....
Posted by walt at 00:45│Comments(0)