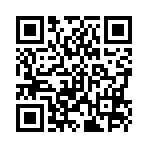2010年01月28日
938) 読売新聞特集記事 -メガチャイナ-
一昨日1/26の大安吉日にコミュニティカフェ「まちカフェSHIMIZU」をオープンさせました。多くの
方々にオープニングイベント参加して頂き、誠にうれしく思います。これから多くの人に来てもらう
ための仕組み作りをしっかりしていきたいと思います。オープニングイベントがあったため、1/26の
このブログはお休みとなってしまいました。そして、昨日はしばらくぶりに、ワイン講座で知り合っ
た仲間と集まり、新年会という名目でワインを飲みに行きました。清水銀座戸田書店の露地を入った
所に「ビアホールOUCHI」さんがあります。以前酒屋さんでしたが、今ではビールとワインのお店に
なっています。落ち着いた雰囲気でワインが楽しめます。昨日は4名で行きましたが、ビールを注文
せず、最初からワインを注文しました。まずは白ワインのシャルドネ、そのあと、メルロー、カベルネ
と進み4本目も赤ワインを頼んでしまいました。結局、火曜日の平日に1人1本づつ飲んでしまったわけ
です。でも不思議と今朝は何ともありませんでした。というわけで2日連続でブログをお休みしてしま
ったわけです。
ワインと言えば、本日の読売新聞朝刊一面に「メガチャイナ」という特集が組まれていました。それは
フランスのワインの名産地であるボルドーで28ヘクタールのブドウ畑を持つ蔵元「シャトー・ラトゥー
ル・ラギャン」が中国山東省の不動産会社に2億5千万円で買収されたという話から始まっていました。
「中国の乗っ取りだ」と中傷する半面、「聞きに瀕したボルドー産ワインの救世主です」と歓迎する
意見もあったようです。当方知らなかったのですが、ボルドー地区では醸造業者1万軒のうち毎日1軒
がつぶれ、フランス国民のワインの消費量が健康志向の影響もあって、50年前の半分に減ったそう
です。一方中国ではワイン消費量が急増し、10年前の倍となり、フランスからの中国本土への輸出額
は10年前の20倍となり、対日輸出との差を縮めているそうですボルドーの独立ワイン生産者連盟の
ムーディ会長は「中国人が年に1本ワインを飲んでくれるのが夢だ。そうなれば、危機は去る」としてい
ます。
中国の豊かな生活に目覚めた13憶の胃袋が飲み込むのはワインにとどまらず、家庭の肉の消費量
は30年間で2~3倍に増え、それに伴い、肉の味や安全性を高めるため、餌を残飯から配合飼料に
替える動きが加速し、その結果、穀物消費も何倍も増えているようです。大手商社・丸紅によると、
中国の大豆需要は世界の年生産量の4分の1の約5,600万トンとなり、1990年代に始まった輸入は
今や約4,000万トンに達し、世界の貿易取引量の半分を占めるそうです。現在の中国のトウモロコシ
年生産量は世界の2割(約1,500万トン)で自給の範囲内だそうですが、いずれ輸入が始まり、例えば
中国を干ばつが襲えば価格は急騰し、1,600万トンを輸入する日本も含め大パニックになるそうです。
ワイン、穀物だけでなく海産物特にマグロの消費量も増えています。このままいけば、食材が全て中国
へ行く可能性もあるわけです。さて、飽食の時代となった日本、このままでよいのでしょうか?
方々にオープニングイベント参加して頂き、誠にうれしく思います。これから多くの人に来てもらう
ための仕組み作りをしっかりしていきたいと思います。オープニングイベントがあったため、1/26の
このブログはお休みとなってしまいました。そして、昨日はしばらくぶりに、ワイン講座で知り合っ
た仲間と集まり、新年会という名目でワインを飲みに行きました。清水銀座戸田書店の露地を入った
所に「ビアホールOUCHI」さんがあります。以前酒屋さんでしたが、今ではビールとワインのお店に
なっています。落ち着いた雰囲気でワインが楽しめます。昨日は4名で行きましたが、ビールを注文
せず、最初からワインを注文しました。まずは白ワインのシャルドネ、そのあと、メルロー、カベルネ
と進み4本目も赤ワインを頼んでしまいました。結局、火曜日の平日に1人1本づつ飲んでしまったわけ
です。でも不思議と今朝は何ともありませんでした。というわけで2日連続でブログをお休みしてしま
ったわけです。
ワインと言えば、本日の読売新聞朝刊一面に「メガチャイナ」という特集が組まれていました。それは
フランスのワインの名産地であるボルドーで28ヘクタールのブドウ畑を持つ蔵元「シャトー・ラトゥー
ル・ラギャン」が中国山東省の不動産会社に2億5千万円で買収されたという話から始まっていました。
「中国の乗っ取りだ」と中傷する半面、「聞きに瀕したボルドー産ワインの救世主です」と歓迎する
意見もあったようです。当方知らなかったのですが、ボルドー地区では醸造業者1万軒のうち毎日1軒
がつぶれ、フランス国民のワインの消費量が健康志向の影響もあって、50年前の半分に減ったそう
です。一方中国ではワイン消費量が急増し、10年前の倍となり、フランスからの中国本土への輸出額
は10年前の20倍となり、対日輸出との差を縮めているそうですボルドーの独立ワイン生産者連盟の
ムーディ会長は「中国人が年に1本ワインを飲んでくれるのが夢だ。そうなれば、危機は去る」としてい
ます。
中国の豊かな生活に目覚めた13憶の胃袋が飲み込むのはワインにとどまらず、家庭の肉の消費量
は30年間で2~3倍に増え、それに伴い、肉の味や安全性を高めるため、餌を残飯から配合飼料に
替える動きが加速し、その結果、穀物消費も何倍も増えているようです。大手商社・丸紅によると、
中国の大豆需要は世界の年生産量の4分の1の約5,600万トンとなり、1990年代に始まった輸入は
今や約4,000万トンに達し、世界の貿易取引量の半分を占めるそうです。現在の中国のトウモロコシ
年生産量は世界の2割(約1,500万トン)で自給の範囲内だそうですが、いずれ輸入が始まり、例えば
中国を干ばつが襲えば価格は急騰し、1,600万トンを輸入する日本も含め大パニックになるそうです。
ワイン、穀物だけでなく海産物特にマグロの消費量も増えています。このままいけば、食材が全て中国
へ行く可能性もあるわけです。さて、飽食の時代となった日本、このままでよいのでしょうか?
Posted by walt at 22:52│Comments(0)