2008年09月05日
453) 苦手な部下、苦手な上司
ビジネスパーソンでは一生付いて回る職場での上司と部下の関係。退職した後もOB会が組織されて
いれば、元上司には気を遣ってしまう関係。良いか悪いか判断に困りますが、組織を離れれば友人
感覚で良いと思うのですが、まだ、まだ日本では先輩風をふかす人が多いようすね。その点、アメリカ
では名前を呼んで親近感を持たせますね。
日経ビジネスオンラインに2回に分けて「ビジネスパーソンの本音」として、苦手な部下、苦手な上司に
ついてのアンケート調査結果が掲載されていました。ビジネスパーソンの貴方であれば、「苦手な部下
苦手な上司はいない」と言い切れる人は少ないのではないでしょうか?部下を持っている人に、苦手な
部下がいるかどうか聞いた結果、「いる」と答えた人は65%でいて、「苦手な上司がいる」と答えた人は
67%いて、ほぼ同じ数値になっとのこと。「名ばかり上司」といわれる問題上司がいる一方で、どこの
職場も何かとやっかいな部下も存在するといったことになります。部下が上司を問題視するように、上司
も部下を問題視しているそうです。苦手な部下がいると思う理由の上位4つは、「言い訳をする」、
「言われたことしかせず積極性がない」、「人の意見や話を聞かない」、「できないのに自信過剰」だった
そうです。又、苦手な上司がいると思う理由の上位4つは、「指導力がない」、「人の話を聞かない」、
「気分屋、感情的」、「意見交換ができない」だったそうです。 そして、その対処法として苦手な部下に
対しては、「とことん向き合って指導する」と「部署内で協力して被害を少なくする」の2つが中心で、何と
かして指導しようとする上司と、諦めて周りでフォローする上司に分かれたようです。苦手な上司に対し
ては、「受け流すようにしている」、「極力、接触をしないようにしている」が多く、この結果から苦手と
思える上司の問題点を改善することが、いかに難しいかがわかり、多くの人は諦め、極力被害が及ば
ないよう、「気にしない」「近づかない」という方法を取っている寂しい結果となったようです。
上司の部下に対する具体的な指導法では、「とにかくコミュニケーションの場を作り、とことん話し合う」
というものが多かったようです。上司から積極的に声をかけることは今も昔も大切だが、最近は特に
部下から話かけてくる機会が少ないと感じている上司が多いようだ。と上司は言っていますが、部下は
上司を「気にしない」「近づかない」と考えているのですから、全くかみ合うはずがありません。部下から
は近づきたくないのですから、部下から話しかけてくるはずがありません。又、お互いが「人の話を聞か
ない」と思っているのですから、コミュニケーションが取れるはずがありません。人間関係でも、「あの人
が嫌い、あの人とは合わない」と思った瞬間、先方も「自分のことが嫌い、合わない」と思うはずです。
よって、上司たるもの自分から積極的に部下に話しかけなければなりません。コミュニケーションが取
れないのを部下のせいにしている上司が多いのではないでしょうか?給料を部下より多くもらっている
のですから、もっと気を遣い部署が円滑になるよう努めるのも上司の役目(仕事)のはずです。
今から20年ほど前、当方が30歳頃、人の話を聞かない、強情で良くしゃべる上司がいました。良く
飲みにいきましたのでコミュニケーションは取れていたと思います。かなり、お小言はもらい怒られまし
たが、リタイアした現在でも付き合っています。当時は、酔って家に帰ったときは「○○のバカヤロー」と
よく叫び、妻から翌朝指摘されたものです。そんな上司でしたが、今は何もあとくされがなく、逆に昔話
に花が咲きます。只、当時の同僚と「あのような上司にはならないようにしようね」と言っていたのです
が、その立場になると、昔のことは忘れてしまったのか、それとも、そのような雰囲気にさせる会社なの
か分かりませんが、同じような上司になってしまっていることが気にかかります。勿論昔ほど物分りが
悪いことはありませんが、環境によって同化してしまうのかと思うと残念でなりません。多分、上司、
部下のそれぞれの言い分は、これからも永遠に続くことだとは思いますが、内容が低次元になっていく
ように危惧されます。話す行為が少なくなっているため、口語で言いたいことを伝える能力が低くなって
いることに起因すると思っています。余計な心配をしてもしょうがないのですが、世の中移り変わって
いっても、その時代にあったやり方が肯定されれば、それがスタンダードとなり、何も問題が発生しない
ことになります。よって、なすがままになると思って良いことでしょうか?これって打算的ですかねー?
まずは、みんなの心がけ、このような部下、上司にならないよう自分自身の振る舞いを気にしましょう
ね。
いれば、元上司には気を遣ってしまう関係。良いか悪いか判断に困りますが、組織を離れれば友人
感覚で良いと思うのですが、まだ、まだ日本では先輩風をふかす人が多いようすね。その点、アメリカ
では名前を呼んで親近感を持たせますね。
日経ビジネスオンラインに2回に分けて「ビジネスパーソンの本音」として、苦手な部下、苦手な上司に
ついてのアンケート調査結果が掲載されていました。ビジネスパーソンの貴方であれば、「苦手な部下
苦手な上司はいない」と言い切れる人は少ないのではないでしょうか?部下を持っている人に、苦手な
部下がいるかどうか聞いた結果、「いる」と答えた人は65%でいて、「苦手な上司がいる」と答えた人は
67%いて、ほぼ同じ数値になっとのこと。「名ばかり上司」といわれる問題上司がいる一方で、どこの
職場も何かとやっかいな部下も存在するといったことになります。部下が上司を問題視するように、上司
も部下を問題視しているそうです。苦手な部下がいると思う理由の上位4つは、「言い訳をする」、
「言われたことしかせず積極性がない」、「人の意見や話を聞かない」、「できないのに自信過剰」だった
そうです。又、苦手な上司がいると思う理由の上位4つは、「指導力がない」、「人の話を聞かない」、
「気分屋、感情的」、「意見交換ができない」だったそうです。 そして、その対処法として苦手な部下に
対しては、「とことん向き合って指導する」と「部署内で協力して被害を少なくする」の2つが中心で、何と
かして指導しようとする上司と、諦めて周りでフォローする上司に分かれたようです。苦手な上司に対し
ては、「受け流すようにしている」、「極力、接触をしないようにしている」が多く、この結果から苦手と
思える上司の問題点を改善することが、いかに難しいかがわかり、多くの人は諦め、極力被害が及ば
ないよう、「気にしない」「近づかない」という方法を取っている寂しい結果となったようです。
上司の部下に対する具体的な指導法では、「とにかくコミュニケーションの場を作り、とことん話し合う」
というものが多かったようです。上司から積極的に声をかけることは今も昔も大切だが、最近は特に
部下から話かけてくる機会が少ないと感じている上司が多いようだ。と上司は言っていますが、部下は
上司を「気にしない」「近づかない」と考えているのですから、全くかみ合うはずがありません。部下から
は近づきたくないのですから、部下から話しかけてくるはずがありません。又、お互いが「人の話を聞か
ない」と思っているのですから、コミュニケーションが取れるはずがありません。人間関係でも、「あの人
が嫌い、あの人とは合わない」と思った瞬間、先方も「自分のことが嫌い、合わない」と思うはずです。
よって、上司たるもの自分から積極的に部下に話しかけなければなりません。コミュニケーションが取
れないのを部下のせいにしている上司が多いのではないでしょうか?給料を部下より多くもらっている
のですから、もっと気を遣い部署が円滑になるよう努めるのも上司の役目(仕事)のはずです。
今から20年ほど前、当方が30歳頃、人の話を聞かない、強情で良くしゃべる上司がいました。良く
飲みにいきましたのでコミュニケーションは取れていたと思います。かなり、お小言はもらい怒られまし
たが、リタイアした現在でも付き合っています。当時は、酔って家に帰ったときは「○○のバカヤロー」と
よく叫び、妻から翌朝指摘されたものです。そんな上司でしたが、今は何もあとくされがなく、逆に昔話
に花が咲きます。只、当時の同僚と「あのような上司にはならないようにしようね」と言っていたのです
が、その立場になると、昔のことは忘れてしまったのか、それとも、そのような雰囲気にさせる会社なの
か分かりませんが、同じような上司になってしまっていることが気にかかります。勿論昔ほど物分りが
悪いことはありませんが、環境によって同化してしまうのかと思うと残念でなりません。多分、上司、
部下のそれぞれの言い分は、これからも永遠に続くことだとは思いますが、内容が低次元になっていく
ように危惧されます。話す行為が少なくなっているため、口語で言いたいことを伝える能力が低くなって
いることに起因すると思っています。余計な心配をしてもしょうがないのですが、世の中移り変わって
いっても、その時代にあったやり方が肯定されれば、それがスタンダードとなり、何も問題が発生しない
ことになります。よって、なすがままになると思って良いことでしょうか?これって打算的ですかねー?
まずは、みんなの心がけ、このような部下、上司にならないよう自分自身の振る舞いを気にしましょう
ね。
Posted by walt at 23:16│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|

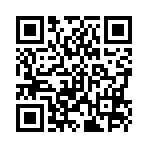


書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。