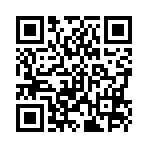2008年08月19日
436) サンマは目黒に限る?
暦の上では立秋(今年は8/7だったそうです)が過ぎました。太陽が黄経135度の点を通過する
瞬間を立秋と言うそうです。残暑見舞いの時期となったということです。まだまだ、暑い日が
続きますが、なんとなく秋の気配も感じられるようになったと思います。夜になると、虫の音が
聞こえますよね。
秋と言うと、代表的な食べ物として秋刀魚(さんま)があります。漢字でも秋の魚と分かる表現が
されています。今年はさんまの漁獲産地である北海道で8/6に解禁されました(解禁されたのは
10トン以上20トン未満の小型船だったようです)。又、10年連続でサンマ水揚げ量日本一の花咲港
でも37隻が前年とほぼ同じ約200トンを水揚げしたそうです。全国さんま棒受網漁業協同組合
(全さんま)は、8/17に釧路市内で開いた理事会で、100トン以上の大型船が出漁する8/19から
9/2までの水揚げ自主規制の内容を決め、昨日、サンマ漁業者でつくる「全国さんま棒受網漁業協同
組合」(全さんま、東京)と「道東小型さんま漁業協議会」(釧路)の所属船230隻が100トン以上
の大型船出漁の解禁日に合わせて、一斉休漁日としたことがニュースとなりました。 花咲市場に
よると、8/6の解禁日の浜値は180グラム前後の大型魚がほとんどで、脂の乗りも良かったのですが
昨年より100円安い、1キロ200円だったそうです。
全国さんま棒受網漁業協同組合が決めた9/2までの水揚げ規制は、道内港に水揚げする場合、すで
に操業している中・小型船を含め3グループに分けてローテーションを組み、3日に1回ずつ交代で
水揚げし、大型船で計140トン以下とするなど、船の大きさに応じて水揚げ量に上限を設定したそう
です。その影響なのか、サンマの浜値は小型船解禁直後の7日、1キロ当たり30~40円台まで暴落
し、その後は水揚げ減などもあって、一時は1,000円前後に高騰するなど乱高下したそうです。
その後は100円~200円に落ち着いているとのことです。
価格は需要と供給によって決められるのが常です。農産物、水産物はその典型です。その為、市場
に大量に持ち込まれると(豊作、豊漁)価格は一気に下がります。逆に少ないと極端に価格が上がり
ます。但し、農産物、水産物ともコストがあるわけであり、原価割れでは赤字となってしまい商売が
成り立たなくなるのですが、これら一次産品においてはコストを考慮した価格の設定がされません。
魚においては消費者の魚離れも影響してか、販売側(スパー)が売りたい価格を設定し、その逆算
で購入価格が決まるといった現象も生じていると聞いたことがあります。売り手側主導の価格政策と
言うわけです。その状況と燃料費の高騰によるコストアップを考えると、漁に出ないほうが良いと
いう結果になってしまうわけです。農産物の場合は、仮に同じ状況になっているとしても、生産調整
ができる分だけ深刻ではないかも知れません。しかし、今年は出荷されずに大量に捨てられた多くの
野菜があることを聞き流通の仕組みが何とかならないものかと考えざるを得ません。
政府は総額745億円の漁業者支援を決めているそうですが、漁業関連者一人当たりに換算すると、
いくらの支援になるのでしょうか?小遣い程度の金額であれば焼け石に水、効果はありません。この
際根本的な漁業対策費として、その場限りでないお金の使い方にしてもらいたいものです。
「さんまは目黒に限る」という、落語がありますが、たまたま庶民(目黒の)が食べていたサンマを
殿様が食べ、おいしかったことから、そのように言われたようですが、目黒だからおいしかったわけ
ではなく、油ののったサンマだったからです。殿様もおいしいといったサンマ、庶民がおいしく食べる
ことのできるサンマの値ごろ感のある価格はいったいいくらなのでしょうか?100円ですか?200円
ですか?それとも300円ですか?200円、300円であれば当方は妻と1匹を半分づつ食べますが....
それでも、食べたいと思いますよね。
瞬間を立秋と言うそうです。残暑見舞いの時期となったということです。まだまだ、暑い日が
続きますが、なんとなく秋の気配も感じられるようになったと思います。夜になると、虫の音が
聞こえますよね。
秋と言うと、代表的な食べ物として秋刀魚(さんま)があります。漢字でも秋の魚と分かる表現が
されています。今年はさんまの漁獲産地である北海道で8/6に解禁されました(解禁されたのは
10トン以上20トン未満の小型船だったようです)。又、10年連続でサンマ水揚げ量日本一の花咲港
でも37隻が前年とほぼ同じ約200トンを水揚げしたそうです。全国さんま棒受網漁業協同組合
(全さんま)は、8/17に釧路市内で開いた理事会で、100トン以上の大型船が出漁する8/19から
9/2までの水揚げ自主規制の内容を決め、昨日、サンマ漁業者でつくる「全国さんま棒受網漁業協同
組合」(全さんま、東京)と「道東小型さんま漁業協議会」(釧路)の所属船230隻が100トン以上
の大型船出漁の解禁日に合わせて、一斉休漁日としたことがニュースとなりました。 花咲市場に
よると、8/6の解禁日の浜値は180グラム前後の大型魚がほとんどで、脂の乗りも良かったのですが
昨年より100円安い、1キロ200円だったそうです。
全国さんま棒受網漁業協同組合が決めた9/2までの水揚げ規制は、道内港に水揚げする場合、すで
に操業している中・小型船を含め3グループに分けてローテーションを組み、3日に1回ずつ交代で
水揚げし、大型船で計140トン以下とするなど、船の大きさに応じて水揚げ量に上限を設定したそう
です。その影響なのか、サンマの浜値は小型船解禁直後の7日、1キロ当たり30~40円台まで暴落
し、その後は水揚げ減などもあって、一時は1,000円前後に高騰するなど乱高下したそうです。
その後は100円~200円に落ち着いているとのことです。
価格は需要と供給によって決められるのが常です。農産物、水産物はその典型です。その為、市場
に大量に持ち込まれると(豊作、豊漁)価格は一気に下がります。逆に少ないと極端に価格が上がり
ます。但し、農産物、水産物ともコストがあるわけであり、原価割れでは赤字となってしまい商売が
成り立たなくなるのですが、これら一次産品においてはコストを考慮した価格の設定がされません。
魚においては消費者の魚離れも影響してか、販売側(スパー)が売りたい価格を設定し、その逆算
で購入価格が決まるといった現象も生じていると聞いたことがあります。売り手側主導の価格政策と
言うわけです。その状況と燃料費の高騰によるコストアップを考えると、漁に出ないほうが良いと
いう結果になってしまうわけです。農産物の場合は、仮に同じ状況になっているとしても、生産調整
ができる分だけ深刻ではないかも知れません。しかし、今年は出荷されずに大量に捨てられた多くの
野菜があることを聞き流通の仕組みが何とかならないものかと考えざるを得ません。
政府は総額745億円の漁業者支援を決めているそうですが、漁業関連者一人当たりに換算すると、
いくらの支援になるのでしょうか?小遣い程度の金額であれば焼け石に水、効果はありません。この
際根本的な漁業対策費として、その場限りでないお金の使い方にしてもらいたいものです。
「さんまは目黒に限る」という、落語がありますが、たまたま庶民(目黒の)が食べていたサンマを
殿様が食べ、おいしかったことから、そのように言われたようですが、目黒だからおいしかったわけ
ではなく、油ののったサンマだったからです。殿様もおいしいといったサンマ、庶民がおいしく食べる
ことのできるサンマの値ごろ感のある価格はいったいいくらなのでしょうか?100円ですか?200円
ですか?それとも300円ですか?200円、300円であれば当方は妻と1匹を半分づつ食べますが....
それでも、食べたいと思いますよね。
Posted by walt at 20:45│Comments(0)