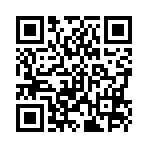2008年05月08日
333) 株式会社武蔵野 小山社長のコラム
以前も何度かブログに取り上げたことがありますが、株式会社武蔵野の小山社長のコラムで共感の
もてるものがありました。GW前の4/28に日経BPネットに掲載されたものです。タイトルは「わたしは
社員に『感謝の心』を教えている」というものです。以前4月に「袋叩きの社会保険庁を少しだけ擁護
する」というタイトルで書いたコラムが多くの方の反感を買ってしまったことがありましたが、小山社長
らしい考えであり、当方も小山社長を擁護したくなったこともあります。
今回の「わたしは社員に『感謝の心』を教えている」は、社員教育を長い時間とコストをかけてやって
いるが、その内容はビジネスマナーや、パソコンの操作、商品知識、社内の各種制度の研修ではなく、
「感謝の心を教える」と言うものだそうです。コラムの中で「我が社に利益をもたらしてくださるお客様に
感謝する。ビジネスパートナーに感謝する。人との出会いに感謝する。自分を育ててくれた両親に感謝
する‥‥。わたしが感謝を教える理由は簡単です。それこそが利益の源泉だからです。同じサービス
をするのでも、根底に感謝の心があるのとないのとでは、お客様への接し方が大きく違ってくる。それ
はお客様満足度の高低にも直結します。極端な話、商品知識はまるでないが感謝の心のある営業
担当者と、商品知識は万全だが感謝の心は皆無の営業担当者とでは、前者のほうがお客様満足度は
高い。利益は、お客様に喜ばれた結果です。」と。
過去に営業研修を受けたことがありますが、どちらかというと営業のテクニックだったように感じます。
小山社長がおっしゃるような「感謝の心」は教わりませんでしたし、そのようなことをいう上司もいま
せんでした。営業であれば、売ってなんぼの世界であり、数字を作ることが使命でした。お客さんの
事をまず第一に考えていなかったと思います。「儲ける」という漢字は「信者」を作ることを意味し、
給料は会社からもっらっているのではなく、お客様から頂いていること。そのような考え方も、セミナー
や、本などから学びました。そして自分なりに「誠実であること」、「お客様にとって利益になること」
を心がけています。要するに「感謝の心」が根底になければできないことです。改めて、「感謝の心」
の重要性を知りました。どんなシチュエーションでも「ありがとう」という感謝の言葉が使用されて
います。「ありがとう」と言われて気分を悪くすることはめったにありません。
現在、中国の胡錦濤国家主席が来日しています。中国語では「謝る(ごめんなさい)」という言葉を聞く
機会がありません。もしかしたらないのではないかと思うほどです。しかし、「感謝(ありがとう)」は
よく聞きます。スピーチ、文章の終わりに「謝謝合作」という言葉が使用されます。日本語はどうでしょ
うか?謝る言葉はよく聞きますが、感謝の言葉のほうが少ないような気がします。スピーチの終わりに
「ご清聴ありがとうございます」と言いますが、文章の最後には感謝の言葉は使用しませんね。文化の
違いかもしれませんが、あえて「感謝の心」を伝えなければ(教えなければ)ならない時代になってしま
ったかもしれません。
また、そんなことを思った一日でした。
小山社長のコラム: http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/aa/103/
もてるものがありました。GW前の4/28に日経BPネットに掲載されたものです。タイトルは「わたしは
社員に『感謝の心』を教えている」というものです。以前4月に「袋叩きの社会保険庁を少しだけ擁護
する」というタイトルで書いたコラムが多くの方の反感を買ってしまったことがありましたが、小山社長
らしい考えであり、当方も小山社長を擁護したくなったこともあります。
今回の「わたしは社員に『感謝の心』を教えている」は、社員教育を長い時間とコストをかけてやって
いるが、その内容はビジネスマナーや、パソコンの操作、商品知識、社内の各種制度の研修ではなく、
「感謝の心を教える」と言うものだそうです。コラムの中で「我が社に利益をもたらしてくださるお客様に
感謝する。ビジネスパートナーに感謝する。人との出会いに感謝する。自分を育ててくれた両親に感謝
する‥‥。わたしが感謝を教える理由は簡単です。それこそが利益の源泉だからです。同じサービス
をするのでも、根底に感謝の心があるのとないのとでは、お客様への接し方が大きく違ってくる。それ
はお客様満足度の高低にも直結します。極端な話、商品知識はまるでないが感謝の心のある営業
担当者と、商品知識は万全だが感謝の心は皆無の営業担当者とでは、前者のほうがお客様満足度は
高い。利益は、お客様に喜ばれた結果です。」と。
過去に営業研修を受けたことがありますが、どちらかというと営業のテクニックだったように感じます。
小山社長がおっしゃるような「感謝の心」は教わりませんでしたし、そのようなことをいう上司もいま
せんでした。営業であれば、売ってなんぼの世界であり、数字を作ることが使命でした。お客さんの
事をまず第一に考えていなかったと思います。「儲ける」という漢字は「信者」を作ることを意味し、
給料は会社からもっらっているのではなく、お客様から頂いていること。そのような考え方も、セミナー
や、本などから学びました。そして自分なりに「誠実であること」、「お客様にとって利益になること」
を心がけています。要するに「感謝の心」が根底になければできないことです。改めて、「感謝の心」
の重要性を知りました。どんなシチュエーションでも「ありがとう」という感謝の言葉が使用されて
います。「ありがとう」と言われて気分を悪くすることはめったにありません。
現在、中国の胡錦濤国家主席が来日しています。中国語では「謝る(ごめんなさい)」という言葉を聞く
機会がありません。もしかしたらないのではないかと思うほどです。しかし、「感謝(ありがとう)」は
よく聞きます。スピーチ、文章の終わりに「謝謝合作」という言葉が使用されます。日本語はどうでしょ
うか?謝る言葉はよく聞きますが、感謝の言葉のほうが少ないような気がします。スピーチの終わりに
「ご清聴ありがとうございます」と言いますが、文章の最後には感謝の言葉は使用しませんね。文化の
違いかもしれませんが、あえて「感謝の心」を伝えなければ(教えなければ)ならない時代になってしま
ったかもしれません。
また、そんなことを思った一日でした。
小山社長のコラム: http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/aa/103/
Posted by walt at 23:33│Comments(0)